ふ〜・・・完全なる寝正月を過ごしてしまった。明日から仕事。平常運転に戻らねばならない。うま煮は三が日どころか,二日目で全部平らげてしまった。植物繊維をたっぷり取ったせいか,便通がいい。ケツの穴が楽なのは久しぶりである。
箱根駅伝は早稲田と駒大との一騎打ちになって,駒大が優勝。日東駒専がメディア上で活躍できる数少ない機会だが,日大は相変わらずシード権を確保するレベルに留まっているのが残念。学生数だけなら文字通り日本一なのだが,選手の出身学部を見ると殆ど文系学部,たま〜に理工学部が混じるだけだな。つまり真面目に勉強しなきゃダメな学部からは(以下略)。ともかく,もうちっと頑張れ。
今日は寝て起きて飯食って寝て・・・で一日が暮れた。寝過ぎたせいで頭が痛い。土曜日は東京往復なので,それまでに2回目の査読報告をせねば。ま,ワシ以上にいっぱい文句付けた第一査読者の指摘のおかげであらかた直っているようなので,あまりコメントすることもなさそうだが。
いつの間にやらここにupしたエントリ数が1000を超えたようだ。日記開始以来,今年は10年目を迎えるし,blog形式に変更してからも5年目となる。ぽっつんぽっつん,断続的に止まるともなく,さりとて爆発的人気を得ることもなく,コメント機能もoffにしてあるから炎上することもなく続いているのも,このシステムが性に合っているからなんだろうな。今のところ止めるつもりもないが,ある日突然打ち切りにする可能性がなきにしもあらず。ま,続く時は続く,終わる時は終わる,全てはなるようになるのである。無理せずマイペースでやっていきます。
昨年からやり残したぷちめれを書いたら寝ます。
1/1(火・祝) 掛川・晴
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。
2008年の初日はピーカン晴れ。遠州名物空っ風が強い。日本海側は大雪のようだ。
昨年は過去最大の仕事量だったが,今年は少し減らす予定。いい加減,レベルはともかく,査読論文を継続的に書いていかないとねぇ。ワシの場合,完全な単著となるので,年に1〜2本あればかなり上出来な方。acceptされるかどうかは置いておいて,このレベルを今後10年は続けたいなぁ・・・と,希望的観測。査読ばっかりしている評論家にだけはなるまいぞ。
大晦日は一日中,煮物を仕込んでいた。ワシの場合,おせち料理としてはうま煮(筑前煮)だけあればよく,これに年越しそば兼雑煮汁が加われば,他には何もいらない。とはいえ,余った材料をほったらかしにするのももったいないので,きんぴらも作った。これで全ての食材を使い切る。
煮込み料理ってのは場数を踏まないと上達しないものであるが,大分修行を積んだので,今年のうま煮は最高の出来となった。

絹さやの緑,銀杏の黄,人参の赤が入って色のバランスは完璧なのだが,全体的に薄味になったのと,百合根をもうちっと煮込む必要があったかな,という2点については改善の余地有り。来年への課題としよう。
ボウル一杯分になってしまったが,こんなに作っても三が日に全部平らげてしまうのであった。
さてボチボチ散歩がてらの地元初詣でもしますか。
ただいま。10円でどれほどの御利益があるかどうか不明だが,現在の全財産が

しかないんだから致し方なし。でも今は元旦でもコンビニATMが使えるんだよな。今のところ,三が日に銭を使う用事は他にないけど。
らき☆すた特需に沸く地元。うーむ・・・。
ボチボチ過ごします。
わかつきめぐみ「シシ12か月」白泉社
[ Amazon ] ISBN 978-4-592-14278-2, ¥752
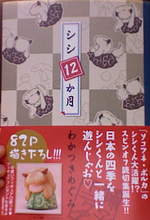
日本の土着神をファンタジー漫画の主役として登場させる時,そこに住む人間との関わり方には幾つかのパターンがある。その一つとして,人間社会の変化を直接あるいは間接的に引き受けるというものがある。人間がいてこその神,というのは紛れもない事実であるから,これは自然な神のあり方と言える。
例えば手塚治虫の「火の鳥・太陽編」では,壬申の乱の原因の一面を象徴するものとして八百万の神と仏教神との戦いが描かれるし,あとり硅子の「夏待ち」では,そろそろ過疎地の住民からは忘れられつつあるお稲荷様が主役の一人を張っている。夢路行の主様シリーズでは,神とも妖怪とも宇宙人とも解釈できる「主様」と他の土着神や鬼との交流が描かれるが,雪の神の一族は次第に山奥へと追いやられていく過程にある。
これらに共通するのは,古の日本では神と人間が安定した共存関係にあったという幻想が土台にあるということだが,これはあくまで幻想でしかない。もともと神という概念自体,近代においては科学的に否定されたものであり,人間社会のありように付随する浮遊的なものでしかない。つまり,過去においても安定したものであった試しがないものだ。だからこそ,神は常に人間から畏怖されたり唾棄されたり都合良く愛されたりしながら,人間が共有する概念として,変化しながらも存在し続けているのである。
わかつきめぐみが描く土着神が主役のシリーズも,単なるほわほわとしたファンタジーから変容し続ける人間社会の一端を担うように変化してきたが,それは今まで述べてきたように,神という存在を考えれば自然な帰着と言えよう。そしてその変化の結果,わらわらと画面を賑やかにしてきたキャラクター達には,我々人間が抱いている感情のメタファーとしての役割が担わされるようになっているのである。
「シシは土地神さまの所に住んでいます」というのが本書の冒頭の文句だが,タイトルロールの「シシ」にはこれ以上の説明はない。ちょっとエキセントリックなイケメンの土地神は,インテリジェンスと爆発する感情との間を往復しながら12ヶ月を過ごす存在であるが,シシはその土地神に何の影響も与えない存在で,愛玩動物としての役割も果たしていない。が,自身の存在が人間から忘れられつつある土地神がキセル煙草をくゆらせながらシシ相手に語るシーンにおいて,シシは我々人間が持つ「よく分からないけどそこにいる第三者」としての機能を担うようになった。たぶん,シシは村上春樹が言うところの「うなぎ」(分からない人は「村上春樹にご用心」でも読んで下さい)なのである。睦月から師走まで,愛嬌やトラブルを振りまいてくれはするものの,それはストーリー全体の本筋を直接担ってはいない。多分,天性のファンタジー作家・わかつきめぐみは,本書において,ストーリーを間接的に語ることに挑戦したのだ。シシと土地神のお付きの者どもが織りなすエピソードを介して,ワシみたいな読者が「勝手に物語る」作品を作り上げてしまったのである。つまり本書は「機能としての漫画作品」になってしまったのだ。・・・ってのはおおげさかな?
神という存在が共同幻想であることが明確になった今でも,いや今だからこそ,神は求められている。この先,日本の少子高齢化が進展するにつれ,限界集落が増え,うち捨てられる土地の寺・神社・地蔵も増えていくに違いない。しかしそれでも人間が全滅しない限り,土着神信仰もまた全滅することはないのだ。本書において,仲間が減りつつあることに嘆息する土地神は,悩みながらも破れかぶれになることはない。それはタネマキという謎の存在が置いていった種に希望を託しているからという単純な理由ではない。タネマキがいようといまいと,傍らで話を聞くシシさえ居てくれればいいのだ。そして我々人間が季節の変わり目を意識さえしていれば,土地神もまたそれに合わせて行動してくれるはずなのである。
今日は大つごもりである。今夜は一年を振り返って土地神とシシ共々しみじみとし,年が明けたら近所の社を巡って彼らの存在に思いを馳せようと考えている。
来年もよろしくお願い致します。
雅亜公「シークレット・ラブ」I, II, III,芳文社コミックス
シークレット・ラブ I [ Amazon ] ISBN 4-8322-3058-1, ¥552
シークレット・ラブ II [ Amazon ] ISBN 4-8322-3071-9, ¥552
シークレット・ラブ III [ Amazon ] ISBN 978-4-8322-3094-1, ¥552
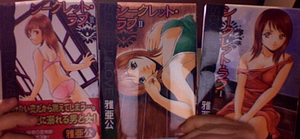
いや〜,エロ特集をすると予告しておきながら,年末に入ってしまうとテンションが落ちてしまい,殆どらしいことが出来なかった。だもんで,最後に書きたいことを全部書いてしまうと共に,これだけは紹介しておかねばらならないという3冊をご紹介することで,お詫びに代えたいと思う。
最近の2次元フェチな若者どもがどんなエロマンガを読んでいるのかを知るため,それなりにこの分野のマンガを渉猟し,何冊かは買って読んでみたのだが,いや〜,なんつ〜か,やっぱこの分野,進化が早いというか,もはや中年親父のワシには付いていけない所まで逝っちゃっている。SEX中の男が透明人間になるとか,巨乳女性はもはやホルスタインの化け物のような肉の塊になっちゃっているとか,性器の露出が殆ど欧米並みになっているとか(秘宝館が廃れる訳だ),ともかく凄い。一体どうやったらこんなホラーみたいなマンガを夜のおかずにできるのか,おじさんにはさっぱり理解不能である。Web上では全世界規模で実物が拝めるので,フィクションの世界では極端に走らないと刺激が足りないのかしらん? 中には完全なラブコメ&スポ根マンガの構成でありながら,スポーツの代わりにSEXをしているというものもあって,著者の意図とは別に大爆笑しながら読ませて貰ったが,おっさんとしてはもはやこの分野,トンデモ的な楽しみ方をしないとついて行けない所まで逝ってしまっているのだ。
ただ,この極端な変化は男性向けのエロマンガに限られるようである。女性漫画家が担当することの多い女性向けエロマンガの方は,そこまでファンタジック(と言っていいのかどうか?)な進化は遂げていないようで,まだ何とか「実用」に耐えうる程度に留まっている(BLは別ね)。つーか,今時,恋愛の中にSEXが登場しないというのも不自然である上に,女性にとってのSEXはどうしても妊娠という可能性を孕むものだから,幻想の上に乗っかって射精だけしていればいい男とは違う,生々しい現実を伴うものなのである。それ故に,化け物同士のくんずほぐれつなんぞ見せられても困るのであろう。
従って,同じエロでも男性よりは女性の漫画家が描いたものの方が現実離れしていないのではないか。徹底して男向けに描いたとしても,どこか違和感を抱えてしまうのではないか,と思えるのである。で,その違和感に誠実であればある程,男性奉仕のための作品からは離れていくのが自然の成り行きなのであろう。男性漫画家でも,エロから入って徐々に普通のマンガへシフトしていった一群としては,吉田戦車,山本直樹,陽気碑などが挙げられるが,彼らもどこか単なるエロには飽き足らなくなっていたのではないか。女性ならばなおのこそ,と,ワシには思えて仕方がないのだ。
そんな一人がこの「シークレット・ラブ」というベタベタなタイトルの短編集を描いた,雅亜公(まあこう,と読む)なのだとワシは勝手に確信しているのである。もし男性だったらごめんなさい。女性同士が使うあだ名のようなペンネームと,単行本の著者コメントで判断する限り女性と思われるので,以下ではそう仮定してぷちめることにする。
さて,この3冊の単行本の表紙を見て(写真参照),これがエロマンガではないと思った人はいないだろう。ワシもそのつもりで(どんなつもりだ)買ったのだが,その期待は半ば裏切られたのである。半ば,というのは,確かに本書に収められている作品にはSEXが描かれているのだが,ストーリーが面白いため,SEXが単なるお色気成分に成り下がっているからである。つまり本書はSEXを見せることではなく,SEXにまつわる男女の物語を描くことが目的の作品群だったのである。
特に感心したのは,女性キャラの心理描写が巧みなことである。まあ女性が描いている(たぶん)のだから当然と言えば当然なのだろうが,掲載誌は「別冊週漫スペシャル」である。小汚いラーメン屋に置いてあるマンガ雑誌に,SEX後に雨の音を聞きながら男と語らう行きずりの女性を描いたり(第6話「雨宿り」),既婚女性が男からコートをかけて貰ったことに「こんなことしてもらうの何年ぶりだろ」「女の子扱いしてもらったみたいで何か嬉しいな・・・」と少しジンとしたり(第26話「アイ・ニード・ユー」)というような繊細な女性の心理描写が描かれている作品が掲載されているなんて,時代も変わったものだと思わざるを得ない。絵柄はデビュー当時の金井たつおを思わせる,端正なデッサン力と可愛らしさを伴ったもので,確かに男臭い雑誌に載っていても違和感はないレベルである。しかし,単行本3冊になる作品を描き続けられたのは,絵柄だけではない,ストーリーの持つ魅力があったからこそなのであろう。そして,その魅力は女性心理描写の巧みさがあったればこそなのであり,今はそれを週漫の読者が支持する時代になったのである。
この作品群は3冊の単行本にまとめられているが,1巻よりは2巻,2巻よりは3巻に感心させられるストーリーが増えている。女性心理描写が巧みなのは全てに共通しているのだが,その上に構成させるシチュエーションが段々凝ってくるのである。
ワシが一番感心したのは,3巻巻頭の第21話「言えなかった言葉」である。これは電車の中で痴漢行為を働いてしまった男が主人公で,その男が好きになった相手が実は痴漢の相手だった・・・というものである。男にとって一方的に都合のいいエロマンガばかり読んでいる輩には少し苦いものを残すかもしれないが,それ故に,ワシはマジにこの作品,道徳教材として使えるのではないかと思っている。純粋エロを求めて買ったワシにとっては意外だったが,マンガとして楽しめたのに味を占め,この漫画家の作品を全部買ってしまったのは当然の成り行きと言えよう。
雅亜公の最新作「ラビリンス Vol.1」は,「シークレット・ラブ」の一短編を拡大したような不倫ものの長編であるが,ベタなタイトルが相変わらずなのはいいとして,今のところは間延びした作品という印象が強く,切れ味という点では短編の方がお勧めである。まだ始まったばかりなので,これについては今後に期待することにして,今は在庫がある「シークレット・ラブ」3冊で楽しむことをお勧めしたい。
12/29(土) 掛川・晴
順調に全ての予定が停滞中である。まー世の中そんなモン。出来ることをやっていくしかないのである。
自炊飯のための買い物以外はずーっと自宅でダラダラ。これがマンションになるとますます自堕落になりそうである。うーむ,Wii & Fitでも買って室内運動に励むか。
大鍋一杯に作ったおでんは三日で平らげてしまった。明日&明後日はカレーで過ごす予定。自炊だけだとホント,金が掛からないな。
ナイスステップな研究者の発表。九大の中尾先生が受賞。人材育成とのこと。なーるほど。
それにしてもこの賞のネーミングセンスを何とかした方がいいと思う。
停滞しながら寝ます。