肌寒い日が続くな~。今週末からは平年並みの気温に戻るようだが。花冷えって奴か?
首を長ーくして待っていたCentOS 5.3,やっとMirrorへの配布が始まった模様。正式アナウンスはもうすぐのようだ。ちらっと日本のミラーサイトを覗いたら,CD imageは届いていたりする。はよDVDも欲しいものである。いまさらCD7枚も使いたくないよなー。
ともかく入手できたらCore i7マシンにとっとと突っ込んでインストールしなきゃぁ。無駄な電気食いマシンをこれ以上放置しておくわけにはいかんからな。
ちょうど,XenServerがノード数無制限のまま無償化というニュースが入った。一度チャラにしてクラスタを組みなおす予定なので,ちょっと遊んでみようかという気分にはなる。解説ビデオを見る限りはかなり便利そう。問題は共有データストレージが必要になることで,iSCSIを推奨とのことだが,安いTerastation iSCSIでも10万以上はする。そんな予算はない。Linux boxをiSCSI targetにできるようなので,ストレージマシンを作るか,NFS serverも使えるみたいなので,運用的に問題がなければそっちを使うという手もあるか。・・・しかし遊んでいる暇はなさそうなところが困ったことだ。8月後半までは無理かなぁ。
「習熟度別授業、効果出ない例も」(朝日新聞)。
いわゆる「できが良くない生徒」をどうやったら引き上げることができるか。もちろん「できる」という前提で言っているのだろうが,うーん,無理なケースも多いんじゃないのか。ワシもできない部類の人間だったから言っておくけど,同じ学習内容でも習得に必要な時間というのは個人差がでかいのだ。
むしろ,できない子は小中高の早いうちに留年させるという仕組みも必要かと思う。大学に入ってから留年したんじゃ,学費がかかって仕方がない。習得速度に差があるのは当たり前のことなので,内容が高度になる前に留年してもう一度同じ内容を学習させるってのは悪い方策ではないと思うんだがな。
問題は留年した場合の経済的・精神的ケアか。留年制度が定着して,一教室に二けた程度のダブり生徒がいるとなれば,おのずと留年のショックは和らぐ・・・ってのは楽天的すぎるかなぁ。しかし日本の大学進学率がこんだけ高くなると,まずベース部分の学習をきっちりやっておかないと学士号の質の担保なんぞ不可能だ。小中高で留年あるいは復習学習を定着させるか,大学で小中高で足りなかった部分を補わせるのか,具体的な方策を作り上げていかなきゃならんよなぁ。
さて明日からは新年度始まり。予算不足でぶっ壊れていたプリンタだのマシンだのを修理せねばならず,朝一番で予算申請しておかねば~。
つーことで一仕事したら寝ます。
漫画家デビュー物語:吾妻ひでお「地を這う魚 ひでおの青春日記」角川書店,小林まこと「青春少年マガジン1978~1983」講談社,久世番子「わたしの血はインクでできているのよ」講談社
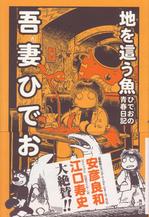
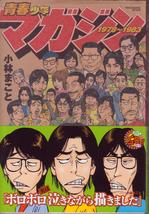
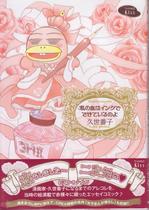
吾妻ひでお 「地を這う魚」 [ Amazon ] ISBN 978-4-04-854144-2, \980
小林まこと 「青春少年マガジン] [ Amazon ] ISBN 978-4-06-375618-0, \933
久世番子 「私の血はインクでできているのよ」 [ Amazon ] ISBN 978-4-06-337661-6, \667
青春は光り輝く時代,なんて嘘っぱちを流しやがったのはどこのどいつだ。少なくともワシが見聞した限り,高校から大学を経て社会人になり数年過ごすあたりまでの時代をもう一度繰り返したいと願う人間は皆無であった。曰く,「体力・気力はあったけど思い返すだに恥ずかしいことばかり」「思い通りにならないことばかりで嫌気がさした」「四畳半の下宿で引きこもり生活になってしまって十二指腸潰瘍を発症して病院に担ぎ込まれた」・・・などなど,まーロクでもない思い出したくもないことばかり。知識経験不足のバカで貧乏だったにも関わらず,鼻息だけは荒いクソガキだったワシなぞは,あの当時のことを思い出すと身悶えしたくなるほどである。少なくとも人並みの世間体ってものを身に付けるまでの,そーだなー,三十路前半までの人生はなかったことにしておきたいと思っているのである。
だがしかし,だ。今の自分があるのは,穴掘って埋めてコンクリ詰めにした数多のみっともない経験が土台となっているからであって,今更隠したところでしゃーないではないか,とも理性では思うのである。自分にどんな才能があり,どんだけの力量が発揮できるかは,それが試されるような出来事がなければ一生分からないまま。BSマンガ夜話で夢枕獏が「才能ってのは汲んでみなければ分からない。もう滅茶苦茶な状況になって汲み出し続けて『これまでかぁ』と精も根も尽き果ててようやく分かる」と言っていたが,よほど幸運な人間でない限り,一定の地位を社会に築くまでは「めちゃくちゃな状況になって汲み出し続ける」作業を若い時分に経験するものなのであろう。それ故に,そんなきつい経験は二度とゴメンだ,と思うのが普通の人間の青春の有様なのだ。
ここで取り上げる3冊のマンガのうち,「地を這う魚」と「私の血はインクでできているのよ」(長ぇよ)は吾妻ひでおと久世番子がデビューするまでの「みっともなさ」の軌跡を描き,「青春少年マガジン」はデビュー後の過酷な週刊誌連載を闘ってきた小林まことが,早世した同期漫画家・小野新二と大和田夏希らとのさまざまな思い出を切々と描いている。3冊に共通しているのは,デビュー前後の時代は誰しも精神的・肉体的にきっつい思いをするものだ,ということを隠さずに語っていることだ。この度めでたく(?)四十路の仲間入りをしたワシは,漫画としての面白さと共に,彼らの誠実さに感銘を受けたのである。以下,それぞれのマンガ作品について,面白さと感銘のポイントを語っていこう。
○吾妻ひでお「地を這う魚 ひでおの青春日記」
失踪直前に描いていた「夜の魚」シリーズは,広くて暗い昭和40年代を彷彿とさせる街中を主人公・吾妻ひでおとその仲間たちが徘徊する,独特の雰囲気を持った作品だった。大塚英志・責任編集のComic新現実の著者インタビューを読んで,それが実際に吾妻ひでおが北海道の仲間たちと上京してデビューに至るまでの出来事をファンタジー風味にした作品と知った。そのインタビュー中に大塚が吾妻に直接依頼をして始まった新たな「魚シリーズ」が,Comic新現実→新現実→コミックチャージ(休刊が決定)と場所を移しつつ,この度ようやく一冊にまとまった。それがこの「地を這う魚」である。
吾妻ひでおは,「うつうつひでお日記」(P.183)でこの新シリーズ作品を次のように評している。
今回の「地を這う魚」は
以前描いた「魚シリーズ」
のような狂気や迫力
恐怖感を出せませんでした
今の自分には
あの続きを描くのは
無理のようです
吾妻自身は,何故あのような「キ○チガイ漫画を描けたのか分からない」としているが,やはり失踪直前の精神状態と,恐ろしいほどの画力と色気のブローアップ時期にあったことの両方が作用して,あのような傑作が描けたとワシは推察している。こんなことを言うとまた吾妻が傷つくかもしれないので言いづらいが,ええい言ってしまおう。ワシは今でも失踪直前,1980年代後半の吾妻ひでおの絵・作品が最高だと思っているのである。
その時代を知っているワシから本作を見る限り,少なくとも最初の,Comic新現実に描いていたいた自分の作品は,若干の狂気の香りは感じられるものの,まだ本調子ではないな,と感じてしまうのである。作品のコンセプトも変わっており,キャラクターは同じであるが,オムニバス的にファンタジーとして描かれていた旧「魚シリーズ」とは異なり,時系列的に,秋田書店でデビューが決まるまでの出来事が並べられている。まさに大塚が名づけたキャッチフレーズ「吾妻ひでおの青春」が描かれているのだ。
本調子ではない,と思っていたワシであるが,今回こうしてまとまったものを読むと,どんどん「リハビリ」が進み,荒っぽかった線が精緻になり,文字通り「地を這う魚」の数は画面いっぱいを埋め尽くすほどに増殖していることが分かり,吾妻ひでおのクリエーターとしてのプライドの凄みを思い知ることになった。
コマの隅から隅までうぞうぞしている魚以外の生物も多様だ。タコ,イカ,イモリ,ヤモリ(区別がつかんが),昆虫やロボットまでが,社会の構成員としてみっしりと詰まっている。仲間以外の他人は,その存在以外は無意味であるから,何も人間の形をしている必要がない,ということを本作を読んで深く納得した。日々の食いブチにすら事欠く毎日を,仲間と戯れつつ描く本作は,旧シリーズとは別物ではあるけれど,普通に暗い東京における青春を描いた良作であることは間違いない。
○小林まこと「青春少年マガジン 1978~1983」
目は口ほどにものを言う,という格言は,この小林まことの漫画には当てはまらない。逆だ。小林作品ほど,口が目以上に生き生きと表情を作り出しているマンガは,今の日本には見当たらない。への字に曲がった口,たばこの煙を吐き出す河童のような口,キュビズム作品の如くパースが狂った半開きの口,固い意志を表わす左下から右上に伸びる直線上に固く結ばれた口,「びぎえぇえええええん」と咆哮する鉄アレイ口・・・まー,小林作品のキャラクターの口はホントに見ていて飽きない。つーか,口が刻むリズムで読まされているように思えるんだが・・・錯覚だろうか?
小林作品に共通する大衆的ユーモラスさに乗って読み進んでいくと,少年マガジンの賞を獲り,同時期にデビューした小野新二や大和田夏希と「新人3バカトリオ」を結成する所までは,過酷な連載をこなす様も面白く眺めていられる。しかし・・・,あまり書いちゃうとネタばれになるので詳細は省略するが,メジャー週刊誌の連載ほど人気と自己評価の狭間で苦しむ世界はないな,ということをジワジワと読者に伝えてくるあたりから・・・となってくるのである。ま,その辺を知りたければ本作を買って読んで下され。
最終的には小野も大和田も1990年代中盤に逝去してしまうのであるが,これらの死を単純に「過酷な人気商売の故」としてしまうのは,ちょっと違うような気がする。大なり小なり他人との比較による評価を受けるのは現代社会では当たり前のことで,漫画ビジネスの世界ではそれが極端に変動する収入や人気として跳ね返ってくるというだけのことだ。それを自分が受け入れて飼い慣らしていくことができれば,ホントにそれ「だけ」のことなのである。他人による自分という人間の評価に対してどのように精神の安定を保つか,あるいはそれをバネにしてモチベーションを高めるか。現代人であれば,引退するまで悩み続けなければならない宿命なのである。
小林まことが生き残ってきたのは,締め切りをぶっ飛ばしたり,授賞式を大遅刻したりする,確信犯的ズボラさがあったればこそだろう。本書を読む限り,とことん真面目な他の二人は悩みをストレートに抱え込んでしまったり,酒で発散させてしまっているために,早く天に召喚されてしまったと感じられる。もちろん,小林まことの作品が広く支持されているからこそズボラが可能であるとも言えるが,ワシは逆だと思っているのである。
何故なら,川崎のぼるを源流としてその延長上に表情を獲得した小林まことキャラの口は,明確な意思の現れであるからだ。呆けたり歯を食いしばったりナナメ一文字に結んだりするためには,描きながら作者自身が同じことをしなければならないのだ。つまりは作者の意思があってこそのものなのである。ズボラ決め込むことができるのも,まずは「どーでもいーや」と投げ出す意思があってのことなのだ。
まさに,小林まことの漫画家人生は,「口」の作る表情がすべてを物語っているのである。
○久世番子「私の血はインクでできているのよ」
シリアスな匂いのする2作に比べ,本作はあの暴れん坊本屋さんこと久世番子が軽やかな語り口のエッセイ漫画に仕立てたものであるから,気楽に笑って読める・・・のは一般人の証。一度,漫画家に憧れてめったやたらに漫画を書きまくった経験のあるオタクであれば,本書が暴露する,久世番子の画風が確立されるまでの恥さらし的な絵の変遷を笑うことはできないはずだ。「ああ私もそうだったなぁ・・・」とため息交じりにしみじみと昔を思い出すであろう。
そう,本書は久世番子の「まんが道」なのである。いやー,昔はこんなのを描いていたよな~というようなこっぱずかしい絵を次々に見せていくのである。もちろんそんなものを晒す作者自身が一番恥ずかしい思いをしているのであるが,それをうまくユーモアに昇華しているところが久世番子エッセイ漫画のテンションの高さ維持に貢献しているのである。
・・・とまぁ,デビュー直前までのところまでは,お気楽ないつもの久世漫画なのであるが,新書館デビュー時のエピソードは,漫画家志望の方なら一読しておく必要があろう。ネタばれにならない程度にそのエッセンスを言っちゃうと
とうことになる。重要なのは,編集部とコンタクトを取ることなのだ。
個人的には,久世番子はストーリー物よりエッセイ物の方が,現時点では断然面白いと思っている。エッセイ物が最後どこに着地するのか分からないというハラハラドキドキ感を持たせてくれるのに対し,ストーリー物だと,うまくまとめ過ぎているように思えるのだ。たぶん,久世はインテリジェンスあふれる人なので,エッセイ漫画のように「はっちゃける場」がないとかしこまってしまう傾向があるのだろう。悪い意味で,ストーリー物の場合は少女マンガの典型的ストーリーを追いかけてしまい,独自性が発揮されづらいきらいがあるように思える。デビュー時にもたついたのも,そのあたりのパンチ力の無さが原因かも知れない。
・・・以上,漫画家がデビューするまで,あるいはデビュー後にどんな目に合うのかを端的に知ることのできる3作品,資料的価値もあるし,漫画好きならどれか一冊ぐらいは目を通しておきたいものである。そして,ドタバタしまくった昔をシミジミを思い返すまで時が過ぎた時に,「ああワシもそうだったなぁ」と共感しながら読むのがよろしかろう・・・と,四十路を迎えたワシはシミジミしながらそう思っているのである。
3/30(月) 掛川・?
ちょっと寒いな。桜はまだ3分咲きといったところ。この気温のまま推移すれば,満開まではもうちっと時間がかかるかな。
ぷちめれ祭り,予定通り停滞中・・・ささっと書いちゃえばいいのに,適当に流しちゃうにはあまりに重い3冊だったな。まあそのうちぼちぼちと。
日々楽しみにしていたTBSラジオのストリームのポットキャスティング終了(サイトは3月いっぱいでなくなっちゃうそうな)。代わりに新番組が始まり,コラムも続く模様。あー町山さん,しっかり生き残ってやんの。ま,楽しみが残ってワシとしてはありがたし。
へー,QR法の提案者Francis発見・・・って,あんた,川口浩探検隊じゃないんだから。雪男でも見つけたような書きぶりだけど,まだ74歳で健在とはねぇ。ってことは24歳の時に提案・・・すげぇ~。うーん,ワシが24歳の時は研究室でパソコン通信しながら屁ぇこいて寝てましたね。比べる方が間違いか。
本日一番びっくりしたニュース(毎日新聞)。・・・陰謀論をぶつ奴が出そうだけど,仮にそうだとしてもわきが甘いっちゅーかなんちゅーか。東洋大の給料が安いわけでもなかろうに,ベストセラーを書いたばっかしだってのに。かつて手鏡持ってJR車中をうろうろしていた元W大院教授がいたけど,政権批判をしていた学者先生がくだらないことで失脚するってのは,単なる偶然なのか,そーゆー性癖を持った人だからガンガン批判できちゃうのか,果たしてどっち? まあ,愛人を官舎に住まわせていた人については完全に嵌められたんでしょうけどね。人を悪く言うなら身ぎれいにしておかなきゃぁ・・・と自戒。
しかし奥さんと二人で温泉に来てこれじゃぁ・・・ねぇ。奥様の心境やいかに。
昨日の三十路最後の日に論文投稿。あとはreject通知を待って首括って死ぬだけである。・・・嘘です,死にませんから忌憚のない査読をよろしく。って,ホントに忌憚のない意見をされたら人間怒っちゃうものであるけど。あー気にしないでいいですから>編集委員&査読者一同様
さてこの十年間を振り返ってみると,まー仕事してませんね。査読論文7本。馬鹿かおまえはってレベルです。最近調子が出てきましたけど,またこけたりして。まあしかしあと10年は死ぬ気で仕事しなけりゃいけません。なんだったら死んじゃってもいいってぐらいやっておかねばならん。だってさー,この先10年経ったらワシの●●なんて無事に済むとは思えんしな。この少子化の世の中,ワシの●●なんて真っ先に●●されちゃうのがオチ。それならこの先10年でやれるだけのことをやるっきゃないでしょ。幸い●●●は潤沢に貰えているし,活動できる環境があるだけありがたい。この先10年でいなくなっちゃうような●●どもの○○○○なんぞ,聞いてられっかっての。年金貰ってぬくぬくと暮らしてられるなんて夢想できるほど,こちとら平和馬鹿じゃいられねぇんだよっ!・・・はあはあ,つい興奮してしまいましたな。失敬。
そーいや,住宅ローン払い始めて今月でちょうど一年経過したんだった。うう,あと19年,払い続けねばならん。東海地震が来ない・・・いや来てもいいけどワシのマンションを倒壊させないでいただきたい。さーて頑張って2年目の支払いもがんばりましょー・・・あ,次年度から固定資産税の支払いが始まる・・・頭イタ。
つーことでめでたく(?)萌えるひとりもののまま,アラフォー突入でございます。全然賢くなった気がしませんが,神経が図太くなったことだけは間違いない。ますます鼻つまみ者として生きていく所存でございます。
どなたさまも~,すみからすみまで,ずずずぅいいっとぉ,あ,御願い奉りまするぅ~。
3/28(土) 掛川・曇
ふわ~,中途半端な時間に寝てしまったので,こんな時間に目が覚めてしまった。徹夜なんぞやるもんじゃありません。もうしない,ぶー。
あんまりにもVistaのIMEがバカになってしまったので,古いATOK15なんぞを引っ張り出してインスコしたのだが,32bitアプリでしか有効になってくれない。ひえー,秀丸は64bitバージョンなんだよー。今更32bit版に謎戻したくないんだがなぁ。新しいATOKを買って入れるしかないって訳? それもなー,貧窮シフト体制に戻さないといけない状況では避けたい。どーしよーかなー。
いい機会なので,書き逃していたことつらつらとメモっておく。そもそもこのblog,自分用のメモなんだからな。原点回帰は重要である。
SIAM newsの最新号を眺めていたら,GottliebとYoungの訃報記事が載ってた。両人とも昨年12月に亡くなっていたとのこと。Gottliebなんて先日まで知らなかったんだが,タマタマ文献渉猟していたらこの人の論文がまーたくさん見つかること見つかること。時間発展PDEの高次公式に関してはオーソリティだったらしい。ふーん(もう不明を恥じるという羞恥心は失っている。中年だしね)。
ワシにとってはYoungの方が,SOR法の定理なんぞでなじみ深いんだがな。そーいや定常反復法って手がける人,減ったよねぇ。大体,Krylov部分空間法から出発した非定常反復法の研究が進み過ぎちゃって,大規模計算でもこっちの方が高速化しやすいって環境ができちゃったからね。・・・ってワシみたいな門外漢がうっかり書いたら怒られそう。誰かちゃんとした概説書いて下さいな。
このレンタル仮想サーバを置いているのはWebArena SuitePro V2なんだが,来週月曜日から,CentOS 5にも対応するとのこと。現状ではV1がFedora(相当古い奴),V2がCentOS 4。まあ4でも5でも,きちんとセキュリティパッチを出してくれているから,ワシみたいなコバンザメユーザにとってはどっちゃでもいいんだが,本格的にDBMSを使い出したらどーしよーかなーと悩むかも。いや,昔みたいにtar ballからコンパイルしてディレクトリを決めてインストール・・・などとやれないことはないけど,そんな根気はもうない。大体こんだけウィルスがうようよしている状態で,素人仕込みの付け焼刃的対処では危険でしょーがない。さっさと新しい奴に乗り換えていくのが吉,なんだろうけど,めんどくさいんだよね。12月に重い腰上げてよーやっとV1からV2に移行したばっかだしさぁ。半年ほどしてそのうち現実逃避したくなったら(ワシは逃避行動に基づいてしか動かない人間なのである)やるかもねー。
ニトリが値下げで売上伸ばしたとかコンビニ弁当300円台突入とか(朝日新聞),またデフレかよ,という日本経済。まー,若い奴に投資しなくなって年寄りを介護するだけで財政が借金漬けになっちゃってる状況ではしょーがねーよなー,と。ワシも早々に貧窮シフト体制に戻ることにしようっと。
ん~,他にも色々ネタはあったんだけど,spam消したらメモってた自分メールも消えちゃったのでこの辺で。そろそろ寝ます。あー平和な土曜日っていいなー。
起きました。もう桜がボチボチ咲き始めてるってのに寒いなー。いつものように,飯を食いつつ洗濯しつつ,風呂掃除して掃除機かけて便所掃除してスーパーに買い物に行ってポイント5倍ゲットしてクリーニング屋に行って散髪予約して自治会役員引き継ぎして土曜日の予定はすべて終了。はい問題です。この中で「いつものように」ではない行動はどれでしょう?
広島電鉄,全契約社員の正社員化の真相(J-CAST)。城繁幸さんが若者が3年で会社を辞めちゃう理由として,ベテラン社員の高コスト化(ヤな言葉だけどさ)が原因と言っていたが,まさにそれを地でいくような状況だったわけだ。まあ広電に限らず日本全国どこの組織も団塊世代が一番コスト高になっているわけで,成長が見込めない状況ではそのしわ寄せをすべて若い奴が受ける羽目になる,と。従って,ベテランのコストを若いモンに回せば正社員化も可能ってことになる。とはいえ,簡単なことじゃないよな。ワーキングプア問題や派遣切りが騒がれるようになって,その尻馬に乗って給料を減らされたくない正社員層がタッグを組む(ふりをする)・・・と。ああややこしいやや子でございます。
さて,溜まりに溜まった精うぉっほぉおん本を放出すべく,次週はぷちめれ祭りといきますか。まずは若者が実社会に打って出る時の痛みを描いたマンガ3作から~。
3/27(金) 掛川・曇後雨後晴
うっばぁ~・・・まーたやっちまったよ,完徹。といっても9:30に歯医者に行かねばならんかったんで,午前6時過ぎには切り上げて家に戻って3時間ほど寝ましたがね。あ~・・・とにかく疲れた。もーイヤ,論文書き。今月に入って3本目だぜ。しかも査読論文だぜ。ワシがガチャガチャ計算した結果をバリバリ貼り付けただけの(いや,計算そのものがイイって内容だからそれでいいんだけど)論文をこれから皆さん(つーてもせいぜい二人か三人)で読むんですぜ。今月末が投稿締切だから,もうちっと余裕があるんだけど,先月末に思いついて今月上旬に閃いて追加計算して2回しゃべった中身をもう原稿に起こすなんて~,人生2度目だな。一度目は三日で上げた論文を投稿して載せちゃった27歳の冬ぅ~。あーもーあれから12年が過ぎまして,相変わらず能ナシの生活を食っておりますよええ。もーイヤ,さっさと投稿して査読されてrejectくらって首括って死んでしまいたいっ! ・・・あいや,こちとらまじめに書きましたぜ。何せここ一週間ほどずぅうううううう(1KB削除)うううっとうまく筆が(キーボードだがな)進まなかったのにケリをつけて,全面的に構成からやり直したんだから,まー一晩で済んでラッキーってやつですかね。ああこんなこと書いたら載りそなものも載んなくなっちゃうじゃないのよーん・・・って,いったいどーなるんでしょーかーねーだ。わーははははは。いーんだよ書いちまったもんは,もーどーにでもなれーだ。・・・酔ってるな,ワシ。三浦しをんの影響か?

寝ぼけてボシャボシャした頭でサーモンサンドを食いつつ,カーネルおじさんの後ろドタマを眺めていたら,道頓堀川に放り込んだ奴に共感しそうになった。いかんいかん。
あー,現実逃避がてらスケジュールを整理してたら頭痛くなってきた・・・なんでこんなに予定を入れるんだ>ワシ 息つく暇がないじゃんよー。惰弱で自堕落な人間にはこんなモンでも大変なんです,ええ。
あ,風呂湧いた。花王のバブを放り込んだ湯船に浸かって人心地ついたら寝ます。・・・あああ,背中がバリっ…バリだ。いてて・・・。これが三十路最後の肉体でござんす。来週には四十歳! もう日本の老廃物でございますよ,ええ。