予定通り,青春の残滓の残りカスである段ボール7箱を先方へ発送する。先方にはいつ送ったらよいのか,お伺いを立てていたのだが返事がないので問答無用で送りつけることに。まあ良いわ,これで青春の残滓の残りカスの絞り汁までなくなったワイ。とはいえ,青春の(中略)の気配ぐらいは残してあるけどな。
それにしても,さすが段ボール40箱を越える分量のものがなくなると,すっきりするモンである。昔,高橋留美子のエッセイマンガで,腐海と化した仕事場を掃除した後,「おおっ,まっすぐ歩ける!」と感動しているシーンがあったが,ワシも今,同じ感動を味わっているのであった。
その後,アパートの部屋に掃除機をかけたりあれこれ買い物したり銀行へ行ったり灯油を買ってきたりしてドタバタしながら,先日,当研究室のお二人に取ってきて貰った小生御大の映像をDVDへ落としていたりする。これが終わったら新幹線に乗り込むのだ。
・・・が,今日といい昨日といい,運動不足と中性脂肪だだ漏れの中年親父には疲れる作業や行事が満載だったので,もう疲労のピーク。このままホテルにチェックインしてシャワー浴びたら2時間ばかり昼寝する予定。だめだ~,疲れた~,でも行く。
では行ってまいります。
3/19(月) 掛川・?
昨日から作業を開始し,本日午前中に,全ての青春の残滓をクロネコヤマトに託すことができた。しめて段ボール33箱。ゆっくり別れを和む,などという詩的な時間を持つ余裕などなく,ひたすらクソ重い段ボールを,屈強なクロネコ3人に託すだけである。送り先(神保町の某書店)にメールを出して,この件は落着。
が,勢いというものは急には止まらないもんで,この機会にと一気に青春の残滓の残りカスを束ねて括って古紙再生業者の所に持っていった。これで後は寄贈する某雑誌(創刊号から10年分)を明日7箱出せば,きれいさっぱり,ワシの青春は霧消するはずである。・・・単に古雑誌・古本を整理しただけなんだけどな。
午後は,移設したPentium III clusterのcablingをキレイにやり直し,戻ってきた英文校閲の膨大な,文字通りの赤字を眺めつつ,某国際研究集会用のabstractをボチボチ修正。いい加減いやんなった頃,先方へメールしてsubmit処理完了。screeningされるので,落っこちたら行かないだけで済むが,受かっちゃうと補助金申請やら出張届けやら休講・補講の処理やら面倒なことが多数待ち受けているのだなぁ。ま,来週には結果が判明するじゃろ。
夕方からは,関西の大学へ移られる先生の送別会に出席。卒業生も乱入してとても賑やかになる。中締めと共にサヨナラして,ワシはひとり帰宅したのであった。
明日は東京・・・へ行く前にあれこれ処理しなきゃな。重いものを持つやら立ちっぱなしで40本ものtwisted pair cableと格闘するやらで腰がだるい。明日遠出した途端に腰骨が崩壊・・・なんてことにならなきゃいいが。
腰を休ませるために寝ます。
吉本敏洋「グーグル八分とは何か」九天社
[ BK1 | Amazon ] ISBN 4-86167-146-9, \857
アマゾンの書評を見る限り(2007年3月16日(金) 20:29時点),本書に対する評価はまっぷたつに分かれている。支持する向きは本書が「Google八分」なるものを公の場にさらしたことを評価し,そうでない向きは著者の一方的な感想を書き連ねただけの本だと批判する。
ワシの結論は,
ということに尽きる。本書を読むことなしに「Google八分問題」を語ることは,他に類書が少ない今の時点では片手落ちと言わざるを得ない。しかし,本書の言い分だけで「Google八分問題」を結論づけてしまうのもまた片手落ち,なのだ。
著者は,その筋では有名なサイトである「悪徳商法?マニアックス」を主催する管理人beyond氏である。サイトの文面や本書の記述を読む限り,飄々とした2ちゃんねるのひろゆき氏とは正反対の熱血漢とお見受けする。そして,詐欺的な商売をする輩を糾弾する姿勢,度重なる圧力や抗議にもめげず,サイトを維持し続けている姿勢は尊敬に値すると,これはイヤミでもなく褒め殺しでもなく,そう感じる。
そして,本書を書くきっかけとなったGoogle八分は,この著者のサイトの情報に関連して起こったものであった。実際,「悪徳商法?マニアックス」でGoogleると今でも(2006年3月16日(金)現在),削除された情報がある旨が検索結果の下に表示される。どうも,著者のサイトにある某詐欺的商法の情報に対して抗議を受けた事による「Google八分」であるらしい。
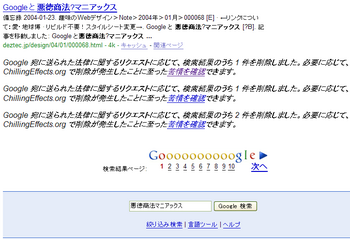
著者はGoogle日本法人への問い合わせを行い,名誉毀損の疑いありと判断されてしまったことを確認したが,どのように該当ページを修正すれば再掲載されるのかを問うてもはかばかしい返事は得られない。佐々木俊尚氏がこの件に関してGoogleにインタビューを行った結果,Googleとしても判断を迷った削除であることは判明したものの,上記のように,今現在もGoogle八分状態は変わっていないのである。
本書にはそれ以外のGoogle八分事件が紹介されているが,中国政府による検閲・朝日新聞による削除養成に関する報告を除けば,大部分のGoogle八分の事例は「悪徳商法?」に関連している事例である。それに気が付いたあたりから,ワシは「これは・・・自分の受けた被害を肯定する資料を積み重ねるだけの本か?」という疑念がついて回り,本書のタイトルから受けていた「Google八分問題を総合的視点から議論する書」というイメージがガラガラと崩れるのを感じたのである。
従って,
という印象を受けた読者が批判的な書評をするのは,至極自然な成り行きなのである。
第4章の「グーグル八分と表現の自由」では,弁護士と図書館協会の方にインタビューを行っているが,ここが本書で最も議論が開かれている部分である。ここがなければワシは本書を「Google八分が理解できる本」として紹介することはなかった。そして,このお二人の話を総合して
・Google八分の問題は,そもそもサーチエンジン市場におけるGoogleの占有率が高いことに起因している
・Googleは情報を削除する基準が曖昧であり,それ故に「表現の自由」を犯す危険が高い
・Google八分そのものが悪いというのではないが,可能な限り,情報は検索・閲覧できるようにしておくべきである
という,かなり多くの賛同を得られるであろう主張を取り出すことができるのである。逆に言えば,この辺を立脚点にして議論を進めていけば,Amazonの書評のように評価が分かれる本にはならなかったのではないか。更に逆に言えば,このような客観的な視点が少ないということが,本書の一番の特徴であり,好き嫌いの別れるところなのであろう。
個人的には,「そもそも何でGoogleだけが情報削除を叩かれるのか?」という疑問が拭えないのだ。それを言い始めると,Yahoo!のカテゴリに自分のサイトが登録されないなんてことは日常茶飯事なのに,何で問題にならないの?,という反論がされるに決まっている。実際,前述の最初の論点に挙げたように,確かにGoogleのシェアは高くなってはいるが,アメリカでも約47%,日本ではトップがYahoo! Japanの約62%で,Googleは本家とあわせても28%に過ぎないという調査結果がある。現状,日本では,ことさらGoogleの「八分」だけを問題視する客観的理由は薄弱なのである。中国の有力サーチエンジン「百度」が近々日本にも上陸するらしいから,今のうちに独占禁止法的な枠組みを議論しておく必要はあろうが,基本的には私企業に対して,商売を度外視して「表現の自由の番人たれ!」とせっつく主張がどこまで強制力を持っていいのか,ワシにはよく分からない。
してみれば,本書はやはり自分のサイトがGoogle八分されたことによる「私憤」をぶちまくための場なのであろう。しかし,全ての「公憤」は,「私憤」を種として発芽し,そこに第三者の共感を得て育っていくものである。本書は,かなりひん曲がっちゃってはいるものの,第4章の助力も得て,私憤が育った苗にはなり得ている。これがそのうち巨大な,それこそクローバルスタンダードとしての公憤の大木に育っていくのか,それとも著者個人とその周辺だけの私憤として収束していくのかは,ワシにはこれもよく分からない。
しかし,今のサーチエンジンの周辺事情に興味のある向きは,必ず読んで,手元に置いておく必要があるだろう。そして,年月が経過した後,再び本書を紐解いて,著者の主張がどのような結果に結実しているかを確認すべきである。世の中には時間でしか解決できない物事が山ほどあるが,たぶん,著者が投げかけたのも,その中の一つなのである。
3/16(金) 掛川・?
ふー,書類書きに研究がサンドイッチされてきた一週間がやっと終わった。本日ようやく学内研究費の報告書を上げて,某国際研究会に投稿するabstractの下書きを書き上げたのである。菱沼さん(@動物のお医者さん)のように「えいご~,やだ~」とかいいながら,助動詞と副詞と仮定法を使いこなせない中学生並の英文をA4用紙1ページ分も書いたのである。3時間ぐらいだったけどな。後は校閲が帰ってくるのを待つばかり,と。月曜日に届いたら即座に投稿である。ところで”screen”ってどのぐらいのレベルの査読なんだろ? ちらっと見るだけ?
そーいや,SIAM reviewに面白い記事があった。日本語だと「ドミノ倒しの波」って感じかな? エネルギー保存則と数列,微積分だけで数学モデルを作ってあるから,エリート高校の理数系生徒なら理解できるんじゃないかしらん。
日本の応用数理も,エライ方々の思い出話とか自分の研究の自慢話ばっかりじゃなくって,こういう記事をどしどし載せればいいのにな。折角,岩波から発行して貰っているってのに,仲間内の同人誌みたいな記事ばっかりではなぁ。情報処理を見習って,リニューアルしないのかしらん? 数理科学と数学セミナーよりコンピュータ&工学寄りの記事を増やせば,それなりに会員以外の読者も付くと思うんだが。数学文化だってもう7号も続いているんだからね。
風呂沸いたら,入ってから寝ます。
3/14(水) 掛川・?
桜開花予想は間違いでした,という記事。気象庁の発表によれば
「さくらの開花予想の計算に用いるプログラムに一部不具合があったため、7日に発表した第1回さくらの開花予想を下記のとおり訂正します。
これらの4地点では、用いた気温データに一部誤りがあり、予想日が正しく計算できませんでした。」
ということだが,気温データの不具合が原因なのか,プログラムの不具合が原因なのか,前者の不具合を後者の不具合と言い換えているのか,訳がワカラン。「初期誤差が間違っていると,以降の計算結果も狂ってくる」という実例として教材に使おうかと思っていたのだが,うーん,この発表文だけではそーゆーミスなのかどうか判断しかねる。よってpending。気象庁に電話で聞けばいいんだろうが,そこまでする必要もないし,そんな下らない桜桃・・・じゃない応答で貴重な頭脳資源を無駄にさせてもいかんしな。
・・・と続報。NHKニュースによれば,
「気象庁によりますと、システムに気温のデータを自動で取り込む際、トラブルが起きて誤ったデータが書き込まれたということですが、エラーの表示が出る仕組みはありませんでした。」
ということで,入力データを読み取るプログラムが何らかの理由で誤作動し,一部の地域における昨年12月下旬の気温が正確なものではなくなってしまったことによるものらしい。だから,
・入力データを読み取れなかったも関わらずエラーを出さない
・読み取れなかったデータを自動的にいい加減なものに差し替えてしまう
という「プログラムの不具合」によって,データが狂ってしまった,ということなんだな。納得。
そんな予想より,この寒さ,いつまで続くんじゃい。春の直前で,冬将軍が残業をしているという感じ。マッタ・カムイがルプシゥル・カムイ(詳細はこれを読みたまい)をさぞやこき使っているのであろう。早く仕事を終わらせて欲しいモンである。
「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」が設置されたとのこと。さて,冷静な議論がここでもちゃんとなされるかどうか,チェックすべきだな。委員のメンツを見ても,三田以外の立場がよーわからん。議事録が出ればおおよそ分かるんだろうが。
| 延長への立場 | 氏名(役職) |
|---|---|
| ? | 上野達弘(立教大学・助教授) |
| ? | 大渕哲也(東京大学・教授) |
| 賛成? | 久保田裕(コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)・専務理事) |
| 賛成? | 里中満智子(漫画家) |
| ? | 津田大介(IT・音楽ジャーナリスト) |
| ? | 佐々木隆一(ネットワーク音楽著作権連絡協議会・代表世話人) |
| ? | 都倉俊一(作曲家) |
| 賛成 | 三田誠広(作家) |
この表は次第が明らかになった時にupdateしたい。
書類書きに戻ります。
