Rainierスタイルを使って再構築し,曲がりなりにもマルチデバイス対応にしてみました。PCから読むと字が小さいなぁと感じますが,スマホから見るといい感じです。ぼちぼち手直ししていきます。
久世番子「パレス・メイヂ 1巻」白泉社
[ Amazon ] ISBN 978-4-592-19404-0, \429
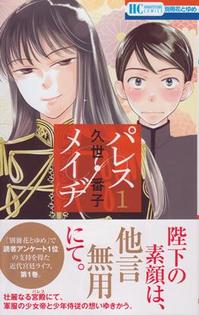
エッセイ漫画の名手,久世番子が少女漫画「コミックス」を出すとは,時代も変わったものである。別冊花とゆめで連載が始まったと知った時には意外だなぁと少し驚いたのだが,今回単行本として纏まったものを読むと,不思議なほど違和感がない。勿論,ワシがスレッカラシの中年漫画読みであることの影響も大きいのだろうが,本作は至極まっとうな「純粋少女漫画」であると感じたのである。それはいわゆる「王宮もの」(今ワシが勝手に作ったジャンルだ)に分類される「(初期の)パタリロ」や「大奥」が純然たる少女漫画であるのと同様,本作は間違いなく少女の夢・ファンタジーを描く作品となっているからである。
6/23(日) 駿府・曇
どんよりした梅雨らしき一日。神さんは出かけているのでワシは一人留守番している。湿度が高いので蒸すことは蒸すが,気温は27度程度と,不快極まりなしというほどではない。このまま冷夏になってくれると日本の電力事情も助かるのだが,コメが取れなくなるのも困る・・・という文句は以前にも何度か書いていたな。考えることが代わり映えしないというのは廊下の証拠であろう。アルツハイマーが進行しているとも言える。困ったものである。
6/20(木) 駿府・雨
梅雨も末期になりつつあるところに,台風4号が九州に上陸しそうだという。勢力は弱いが,梅雨前線を刺激する熱帯の湿気を運んでくるので,雨は激しくなりそうだ。土曜日には職場で説明会があるのだが,影響がないといいな。その頃には太平洋に抜けているという予報を信じるほかない。
さて,出張ラッシュ(という程でもないか)が終わり,査読論文(一応ね)2本の校正が終わって一息ついたので,今後の予定を考えてみる。大体,ワシはほぼ一人で研究活動をやっているので,あんましアチコチ出かけるのは宜しくない。そーでなくても職場関係のお出かけも多い昨今,あんまし業績にならない講演をしまくるのは自重せねばならぬ。
とゆーことで,今後は
- 5~6月 数値解析シンポジウム
- 9月 日本応用数理学会年会
- 7~9月 海外の研究集会(あれば)
ぐらいにしておこう。私情協の講演会もここんとこノコノコ出かけていったが,本年度からは職場が脱退しちゃった関係上,出られない(のかどーかは定かでないが,出づらいのは確か)。まぁ教育絡みのものは紀要かどこぞの三流雑誌にでも乗っけてよしとしようかしらん。
ま,イレギュラーで色々他の研究集会に出なければならないことはあろうけど,こっちからは積極的に出ないことにする。その分,三流紙でもいいから査読論文書きに勤しむことにしよう。でないと,イチャモンつけても引用すべきものがないってみっともないことになるからなぁ。人に絡むんなら査読論文にしておけっての,全く。時期を逸してしまうと,今更論文にした所で「時代遅れ」の一言でrejectになっちゃうからなぁ。せいぜいカキカキしよう。
最近髪の毛が減ってきた。カミさんは肥えてきたし,夫婦ともども初々しさが消えて(最初からあったかどうかは疑問だが),図々しい中年に成り下がったのである。
つーことで,頭がバーコードになる前に短くしたいんだけど,ひげを伸ばしているとバランスが悪いとかで,床屋ではあまり刈りこんでくれないのだ。ワシもそろそろヒゲを落としたいのだが,落とすべきタイミングがなくて困っている。まぁそれもこれも××が××であるせいなんだけど,ひとえに自分の実力の無さに起因するものなので,仕方ないのであった。
つーことで,なるべく引きこもって論文読みとプログラム書きに勤しむことにしたい。ま,出かけたくなったらカミさん孝行も兼ねて一緒にどっかに行くことにしよう(と書いておかないと夫婦不和の元)。
寝ます。
・・・と思ったら,Twitterへの投稿に失敗している。ここんとこどーもアップされないことが多いな,とゆーことで,PostTweetを1.1.3にアップデートして,parent.pm(入ってなかった)を突っ込んだら無事アップできた。
今度こそ寝ます。
私屋カヲル「こどものじかん 13巻(最終巻)」「こどものじかん ほうかご」双葉社
「こどものじかん 13巻」[ Amazon ] ISBN 978-4-575-84246-3, \600
「こどものじかん ほうかご」[ Amazon ] ISBN 978-4-575-84247-0, \600
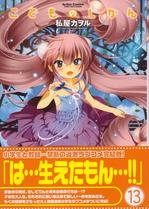
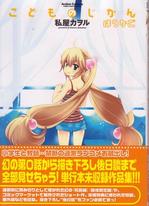
私屋カヲルについては一度は言及しておく必要があると思っていたのであるが,ついぞ述べる機会を逸していた。それは面白い近作を見逃し続けていた(あまり面白くない凡作は読んだ)という理由による。ここはやはりここ一番のヒット作である「こどものじかん」を読むしかないな,と思っていたところで最新刊・最終巻が発売されたので,一気に読んだのである。で・・・さすがだなぁ,と思うと同時に,これをやり玉に挙げて児童ポルノ法案に漫画・アニメ表現規制も盛り込もうという向きは少し考え直した方がいいのではないかと助言したくなったのである。
ということを書くと,お前は表現規制派なのかと言われそうだが,個人的には逆であるつもりだ。ただ両者の間のブリッジはもう少し広くして,規制したい方々の「嫌悪感」と,規制したことによる弊害,いやそれ以前に,規制することの「非合理性」についてガチで議論を深めてほしいと願っている。ま,ガチガチの規制派・規制反対派の方々にとってはどっちつかずのコウモリ野郎ということになるのだろうが,それはそれで正しい認識である。ワシはコティさんよろしく,世間の風向きというものにも一定の合理性は認める人間なので,どっちに転ぶのか,その原因たる社会的背景の方を注視していたいのである。
で,私屋カヲルである。デビュー時にはダッサイ絵だなぁと一顧だにしなかった漫画家が,気が付くと萌え萌えの画風となり,あれよあれよという間に「こどものじかん」で大ヒットを飛ばすまでに成長するなどとは露程も思わなかった。ワシは全く見る目のない一読者であるなぁと今大いに反省しているのである。
いつぞや,Twitter上では結城焔と私屋カヲルとのバトル(という程でもなかったが)が話題になった。第三者が読めば,私屋の本作が「あざといエロ釣り」であり,それ故に結城作品も載っている掲載雑誌が一般書店に流れづらく,結果として売れていない,という批判が発端となったバトルである。これをつらつら読むと,結城の最初の発言は相当言いがかりである。では振り返って私屋カヲルの本作が「あざといエロ釣り」ではないのかと言われれば,大方の人々は肯定せざるを得ないのではないかと思うのである。断言すると,ストーリーではなく絵面の表面だけ見れば,「あざといエロ釣り」という表現は当たっているのである。そしてここからが重要な論点になるのだが,では「あざといエロ釣り」というものが誰にでも描けるのか,そして大多数が認める「あざといエロ」というものに対して同じく大多数が納得する合理性を伴った規制というものが可能なのかどうか,折角本作という成人漫画規制の枠外の「具体例」があるのだから,大いに議論してほしいと思っているのである。そしてその議論の結果,ジャパンクールにおける「あざといエロ」の重要度が認識されるのではないかとワシは考えているのである。
本作の主人公・九重は,担任の教師・青木に恋する小6生だ。それだけならいいのだが,その好意の寄せ方は相当エロく,直接的なものである。この辺りが一部のお固い向きから憤激を買うんだろうが,そこを私屋は「都条例をクリア」する表現で,最大限の効果を得るべく描いているのである。この辺の見せるテクニックは非常に巧みで,萌えの極地のような絵柄と名人芸レベルに達した構成で読者を引きつける。「あざとい」と形容するのがピッタリだ。そしてこのあざとさが,都条例をクリアしているにも関わらず,憤激を買う原因になっている。これに規制の網をかぶせようとすると,もっとぼんやりとしたシチュエーションを規定せねばならず,現在問題なしと見られている他作品への影響が大きすぎるということになる。そこがまた規制派の方々のイライラを募らせている原因なのかなぁと想像するのである。
本作がエロいというのは正しいが,それがエロいのは基準をクリアした表現の巧みさに起因するものであって,私屋カヲルと同レベルの表現力がなければ成し得ない。それ故に本作を規制のターゲットとするのは問題が多すぎる,というのがワシの意見である。大体,ストーリー的には面白く真面目な性教育読本とも解釈できる内容になっているんだし。
・・・しかし規制派の意見にはあまり合理性がないとはいえ,政治的動向によっては「ぼんやりしたシチュエーション」での規制がかかり,最低でも現状以上に厳しいゾーニングを余儀なくされるかもしれない。そうなれば本作も同時発売された「こどものじかん ほうかご」も成人向け作品にカテゴライズされてしまう可能性がある。
だが,私屋カヲルの成り上がりっぷりを見る限り,どんな規制がかかろうと,そういうものはラクラクと踏み越えてしまうだろう。エロ抜きであっても面白いストーリー展開という武器を,私屋はすっかり自家薬籠中のものとしているのだ。規制を逆手に取った漫画作品を生み出して読者の支持を得ること間違いないのである。