[ Amazon ] ISBN 978-4-09-179036-1, \1000
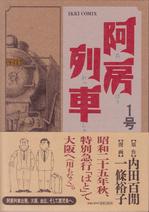
内田百閒のこましゃくれたエッセイ口調と,一條裕子のひねたユーモアが醸し出す独特の雰囲気がこれほどマッチするとは思わなかった。百閒と一條に両者に共通するのは「上品さ」であるけれど,本書を読むと,一條裕子のオリジナル作品と見まごうばかりの自然なコマ運びで,下手くそな原作ものにありがちの引っかかりが全くない。それでいて,百閒エッセイの全体の方向性は踏襲しているように思えるのである。これは両者のセンスだけでなく,やはり根底に流れる「上品さ」,つまりは百閒と一條が共に持つ,上質なインテリジェンスと心優しさがあったればこそなのであろう。一條に百閒作品を描かせるというアイディアをもたらした編集者(かどうかは定かでないけど)の慧眼に,ワシは唸ってしまったのである。
一條裕子の作品はこの上なく上品だ。「ギャグマンガ」とは言いたくない。キザな言い方だが,「エスプリの効いたユーモア漫画」なのである。本人の意識はどうか知らないが,頭で構築したギャグではなく,本人の体質からにじみ出たユーモア感覚で作品を描いているように思えるのだ。頭を使っているのは作品の構成であって,ページ数にかっちり納める無駄のないコマ運びは,とり・みきに並ぶ「理数系」作家と呼ぶべき見事さである。両人がさすらいの編集人・吉田保(フリースタイル)のお気に入りリストに入れられ,雑誌(実際はムック扱いだが)で競演しているのも必然的な成り行きだったのだろう。
一條作品のもう一つの特徴は,余白と白さを生かしたセンスあふれる画面構成であろう。書き込まれた絵やアップは少なく,リズムと空白で読ませる。遠景から描かれた極めて客観的な視点の絵は,デッサンがきっちりした「うまい絵」に分類されるものであるが,空白とのバランスも見事で,こんだけ高度なことをやらかした漫画がしょうもない(褒めてます)ことを延々と語っているのだから,うーん,追随するのは難しい作家であることは間違いない。
内田百閒の作品を読んだことはないので,ワシが抱くイメージは,黒澤明の映画「まあだだよ」で得たものしかない。まあそれほど間違いはないだろうと勝手に結論づけるとして,その印象を一言で言うと,「心底善人のくせに,それをストレートに表現することに含羞を覚えるインテリ」というものである。本書巻末には「特別阿房列車」の冒頭部分が抜粋されているが,それだけ読んでいても,論理的な文章でありながら,感情の発露がありつつ,訳の分からん理屈でたたみ込むという芸当が見て取れる。師匠・漱石譲りのところが大きいように思えるが,ワシは文芸評論家ではないのでその辺の推理は得意な人にお任せするとして,この抜粋部分と一條のコミカライズ部分とを比較すると,一條の構成力の見事さが読み取れるのだ。それを紹介しよう。
文章,特にエッセイは,全体の方向性さえ示されれば(場合によっては「方向なんぞ定めない」という方向性(?)でも可),枝葉部分はどうとでもできる。デコラティブにもできるし,極力シンプルにすることもできるし,全体の方向性に棹さしてもいい。百閒の文章は感情の発露で飾り付けを行っているように思え,そこの部分が上質なユーモアを醸し出す手助けをしている。
しかし,一條は枝葉部分をすべてそぎ落としているのである。たとえば「阿房列車」の意味を述べた文章,戦後になって一等車が復活したことを述べた段落,大阪駅内に無駄遣いをしそうな店が連なっていることを述べた文章をカットし,大阪行きの列車を決めるまでのグタグタした思考行きつ戻りつする様子に絞って描写を行っている。全体の方向性とは関係のない飾り付けをスパスパと枝払いし,漫画としての分かりやすさを重視した構成にしているのである。それで十分,というか,そうすることで,一條裕子の持つユーモアセンスが生かせているのだから,名人芸としか言いようがない。
本書で指摘しておかねばいけないのは,もう一つある。それは一條裕子のチャレンジだ。見開きにドンと据えられた「見せ場」。ごった返す東京駅のホーム,驟雨に煙る富士岡駅の風景,友釣りで引き上げられた鮎が空中を舞う夏の球磨川・・・,一條裕子の卓抜な画力と画面構成力が光るシンプルだが感動的な絵が,読者の目を釘付けにする見せ場を作っている。今までのユーモアものにはなかった,ベタだがワシら大衆に分かりやく感動できる見開きページは,間違いなく,一條のチャレンジ精神が生み出したものだ。紀行エッセイを紀行マンガに変換する「意味」を,一條はこの見開きを描くことで見いだしたのであろう。
ワシは鉄っちゃんではないので,本書に掲載されている,百閒乗車の列車編成表は全く分からないのだが,見る人が見れば,凝った本だなぁと感動するものなのであろう。編成表といい,箱入りの古風な装丁といい,チャレンジングな見開きページといい,分りやすく面白いマンガ構成といい,本書全体が懲りまくっているのは間違いない。掲載誌はメジャー版元・小学館にはあるまじき低部数なんだそうであるが,個性が際立つ作家を集めた雑誌をまとめて読むのは難しく,むしろこうして単行本という形でばら売りしてもらった方が,コアなマンガ読みでない読者にはありがたい。実際,本書は普通のマンガ読みな人にも楽しんでもらえる,「普通に面白い」ように一條が百閒を「翻訳」してくれているのだから,ちょっと高めの定価ではあるけれど,それだけの価値があると断言できる。マニアックなのは本の作りだけであって,内容は決してそうでないだけに,もうちっと一條裕子をたくさんの方々の手にとってもらいやすいよう,凝らない体裁のコスト安な本ににしても良かったのではないか,と,その点だけはちょっと残念に思っているのである。
生涯家計簿をつけてみた
20年支払いの住宅ローンを組んでから早一年,自分の今までとこれからの収入&支出を整理すべく,Excelで生涯家計簿をつけてみた。40年生きてきた経験に基づき,これから毎月あるはずの収入&支出や,一時的にドカンとかかってくる大規模支出(>10万)を皮算用的に組み入れて,ワシが60歳の定年(65歳の間違いじゃないよ)を迎えるまでどの程度の資産形成ができるかを勘定してみたのである。
結果。
ふー,何とか年金が出るまでの5年間は食べていける程度にはなることが判明した。もちろん,今のまま健康で持病もなく親もつつがなく別居して生活し,ワシは永遠に一人で生活するという前提に立てば,の話。どーせこのとーりなんていくはずがないので,まあ思いっきり楽天的な仮定に立脚していればとりあえず人間らしい(ひとりもの生活が人間らしいと言えるならば,だが)文化的な生活が送れるよーだ,というだけである。
積算根拠となる月々の細かい支出明細をまとめてみたら,まぁこれが質素なこと。もちろん「貧窮シフト」と銘打って食費を絞り込んだりしたから,そのせいでもあるんだけど,ホント,ワシの生活ってば,手取り年収240万で十分やっていける程度のものだったのである。これに住宅ローンその他の遊興費が加わっても+xx万程度。してみれば,ワシの生活水準って,初任給以来ほとんど上がっていないのである。修士出てから入社(入団)したので,当時の手取り分は大体20万円ほどだったのだ。いやぁ~,社会人の生活態度って,ホント,初任給で決まるんじゃないかというぐらい変化なし。困ったモンだっつーか,四十路になっても成長しない奴と言うべきか。もうちっと風俗とか酒とか博打とかにのめり込んでも良かったものを,ぜんっぜん興味が沸かないまま,十数年を過ごしてしまったのである。
唯一,読書習慣だけは変わらず,以前よりずっと高価な単行本や専門書(洋書ばっか)をバンバン買うようになっている。よって確実に増えたのは本代なのだが,その分,人付き合いを全くしなくなってしまったので,酒代は全然かからない。もともと家で飲む習慣がないし,ワシの一家は正統なモンゴリアンの血を受け継いでいる下戸なので,一人ではアルコールを摂取しようという気が全く起こらないのである。だもんで,飲酒はゼミコンパの年3回程度+α。酒飲まないと,ホント,金かかりません。つーことで,ワシは飲む分を読む方に回すようになった,誠に辛気くさい中年親父なのであります。
おまけにネットの接続料の安くなったこと。最近はボチボチ高止まりしそうだけど,それでも世界水準からみて,日本の光ファイバー接続料金は段違いに安い。すべてはテカリハゲアントレプレナー親父の無茶苦茶な営業努力のせいであろうが,読書中毒のヒッキー中年男にとって,無尽蔵とも言える活字量がなだれ込んでくるネットの情報を読むだけで十分至福の時間が過ごせるというものである。これでますますリアルなおつきあいが絶えてしまった。いいんだか悪いんだか・・・っていいわなきゃないよな。ま,それでも月々7000円の元は取っているものと確信しております。これなかったら,もう少し人間らしい生活を送れたろうに(言い訳)。
ということで,つらつらと計算しながら過ごした日曜であった。どーも,こういう計算でもしていないと生きるモチベーションが沸きづらいのがひとりものの厄介なところ。ご家庭のおとーさんにでもなっていれば,自分よか子供や奥さんや奥さんのご両親やらのことも心配せねばならず,とてものことこんなノンビリ計算なんぞしていられず,ガシガシと仕事に邁進されるんでしょうけどねぇ。
自分の手持ち財産だけが頼りとなり,一人通帳を抱え込む独居老人・・・ってのは「寂しい老人」のプロトタイプなんだろうが,ワシとしては,抱え込むだけの通帳を作っていきたいというのが,偽らざる心境なのでございます。寂しがるのはその後でイーじゃん。
衣食足りて 寂しさを知る老人となりたい 今日この頃なのでございます。つーか,これって,今の日の本に住む若い奴,共通の念願なんだよなぁ。せいぜい税金支払える奴は支払って,公共の福祉を支えてきたいものである。
牧野貴樹「π 円周率1,000,000桁表」暗黒通信団
[ Amazon ] ISBN 978-4-87310-002-9, \341
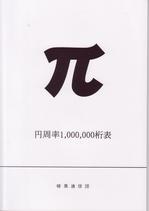
多倍長計算に手を染めるようになって,10年経つ。一応査読論文も何本か書いてきたから,ボチボチこの分野に関しては言いたいことを言っても罰は当たらんだろうと思うので,ここらで本音をぶちまけておく。
そもそもワシがGMPやMPFRを使ってライブラリを作ってシコシコ計算してきたのは,たーくさんの数字の羅列を眺めるのが好きだからである。まあ元は誤差誤差した計算を解析するのに飽きて,「だーっと桁をたくさん取って計算すりゃいいんだろ!」とヤケクソのように始めたのがきっかけなのであるが,元々数字フェチの気があったのが運の尽きで,以来,100桁,1000桁の数値データをみなければ満足しない体となり,中毒の様相を呈するようになってしまったのである。もちろん,「たくさん数字が並んでると楽しいでしょ?」では論文にならんので,それなりに実用的な意義のある悪条件問題やら多倍長計算の分散・並列化やらを対象としてもっともらしい理屈をつけてまとめるのであるけど,根源的には「数字の羅列が好き」という以上の動機が見あたらないのだ。
だから,本書のような,ホントにπを百万桁並べただけの潔い本は,もうそれこそベッドに引きずり込んでホンホン(by 唐沢なをき)したいぐらい大好きなのである。もちろん数字の一個一個を丹念に読むなんてことはしない。適当にぱらぱらめくって一ページあたり一万桁並んでいる数字を眺めて悦に入るのである。これで一時間はイケる。
・・・ええ,変態だよヘンタイッ! いいじゃないか,誰にも迷惑かけてないんだからさ,ほっといてちょうだい!,とワシは声を大にして言いたいのである。
変態の告白だけで終わっちゃうと,ワシの学者人生も共に終わっちゃいそうだから,もう少し真面目な話をしておく。
そもそもπを含む実数は,無限桁小数でなければ正確な表現ができないようになっている。有限桁小数(=有理数)による数列の極限値は有限桁に収まらないのが普通なので,極限計算を土台とする微分積分を行うためにはどうしても無限桁小数を扱わねばならない。とはいえ,それは理論上のことであって,実際に扱う数値が無限桁ではどんなスーパーコンピュータを持ってしてもπの値の出力だって終了しやしない。だから実用的には適当な桁数で打ち切って(丸めと呼ぶ),単精度(約7桁),倍精度(約15強桁)とかでコンピュータでは計算することになっている。ここに理論との齟齬(=誤差)が生まれる。誤差をどーにかする方法は難しいのと簡単なのがあるが,とりあえず桁数をどんどん増やして計算しておけばそんなにおかしな結果にはならないんじゃないの~,とバカの一つ覚え的解決をするのが多倍長計算という奴である。頭の良い方策は,誤差の影響が少ない計算方法を問題ごとに考えるという奴であるが,これは数学的かつ数値計算的素養が必須なので,誰にでもできるというものではないし,やっぱり有限桁計算である以上,限界はあるのだ。
とゆーことで多倍長計算をしておけば誤差の影響は減るのでめでたしめでたし・・・とはいかない。すぐに分かることだが,10桁の小数同士のかけ算をやるのと,100桁小数同士のかけ算をやるのとでは計算の手間(=計算量)がモンのすごく違ってくる。つまり,桁数が大きくなると計算量が増え,それに比例して計算時間も増えてしまう。なるべく大きな桁数でも計算時間を余り増やさないようなアルゴリズムを考えると・・・やっぱりここでも頭を使う必要が出てしまうのだ。
ワシはバカなので,頭を使うより定評のある多倍長計算ライブラリ(GMP,MPFRはこれの一種)を使うだけという安易な方法を取ったけど,ここんとこを自力で解決しようとすると,アルゴリズムとコンピュータの内部構造に通じる必要が出て,相当の馬力を必要とする仕事になる。手計算をそのままなぞる計算方法では桁が増えると非効率になるので,計算量を減らす複雑なアルゴリズム(たとえばGMPのマニュアル参照)を使い,しかもそれを高速に実行できるようチューニングを行うという作業になるからだ。
円周率πの計算も事情は一緒で,桁数を長くすればするほど計算時間は格段に増える。ちなみに世界記録を作った研究室出身の方は,計算時間を極力抑えるアルゴリズムを極めて,その方面では世界的に有名なライブラリを作り上げている。純粋数学の方々にはπの計算なんて,と軽視する雰囲気もあったようだが,コンピュータ屋にとってはかなりいい仕事(の目標)を与えたと言えるのである。もっともその後,BBP公式なんて理論的にもおもしろい結果が出たりするから,みんなが面白がって群がっている研究テーマからはいろんなものが発生するものだと感心する。
最近はパソコンも高速になったので,本書に載っている百万桁計算はかなり軽い計算になっている。試しにSuper πというベンチマークソフトを使ってみたら,Athlon64 X2 3800+マシンで53秒(104万桁)だった。最新のQuad core CPUならこの1/4,さらにSIMD命令を使ったりすればもっと高速化されるので,本気になってあれこれ高速化のためのチューニングをやれば,10秒を軽く切るんじゃないのかな。
本書に掲載されているπの百万桁は自作のプログラムで計算したとのことであるが,だからまあ多大な計算時間を要するというものではないし,計算の仕方はそれこそググってもらえば山ほど出てくるから,真にオリジナリティのある仕事とは言えない。著者としてはプログラムを作る方もさることながら,数字をかっちり並べてTeXで製版する方もおもしろかったのかなぁと想像する。本書は暗黒通信団というサークルが発行した同人誌ではあるが,ちゃんとISBNコードも取得して一般書店に流通させたりしているあたり,しかも314円という,あらかじめ決められていたようなやっすい頒価をつけちゃうあたり,ワシみたいな数字フェチを喜ばせるというやり方で日本文化に貢献しようというあたりの,心意気は見事である。つーか,心意気しか褒めようのない本を出したこと(eの本もあるらしいがワシは未見)が素晴らしい,とワシは,これはイヤミではなく,素直に感心しているのである。
4/1(水) 掛川・?
ふ~,本日はCentOS 5.3 x86_64インストールデイ。CentOS5.2マシンを片っ端からアップデートしまくったが,あの訳の分からんキモい壁紙はFedora起源か? それ以外はまあそこそこ。懸案だったCore i7マシンのハングアップが解消されたかどうかはもうちっと様子を見ることに。ズボラして5.2からアップデートかけたらフリーズしましたからね。BIOS設定をデフォルトに戻してHTもonにして,クリーンインストールしなおして起動してあるが,さてどうなりますから。二三日様子を見ないとまだ何とも言えないな。
Google面接blog記事の翻訳。うーむ,すげぇ手間かけてんな・・・。ワシなんかはたぶん1次試験でアウトであろう。
本日一番感心した記事(デイリーポータルZ)。そうかウズラの卵でピータンが簡単にできるのか! ワシんちは植木がないので,ある方は試して作って自分で食ってみて下さい。ワシはいらん。
猫Watch創刊。うーむ,ホントにやればいいのに・・・。株価,元に戻んないんですけど,猫でも犬でもイタチでもでもいいからなんとかせーよ>インプレスHD首脳陣
どーしよーもなくVistaの仮名漢字変換がバカになっちゃったので,とうとうATOK2009をインストール。おお確かに使いやすいし,変換もそこそこ精度が良い。つーか,元に戻っただけとも言えるが。x86_64環境でも使えるのが嬉しい。しばらくはこれで行こう・・・って,もうIMEの候補って,M$かATOKしかないんだよな。ITという言葉が使い古されてしまった昨今を象徴するような話ではある。
何かいても本日は嘘臭くなっちゃうのでこの辺で。
3/31(火) 掛川・曇
肌寒い日が続くな~。今週末からは平年並みの気温に戻るようだが。花冷えって奴か?
首を長ーくして待っていたCentOS 5.3,やっとMirrorへの配布が始まった模様。正式アナウンスはもうすぐのようだ。ちらっと日本のミラーサイトを覗いたら,CD imageは届いていたりする。はよDVDも欲しいものである。いまさらCD7枚も使いたくないよなー。
ともかく入手できたらCore i7マシンにとっとと突っ込んでインストールしなきゃぁ。無駄な電気食いマシンをこれ以上放置しておくわけにはいかんからな。
ちょうど,XenServerがノード数無制限のまま無償化というニュースが入った。一度チャラにしてクラスタを組みなおす予定なので,ちょっと遊んでみようかという気分にはなる。解説ビデオを見る限りはかなり便利そう。問題は共有データストレージが必要になることで,iSCSIを推奨とのことだが,安いTerastation iSCSIでも10万以上はする。そんな予算はない。Linux boxをiSCSI targetにできるようなので,ストレージマシンを作るか,NFS serverも使えるみたいなので,運用的に問題がなければそっちを使うという手もあるか。・・・しかし遊んでいる暇はなさそうなところが困ったことだ。8月後半までは無理かなぁ。
「習熟度別授業、効果出ない例も」(朝日新聞)。
いわゆる「できが良くない生徒」をどうやったら引き上げることができるか。もちろん「できる」という前提で言っているのだろうが,うーん,無理なケースも多いんじゃないのか。ワシもできない部類の人間だったから言っておくけど,同じ学習内容でも習得に必要な時間というのは個人差がでかいのだ。
むしろ,できない子は小中高の早いうちに留年させるという仕組みも必要かと思う。大学に入ってから留年したんじゃ,学費がかかって仕方がない。習得速度に差があるのは当たり前のことなので,内容が高度になる前に留年してもう一度同じ内容を学習させるってのは悪い方策ではないと思うんだがな。
問題は留年した場合の経済的・精神的ケアか。留年制度が定着して,一教室に二けた程度のダブり生徒がいるとなれば,おのずと留年のショックは和らぐ・・・ってのは楽天的すぎるかなぁ。しかし日本の大学進学率がこんだけ高くなると,まずベース部分の学習をきっちりやっておかないと学士号の質の担保なんぞ不可能だ。小中高で留年あるいは復習学習を定着させるか,大学で小中高で足りなかった部分を補わせるのか,具体的な方策を作り上げていかなきゃならんよなぁ。
さて明日からは新年度始まり。予算不足でぶっ壊れていたプリンタだのマシンだのを修理せねばならず,朝一番で予算申請しておかねば~。
つーことで一仕事したら寝ます。