[ Amazon ] ISBN 4-16-748315-7, \590「決定版 日本のいちばん長い日」
[ Amazon ] ISBN 978-4-480-42443-3, \780
[ Amazon ] DVD 岡本喜八監督作品「日本のいちばん長い日」(1967年)
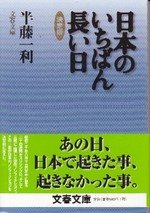
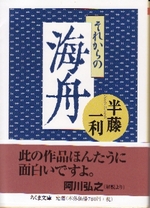
敗戦記念日につき,敗戦処理をトピックとして取り上げることにしたい。
・・・と方針は決まったが,さていざ取り上げるとなると,結構難しい。今更,ウヨクやサヨクの意見開陳本を取り上げるのは退屈だし(ワシはどちらにもすっかり飽きてしまった),かといって,まじめくさった評論・学術書を読むのは,加藤典洋の「敗戦後論」を挫折して以来,なるべく忌避するようにしている。さりとて,右だの左だののプロパガンダっぽいものに引っかかるのはイヤだなぁ・・・と言う時に重宝するのが信用できるジャーナリストによるドキュメンタリーである。ワシのようなめんどくさがりの読者の代わりに綿密な資料の解析と取材を敢行し,事実をキッチリ押さえ,その上でエンターテインメント的なストーリーテリングを行ってくれる,そーゆー人の書いたものなら万人にお勧めできるというモノである。
とゆーことで,それが出来る数少ないジャーナリスト,半藤一利の著作をもって,日本の反省の夏の一日を振り返ってみたい。
最初の出会いは昨年日記にも書いた通り,半藤の本を原作とした映画だったのである。NHK BSの敗戦記念日特集の一環として,この日本映画の大作「日本のいちばん長い日」が放映されたのを見て大興奮したのであった。
何が興奮したかって,まず出演俳優陣の豪華さだ。制作が1967年というから,40年以上前のものだが,制作の2年後に生まれたワシですら名前がスラスラと出てくる俳優ばかり登場する。鈴木貫太郎役・笠智衆や,阿南惟幾役・三船敏郎はいうに及ばず,ナレーターの仲代達矢,佐々木大尉役・天本英世,以下役名は略すが,加東大介,加山雄三,黒沢年男,志村喬,小林圭樹,加藤武,北村和夫・・・,いやー,凄いですね。しかも今と違って,アイドル的な客引きメンバーは加山を除いてゼロ,演技力で圧しまくる実力派ばかりである。つまり,芝居については文句なしの出来にならないほうがおかしい。実際,この中で鬼気迫る演技を見せる黒沢年男と天本英世,対照的に飄々として敗戦処理を決断し実行する笠智衆が一番見応えがある。その辺は実際に映画を見て堪能して頂きたい。ワシは既に5回以上は眺めてしまっている。難点は台詞がある女優が一人しかいないという所か。暑苦しく色気のない映画としてもNo.1であろう。
しかし何と言っても,一番スリリングなのはストーリーだ。しかもこれは実際に,1945年(昭和20年)8月14日正午から翌15日正午まで,つまり,ポツダム宣言受諾を国民に知らせる玉音放送までの24時間を描いた史実に基づく物語だ,というから二重に面白い。いや,面白いと言っては不謹慎かもしれない。しかし,戦後60年以上経過した今のワシらから見れば,殆どスラップスティックかという程,お粗末な小型の二二六事件を描写しているのであるから,呆れると共に,やっぱり無責任に面白いと思ってしまうのである。
第二次世界大戦の枢軸国側において,戦争責任(ここでは「敗戦の」責任者という意味で用いる)を追求するのが一番ヤヤコシイのは日本である。ドイツやイタリアのように独裁権力を持ったヒトラーやムッソリーニという「個人」が不在だったからである。強いて言えば,二二六,五一五事件を引き起こし,中国東北部から権益を拡大しようとした日本陸軍の将校クラスにその責任を帰す,というのが今の日本における一般的な認識と言うことになる。更にそこから個人としての責任者を持ち出そうとすると・・・ま,東京裁判で処刑されたあの方々,ということになるのだろうが,石原莞爾はどうなんだ,いや,もっと上に統帥権を持った天皇という存在があっただろう・・・という議論は未だ絶えることはないけれど,こういうゴタゴタが未だ収束しないと言うことは,やっぱり陸軍というコアグループが日本の世論と政治を引っ張って戦争に突入していった,という他ないってことなんだろう。そしてそれを証明する事実は山ほど上がっている。その事実の一つが,「日本のいちばん長い日」,つまり八一五宮城事件なのである。
事件を一言で言うと,ポツダム宣言受諾に反対する日本陸軍の若い将校達が近衛師団長を殺害し,玉音放送を阻止するため皇居やNHKを一時的に占領,しかし関東を統括していた東部軍首脳にあっさりと事件は鎮圧されてしまうというものである。14日深夜から15日午前中に起こったことなので,とても短い出来事であるが,二二六や五一五事件とは異なり,皇居及び天皇の居住地(御文庫)まで取り囲んでしまったのだから,これが長引いていれば原爆の数個は追加投下されていた可能性もある,歴史的にもないがしろに出来ない事件である。
しかし,それが鎮圧された後で振り返ってみると,この事件,かなりクーデターとしては出来が悪い。陸軍全体が「承詔必勤(意訳:天皇がポツダム宣言受諾を決断したのだから,黙ってそれに従え)」でまとまっていたにも関わらず,その雰囲気を理解せずに一部の青年将校が激高して暴れた,という感が拭えない。しかしそれを実行してしまう「雰囲気」が,日本陸軍内部では充満していたということは確かだろう。そしてその雰囲気熟成が昭和に入ってからなされており,その最後の小爆発がこの宮城事件である,と解釈できる。そう考えると,やっぱり「戦争責任」を個人単位で考えるのは相当難しいんじゃないかなぁ,となってしまうのである。
映画の原作となった半藤の「決定版」は,映画では演出の都合上端折られていた事実も含めて綿密に事件の推移が描かれており,イケイケドンドン日本男子が死滅するまで(「二〇〇〇万(人)の特攻(隊)を出せ」だもんなぁ),という雰囲気の日本陸軍を押さえ込むのがどれほど大変だったことか,イヤと言うほど知らしめてくれる。映画の方も,事実を曲げず,象徴的な「絵」,例えば畑中少佐の狂気じみた情熱,計画が失敗した時の椎崎中佐の激高ぶりなどをうまくストーリーに組み込んでいるので,映画だけを見て宮城事件を勉強した気分になっても,何ら問題ない。どちらもノンフィクションとして,映画として優れた作品になっているのである。
さて,敗戦処理,ということでは,日本では幕末期に幕府側の実質的な責任者として活躍した勝海舟という人物を忘れることは出来ない。半藤が1965年にまとめあげた本書は最初,営業上の理由もあって大宅壮一の名前で出版されたが,そこで大宅はこんな序文(P.3 – 5)を寄せている。
今日の日本および日本人にとって,いちばん大切なものは”平衡感覚”によって復元力を身につけることではないかと思う。内外情勢の変化によって,右に左に,大きくゆれるということは,やむをえない。ただ,適当な時期に平衡を取り戻すことができるか,できないかによって,民族の,あるいは個人の運命がきまるのではあるまいか。
そしてこの宮城事件が「平衡感覚」を試される時期の一つであったとし,本書の意義をこう述べている。
敗戦という形で,建国以来初めてといっていい大きな変化に直面したとき,全日本がいかに大きくゆれたかを,当時日本の中枢にあった人々の動きを中心に調べたら,幕末期のそれと比較して面白い結果が出るのではないか。
結果として逆転しちゃっているけど,半藤は宮城事件と比較対照となる「幕末期のそれ」を2003年に上梓し,2008年に文庫化した。それが「それからの海舟」である。
西郷隆盛率いる官軍に対し,幕府側の責任者として江戸城引き渡し(1868年3月14日)を決断して実行した勝海舟の存在を知らない日本人がいたら,それこそ非国民のそしりを免れ得ない。しかし,それ以降の「敗戦処理」に勤しむ海舟を面白く描いた読み物はかなり少ない。司馬遼太郎に至っては,明治期の海舟は大言壮語や韜晦が酷く信用ならない,と一言の元で切り捨てているぐらいである。古くは福沢諭吉が政府高官になっていた海舟を「痩我慢の説」で非難しているところから発するようで,半藤はこの福沢の批判をかなり詳細に取り上げ,分析している(第11章)。全編これ「海っつぁんびいき」の威勢の良い半藤の啖呵で満ちている本書であるが,歴史的事実と,海舟非難論を書いた福沢の個人的,社会的問題意識も併せて論じているから,単なる卑俗な海舟擁護論になっていないところが半藤の,ジャーナリストとしての「平衡感覚」なのであろう。
そんな訳で,維新後の海舟の評判はおおよそよろしくないのだが,戦後になると,その大言壮語の中にきらりと光るモノを見いだして再評価する動きも出てくる。例えば古山寛・谷口ジロー「柳生秘帖 風の抄」は,海舟の談話における一言がヒントになってシナリオの骨格が出来上がったものである。
それ以上に,思想的な影響を受けていると思われる作品が,安彦良和「王道の狗」である。Comic新現実Vol.1でこの第37話が抜粋されているが,そこでは晩年の海舟が,同じ島国のイギリスが帝国主義に走っている現状をふまえた上で,日本はそれを真似するのではいかん,と釘を刺し,こんなことを言う。
「アジアの海は下町の横町だよ!」
「支那も朝鮮も古い御近所だ」
「つき合いってもんがあるだろ」
「これからは今まで以上にそれを大切にしなくちゃいけねえ!」
出典は多分「氷川清話」あたりかと思うが,あいにく手元にそれがないので(職場に死蔵されているはず),半藤の書から孫引きさせてもらおう。
「日清戦争はおれは大反対だったよ。なぜかって,兄弟喧嘩だもの犬も食わないじゃないか。(中略)
おれなどは維新前から日清韓三国合従の策を主唱して,支那朝鮮の海軍は日本で引受くる事を計画したものサ。」(P.276)
漫画の台詞と,この主張を両方読んで,ああなるほど,サヨクというか平和主義者を代弁して,安彦良和は勝海舟の口を借りているのだな,と会得したモノである。半藤の著作はこの戦後の風潮とは無関係に著されたものであるけれど,太平洋戦争を主導した「雰囲気」への嫌悪感を持っているという点は間違いなく共通している。
1945年8月15日と1868年3月14日を繋ぐ,半藤の大仕事は世紀をまたいでここに一応の完結を見た。鈴木貫太郎と勝海舟,共に敗戦処理を主導した人物とそれを取り巻く環境,そしてそれに対する論評をマゼコゼにして優れた読み物にした労作は,日本の戦後の民主主義がきちんと機能してきた証として誇っていいものだと思う。こういう言い方はある種の人々の憤激を誘うかもしれないけど,ワシ個人は「負けて良かったのだな」と思うのである。そして,「良かったな」と後世のワシらに思わせるだけの仕事を成し遂げた両人に対して,加えてこの両人を取り上げてくれた半藤にも,心からの謝意を表したいと思うのである。




