「大砲とスタンプ 1」 [ Amazon ] 978-4-06-387072-5, \562
「靴ずれ戦線 1」 [ Amazon ] 978-4-19-950281-1, \800
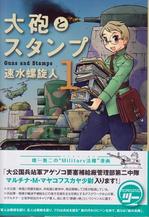
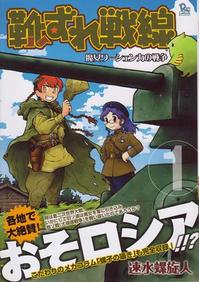
休刊前のComicリュウに突如掲載されるようになった「ツレヅレメカコラム」で速水螺旋人の暖かみのある描線とみっちりつまった情報量のあるイラストに魅了されて以来,同人誌やイラスト集を読みあさってきたが,この年末にはとうとう2冊のマンガの単行本が出版され,しみじみ堪能したところである。
しかし,改めて思うのだが,この人,ホントにひねているというのか,一筋縄ではいかないというのか,マニアックでコアなファン層以外には浸透しづらい特徴があることに気がついた。いや,もちろんこのみっちりつまった絵が苦手という人が多いということは当然としても,それ以上に,マンガのストーリー展開に癖があって,好きになる人はそこがたまらない魅力なんだが,普通のわくわくどきどきするストーリーを期待する大勢の方々には「肩すかし」が多いように思えるのだ。その肩すかし具合,実は速水の膨大な知識量がつぎ込まれた結果なのではないか,というのがワシの見立てなのだが,さてどうかしらね。
まず,モーニングツーで連載されている「大砲とスタンプ」から見ていこう。スマートなデジタル機器なんて見当たらないアナログ的世界において,大公国と帝国の連合軍 vs. 共和国という図式の戦争が続いている中,表の派手なドンパチを支える事務職・大公国兵站軍のマルチナ少尉がアゲゾコ要塞に赴任するところから物語が始まる。しかし,地図を見ると,大公国が今のロシア,帝国が東ヨーロッパ,共和国がトルコからギリシアを含む地域に見えてくるのだが,架空戦記っぽい作りなのかな? その辺の考察についてはゲーム関係に詳しい方にお任せするとして,一番地味で官僚的な「兵站」に着目するあたりが既に変。そう,速水はソビエト連邦的官僚主義と,宮崎駿の如きもっさりアナログメカが大好きなインテリ変人なのである。それでいてストーリー展開は妙にシニカルなところがあり,売春婦のような文盲(差別語なのかな?)の女性が兵長にのし上がっているわ,中立国の嫌みな記者団は重要人物に間違えられてあっさり銃殺されちゃうわ,占領下の銀行家は浪速の商人並みに渋ちんだわ,なんつーか,よくもまぁここまでアンチクライマックス的リアルでシニカルなシチュエーション,即ち「肩すかし」をてんこ盛りにするもんだと呆れかえるほどである。
その変人ぷりは,第2次世界大戦におけるドイツ vs. ソ連,即ち「大祖国戦争」(ソ連側の呼び方ね)を題材に取った,「靴ずれ戦線」で更に度を増すことになる。まず,唯物論で凝り固まっているはずのボルシェビキ・共産党が率いる内務省の役人・ナディア少尉が魔女の所に徴兵にくるというところから始まるってあたりが相当シニカル。速水本人は,ソビエト軍が日本を占領した暁には共産党幹部にのし上がるつもりでいるらしいが,こんなマンガを描いていては,即座に人民裁判送りで自己批判を迫られて失脚すること間違いない。内容に至っては,魔女ワーシェンカとナディアのコンビが魑魅魍魎と戯れる(?)というもので,大体,ソビエト軍のゾンビ(これだけでも爆笑ものだ)が出てくるという発想が凄い。もうどこまでこのデタラメかつシニカルな暴走が続くのか,ワシは手に汗握って楽しんでしまうのである。
肩すかしっぷりも共通していて,ワーシェンカが恋心を抱いた若い兵士はあっという間に死んでしまって死神の餌になるし,ユーゴスラビアではパルチザンを匿った村人を虐殺するウスタシャ(ドイツ側に付いたクロアチアの民族軍事組織)将校をほったらかしして,いつもの化け物ファンタジーにストーリーが流れていく・・・普通なら「石の花」的展開を目指すと思うんだが,その辺が坂口尚と速水螺旋人の作家性の違いなんだろう。
所謂アキバ系に好まれる絵柄であることは間違いないし,そのマニアックなこだわりっぷりは,それ故に普通の読者にはついて行けない部分もあるやもしれない。若くて純粋まっすぐな方にはシニカルぶりが気にかかるかもしれず,すれっからしの中年オヤジ・オバサンの方が「肩すかし」を楽しめる作品なんだろう。速水の歴史的・軍事的・ゲーム的知識の深さがもたらす芳醇なバカ騒ぎが堪能できるこの2冊,年末の喧噪をBGMにして楽しむには格好の作品であること間違いないのである。
内田麻理香・高世えり子(絵)「理系なお姉さんは苦手ですか?」技術評論社
[ Amazon ] ISBN 978-4-77414753-6, \1480
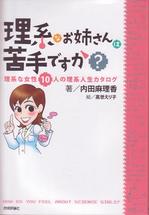
のっけから苦言で申し訳ないが,本書のタイトルはもう少し何とかならなかったのか。このタイトルのままではエロマンガの棚に置かれると間違ってフェチな男どもが妄想コミで買っていきそうである。いや,それをあえて狙ったというならいいのだが,表紙の高世えり子によるグラマラスな内田のカット(美・・・いや余計なことは言うまい)が載っている分さらに誤解されそうなので,一応言っておく。・・・ワシの頭が腐ってるだけかしらん。
ワシ自身,男女偏見のない人間かどうかは定かでないのだが,多分,数学科としては珍しい部類だと思われるので,まずはワシの大学院(修士・博士)の指導教員が女性だった,ということは申告しておきたい。女性だから指導教員に選んだということではなく,流れ流れて数値解析を専門としている先生を探していたらたまたまぶち当たって受け入れてくれた,ということである。一応,著作があるのは知っていたが,それを読んで感動して弟子入り,という美談は一切無い。むしろ,その内容がワシにとっては優しすぎて専門的には(?)を付けていた(失礼な話だが事実だから仕方ない),ということもあり,大学院の6年間(間1年開くので実質7年)はワシの好きなようにやらせて貰った。おかげで色々あったが(特に博士号取得直前の,名目上の指導教員とのいざこざは思い出すだけでもイヤ),今のワシがあるのはこの先生のおかげであって,足を向けて寝られない。今でも齢90になろうという先生の所に迷惑も顧みずお邪魔して駄弁らせて頂いているのだから,縁というのは不思議なものである。
その先生は自由闊達な方で,誰とでも気さくに打ち解けて話してくれる。人見知りの多い理系人間の中では特筆すべきコミュニケーション力を誇っているのだが,その先生ですら,随分と大学内では辛酸を嘗めたらしく,たまに愚痴っぽいことを漏らしていた。実際,都立女専(首都大学東京の前身)を出,日大に助手として着任してから長いこと助手に留めおかれてろくに論文も書かせて貰えなかったとのこと。ワシからすれば信じがたいが,連名でもない単著論文も投稿するに当たっては教授の許可が必要だったという時代があったらしい。そのせいもあってか博士号取得も遅く,教授に昇進したのも定年の何年か前ということになってしまった。・・・しかしワシは思うのだ。それでも同年配,あるいはその後輩に当たる女性研究者の中でもまだマシな部類ではなかったか,と。
・・・という女性受難の時代が長かった以上,今頃「理系にも女子を!」と唱えてもそう簡単には方向転換できるはずがない。偏見だってなくなっていないし(悲しいことだが「女性は理系には向かない」と公言して止まないバカどもがいるのは事実だ),何より教員に女性が圧倒的に少ない。文科省も慌てて女性理系研究者のインタビュー集などを作ったりしているが,ワシから見るにあれは全体としては逆効果なんではないかと思えてくる。女性にとって居心地の悪い世界でピカイチの業績を上げて勝ち残ってきたエリートばかり集めても,普通の女性にとっては眩しすぎて,自分の見本とは思って貰えないのではないか。もう少し普通の仕事をしている普通の人に「理系女子」を語って貰った方がいいのではないかと思っていたのである。
で,本書が出たのである。まさにタイトル以外は理想的。ワシの出身大学のSF研の方も出ていて,ひょっとして本人とどっかですれ違っているのではないかと思われる方もいらっしゃる(コミティアとかでも・・・)。職業も様々で,高校教員,大学教員,イラストレーター,プロデューサー,デザイナー,パーソナルヘアカラー講師(そーゆー職業もあるんですな)・・・と,よくもまぁこれだけ集めたなぁと感心する。カフェ・サイファイティークのコネクション(「応用化学科の逆襲」は大好きな同人誌だ)もあってのこととは言え,やっぱり労作であることは間違いない。文科省も見習って頂きたい。
個人的にはほっといても理系女子は増える傾向にあるし,あまり無理強いするのもどうかと思っているのだが,ICT系には随分女性が増えているから,分野ごと,まだら模様的に男女比率は等しくなってくるのだろうと楽観視している。それでも,「女のことだからやっぱり文系に」というアドバイスを親類縁者,高校教員からされることはしばらく無くならないだろうし,男が圧倒的に多い学部・学科に進んでしまうと,ワシの指導教員ほどではないにしろ,どうしてもマイノリティ的扱いになることもあるだろう。そんな時,本書のように人生の先の先に明るい未来があるのだと指し示す文献は絶対に必要だ。是非とも「理系」への興味のあるなしにかかわらず,全ての女性並びに頭の固い年寄りに読んで貰いたい一冊である。
雲田はるこ「昭和元禄 落語心中」ITANコミックス
[ Amazon ] ISBN 978-4-06-380514-7, \562
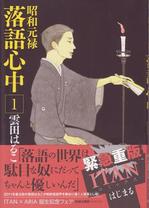
堀井憲一郎に比べると1/1000程度しか落語を聞いていないワシだが,たまに寄席に行くといいこともある。今年(2011年)においては,何より震災直後に聞いた,鈴本演芸場での橘家文左衛門の「文七元結」が絶品で,「そういう演出もあるんだなぁ~」と感心しっぱなしであった。広い客席にぱらぱらとごま塩程度しか客がいない寂しい夜席だったが,あの熱演ぶりにワシは痺れたのである。・・・あ,ひょっとして男に惚れるってこういう感覚なのかもしれない。
残念ながら,今の落語界では女性の落語家はお勧めしかねる。それだけ昔の封建社会的因習が強い世界なのだが,それ以上に,春風亭小朝の言を借りると,古典落語は男が語って面白いように完成されたモノなので,女性が演っても違和感がどうしても残ってしまうという事情も大きい。桂米朝師匠が女性の噺家を育てる自信がないと言って女弟子を取らなかったのも頷けるのである。
つまりそれだけ「男臭い」のが今の落語なのである。それを真っ当に描こうとするとどうしてもオッサン臭くなり,加齢臭に充ち満ちた世界になる。古谷三敏のようにシンプルな線で白っぽく描いてくれるのが,ワシにとってはちょうどいい嵌まり具合に感じられる。さて,この未知の漫画家・雲田はるこはどういう描き方をしてくれるのか・・・と買ってみたらびっくり。こりゃ完全にBLの世界,いや,もっと懐かしい,「やおい」ではないか。そこからは一気通貫,真っ当なマンガなのにエロエロなカップリングが妄想されて止まらなくなってしまったのである(バカ)。
大体,モノホンの落語家にこんな線の細い奴いねーぞ,と毒づきたくなるが,もちろんモデルらしい人物は思い当たる。主人公の強次の師匠・八雲は当代きっての人気者,出ただけで客席が沸くというから,まぁこれは先日亡くなった立川談志がモデルだろうし,懇意にしている上方の萬歳師匠は桂米朝,その実子で弟子の萬月は桂米団治を彷彿とさせる。しかし,実物とは似ていない・・・っつーか,萬歳師匠を除いては全員「やおい的色気」に満ちた人物になっていて,まぁ腐女子でなくても妄想してしまうのは無理ないという作りなのだ。
どこまで意図しているのかは知らないし,単なるワシの勝手な思い込みなのかもしれないが,男臭い落語界を見ているうちに雲田はるこにはやおい的師弟関係が見えてきたのか・・・というほど,ワシにとっては懐かしい「やおいマンガ」なのである。2巻が来年早々に出るそうなので,しばらく追いかけて,「らっぽり」的読後感が味わえたらなぁ・・・というのは年寄りマンガ読みの勝手すぎる願望かしらん?
西川魯介「作家 蛙石鏡子の創作ノート」白泉社
[ Amazon ] ISBN 978-4-592-14665-0, \619
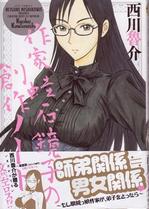
西川魯介はフェチに淫した作家だという解説をどこかで聞いた(Wikipediaだっけか?)。ワシはフェチズムってものを良く理解していないのだが,「ある特定事象にのみ性感帯を刺激されるという性癖全般」を指し示す用語だと解釈すれば,本書を読んでなるほどと頷けるのである。
最近のエロマンガというものにはとんと疎いのだが,「使える」エロマンガを探していたら,オタクビームさんと希有馬屋さんの作品にぶち当たったので,早速取り寄せて使って読んでみた。で・・・うーむなるほど,「付箋」はこんなに小さくなっていたのかとか(既に付箋の意味が無いよな),エロ表現のエスカレーションはここまで来ていたのか,とか色々勉強になったのである。まぁ,こーゆー作品を18禁と知らずに読んだカタッ苦しい方々がいきり立つのも理解できるよなぁと思うと同時に,ここまで日本のエロ表現が普遍的なものになっちゃった以上,パターン化して普通のマンガにも転用されるのも無理ないよなぁと思わざるを得ないのである。その善し悪しは道徳屋さんと政治屋さんにお任せするが,今年ヒットしたマンガでも「花のズボラ飯」なんてのは完全にエロマンガが開拓した表現を食に転用したからこそ成立した作品なのであるからして,あんましエロを締め上げるとマンガ自体が日干しになるという危惧も理解できるのである。
で,本書なのだが,巨乳な作家・蛙石鏡子の創作や,それに刺激されて妄想を繰り広げる弟子・笹巻キゼンの「うすらエロいラブコメ的様相」(著者あとがき)が軸となっている。ヤングアニマル増刊Arasiに2010年から11年にかけて連載された短編を纏めたもので,前編これエロ・・・というのは妄想止まりであり,なんだかんだ言っても西川の描きたかったのは「ウンダーカンマー」にも共通するこの「うすらエロいラブコメ」なのではないかと思わざるを得ないのだ。
何故か? それは本書で展開されるエロ表現がパターン化されたそれとしか思えなかったからである。もちろんそれは全て「妄想」のたぐいなので,既存のエロ表現をなぞるだけでいいと割り切っているのかもしれないが,本当に好きならもう少し表現の血肉になってもいいのではないか。どうも西川の趣味,即ちフェチっぷりは「うすらエロいラブコメ」に発揮されているのではないかと思えて仕方ないのである。何せ本書で一番ワシがエロいと感じたのは蛙石鏡子が頬を赤らめてキゼンに語りかけるコマなのだから。
しかし,本書を読んで改めてワシはツンデレが好きだな・・・ということを認識した次第である。鏡子萌え,なのである。
唐沢なをき「怪奇版画男」小学館文庫
[ Amazon ] ISBN 978-4-09-196030-6, \600
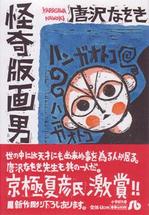
本書は1998年に出版され,世の漫画家をして震え上がらせた怪作,「怪奇版画男」を文庫化したものである。ワシはオリジナルの単行本も買ってあったが,人に貸したら戻ってこなかった。以来,枕に涙して暮らす日々を送っていたのだが(嘘),本年,この怪作が再び世に出たことを弥栄弥栄と喜び,いそいそとレジに本書を運んだのである。
無駄な努力というものが,これほどの衝撃,いや笑撃を与えてくれるモノだとは,本書のオリジナル単行本が出るまで知らなかったのだ。漫画作品これ全部,台詞まで含めて全部手彫りのアナログ作品の手間たるや恐ろしい程である。オマケに,文庫化に当たって新たに付け加わった京極夏彦の解説,あとがき,そして帯や奥付に至るまですべて版画。全くこの資源と労力の無駄遣いっぷりは凄まじい。原稿料が規定通りとすれば,恐ろしいほどのコスト超過。これ以降,版画マンガにチャレンジする漫画家が出現しないことは当然のことなのである。・・・と,今気がついたが,畑中純だって全編これ版画という作品は少なかったよなぁ。まぁ,無理もないのである。これに引き続くコスト超過マンガといえば,梅吉の切り絵マンガ以外に思いつかない。それほどの快挙なのである。
・・・とまぁ,費やされた労力だけでも凄いのだが,それ以上に「版画」というアナログな表現手法の持つ力強い線の魅力がまたいいのである。表現として優れているってのは,版画男のオリジナルたる棟方志功の作品を見れば一目瞭然だ。長部日出雄の解説によると,棟方の作品の多くは日本的な題材だが,所謂それを売りにしたジャポニズムではなく,もっと原始的で人類共通の美術表現になっているのだという。実際,欧米にも棟方のような平面的かつダイナミックな簡素表現作品があるんだそうな。
その棟方の描く顔に岡本太郎を混ぜたような版画男が縦横にギャグを展開する白黒(カラーもあるけど)の画面の力強さはどうだ。これを昇華させると畑中純の芸術作品になるのだろうが,そこまで行っちゃうとギャグとしては成立しない世界になる。その手前に留まってギャグに徹する潔さ(単にメンドクサイだけなのかも)がワシらの感動腺を震わせ,費やされた労力を想像する回路に繋がって脳髄をショートさせるのである。
つーことで,本書は永久保存品として確保されたのである。もう誰にも貸さないからね。読みたければ,買え。