[ Amazon ] ISBN 978-0-521-140638, \4213(2010年9月現在)

SIAM News 2010 SeptemberにP.J.Davisによる本書の書評が載っていた。つらつら読んでみたら,これがなんと,Abramowitz and Stegun編集の”Handbook of Mathematical Functions“(以下,A&Sと略記)の改訂版にあたるというではないか。早速Amazonから購入ボタンをぽちっとなして,手元に届いたという次第である。
まーしかし買ってよかった。こちらはカラー刷り,CD-ROM付(原稿のPDFファイルが丸ごと入っている),さすがにデジタル版のリンクは再現不可能だが,A&Sには入っていなかった特殊関数とか,最新の文献リストまで掲載されている。時代が違うので数表はほぼ皆無になっているけど,いまだに新規参入の特殊関数が考案されるんだから,計算屋としては,やっぱ新しいものを常備しておきたい。
関数という概念が固まる以前からコンピュータが一般化するまで,数表というものは人間社会には必要不可欠のものであった。一松信によると,Napierの対数表にその起源が求められるらしい。また,科学技術が進むにつれて,近似計算でしか表現できない現象も現れてきたようで,D.A.Grierによれば,ハレーすい星の軌道計算はクレローの近似計算(離散フーリエ変換を使ったものらしい)によって実現できたが,この計算はクレローの二人の友人を巻き込んで5カ月間かかったとのこと。以来,産業革命で計算のニーズは高まり,大量の計算ニーズが生まれ,フランスの土木技術者・プロニーによって19巻の三角関数・対数関数表が作られる。もちろん,すべての計算は人力で行われていた時代であるから,大量の計算労働者を動員しての成果である。
で,ENIACから商用電子計算機=コンピュータが一般化するギリギリの時代,最後の人力計算(たぶん,機械式の手回し計算機は使っていたと思うが)による成果が,1964年に発行されれたA&S,すなわち

であった。土台はルーズベルト大統領のニューディール政策の一環として行われた関数表作成プロジェクトにある。土木工事同様,人的資源の大量導入が必須だから,景気テコ入れのための公共事業としてはうってつけだったという訳。
A&S発行後,関数計算はコンピュータで自動的に行うものとなり,以後発行される関数ハンドブックは,数表よりも,解析的性質,計算方法や近似式の記述がメインとなる。ほぼ50年ぶりの改訂版である本書はさらにその先を行き,具体的な計算方法は文献とソフトウェア(大方はNETLIBのTOMSにある)へのリンクに譲っていて,メインの記述はもっぱら解析的性質とかグラフ(3Dカラー!)である。
A&Sのガンマ関数の章を書いたDavis先生によると,そもそもA&Sの出版自体,「私たち著者は恥ずべき海賊版と考えている」(“we authors considered shamefully pirated”)だっつーんだから,穏やかでない。政府発行のものだから不満足なバージョンだったってことなのかどうか,詳細は不明である。もっともこの記述に続いて「とはいえ,法律的には文句の言いようがない」(“but that, legally speaking, were not”)とあるところや,A&SがNIST(National Institute of Standards and Technology)の前身であるNBS(National Bureau of Standards)から出ていること,そしてA&S発行後,25年間も科学書の売り上げトップになっていたことを考えると,著者らの完璧主義に付き合う余裕がないほど早期発行の要求が強かったんで,政府権限で「さっさと出さんかゴラァ」と強引に出版させたってことなんだろうなと想像する。・・・でまぁ,半世紀近く経過してようやく改訂された本書とフリーアクセスなデジタル版が出せた訳で,Davis先生の感激たるや,ワシみたいな若造には想像に余りある。
それににしても,ぱらぱら本書をめくってみると,もうすっかり時代は変わったなぁと,若造でも嘆息してしまう。数表が皆無になった代わりに,FortranやC/C++といった言語で関数計算が記述され,それをそのまま自分のプログラムに組み込んでしまえばいいってんだから。軍隊式に計算労働者を組織して検算付の超低速な並列分散処理をさせていた時代に比べると,石器時代から現代社会への移行並の大変化が,50年程度の期間に圧縮されてしまっていることになる。ワシだって標準ライブラリにない関数はごそごそTaylor展開式を引っ張り出してプログラミングしてた時代があったんだが,それもかれこれ20年近く前になってしまうのだなぁ・・・いや,年は取りたくないものである。
が,否応なくワシは,精神構造は若造のまま,肉体的には年寄りになった。本書は当初,A&Sのように完全フリーで出すことも議論したようだが,結局,CD-ROM付の印刷版も含めて著作権縛りは残し,その代わりにフリーアクセスのWebバージョンを広く公開することにした。しかし,老眼が入ってきつつあるワシの目にはちとWeb画面の数式は読みづらい。結局,印刷版を買ってみて「こっちのほうが断然きれい!」と嬉しくはなったものの,もうすっかり若くないことを思い知らされて,ちょっと気分が落ち込み気味なのである・・・ま,関数ハンドブックなんてものを面白がっていること自体が年寄りの証拠ではあるのだが。
糸井重里「あたまのなかにある公園」東京糸井重里事務所
[ 1101.com ] \1470
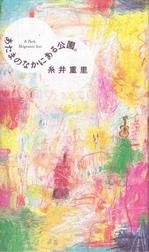
2007年から毎年春に一冊ずつ刊行される,糸井重里の短い言葉をまとめた単行本シリーズも4冊目となった。ワシは欠かさず購入していて,ここでも第一弾「小さいことばを歌う場所」,第二弾「思い出したら,思い出になった」を取り上げている。書いてないけど,第三弾「ともだちがやってきた」も当然購入して熟読している・・・つーか,一つ一つの言葉はやさしい単語で構成されていて短いので,普通に読めば「熟読」になってしまうのであるな。
第四弾にあたる「あたまのなかにある公園」だが,前の三冊と取り立てて変わったところはない。編集担当・永田による文章の抜粋や構成はほぼ同じで,時折,糸井が撮影して「きまぐれカメラ」に掲載した写真が挿入されたり,本の最後の方には「別れ」や,それに伴う「せつなさ」を表現した文章がまとめられているところなども同じだ。そして,毎回,「ふ~ん,これは鋭いなぁ~」と感心するのも相変わらずである。
つーことで,いくつかワシが付箋をつけた文章を引用してご紹介したい。
—-
「プレゼンテーションの時代が,終わるんだよ」
と,ある打ち合わせ中に,ぼくは言いました。
(略)
「ダメ」は,簡単にわかります。
うまく「プレゼンテーション」できればダメにならない,
なんてことは,あっちゃいけないんです。(P.54~55)
—-
そうそう。そう思うよ,昔のじぶんに賛成です。(P.157)
—-
小学校から大学にいたるまで,
学校の勉強が,
ともすれば退屈に思われやすいのは,
問題と答えの両方を知っているものが,
先生という名で,すでにいるからだ。
政治家の言葉が,
どうしてもいやらしくなるのは,
疑いの指先が,
絶対に,相手のほうにしか向いてないからだ。
ぼくが信じられるのは,
自分に疑いの目を向けられる人だ。(P.176~177)
—-
「ねばれ!」しかないんですよね。たいていのことは。
天からの啓示も,ありがたい偶然も,
ねばっている人のところにやってくるわけで,
おそらくそれは「考えつづけている」というのと,
同じことなんじゃないかなぁ。
(略)
おれも,ねばるよ。おまえも,ねばれ。(P.238~239)
—-
それぞれの胸に刻まれたことが,
あとで「よかったな」と思えるようになるといいですね。(P.299)
—-
毎年継続して4冊も購入し,読み続けているワシは,いつも読了する度に「よかったな」と思っている。経験に裏付けされた,素朴な言葉は,毎年ワシをさわやかな気分にさせてくれるのだ。
「土門拳の昭和」クレヴィス,西原理恵子「きみのかみさま」角川書店
[ Amazon ] 「土門拳の昭和」, \2100
[ Amazon ] 「きみのかみさま」, ISBN 978-4-04-874091-3, \1300

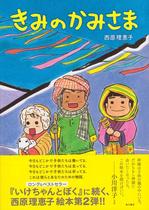
土門拳,という名前を最初に意識したのは,やはり水島新司「ドカベン」の登場人物として「土門」なるイカつい投手が現れた時だろう。デカイ体から繰り出される球はひたすら重く,ヒットを飛ばすのが至難の業,という設定だった。それ以来,「土門」=「重量感」という公式が頭にこびりついてしまい,後に,同姓の写真家がいると知ってからも,「きっと重たい写真を撮っている人なんだろう」という思い込みが定着してしまったのも,無理からぬことなのである。
でまぁ,この度,土門拳の写真展を拝見する機会があって,デカイキャンバスサイズに引き延ばされた作品をじっくり眺めることが出来たのだが・・・いやぁ,重たいどころじゃないな,この人,とワシはつくづく本物の凄みを思い知らされることになったのである。で,会場で販売していたこの「土門拳の昭和」を購入してきたのである。
思い知ったのはワシだけじゃないようで,かの大御所マンガ家・西原理恵子も,「でも土門拳の『筑豊のこどもたち』を見たときは,「こりゃ,負けたわ」って思ったけど。」(「ユリイカ」2006年7月号,P.128)とシャッポを脱いでいる。
写真展でもこの筑豊地区の炭鉱街における子供たちを撮った写真が掲示されていた。本書ではP.83~89に納められているものがそれで,腐ってボコボコになった畳のくぼみに座る女の子,両眼両鼻から液体を瀧のように垂らしてして泣く子,ボタ山の急勾配で使える石炭を拾う男の子・・・いやまぁ,ここに掲載されている作品だけでも圧倒させられる力業であることが分かる。景色の「切り取り方」が写真家の世界を形成しているわけだが,土門の目には子供たちの,仏像の,焼き物の,植物のエネルギーが迸るシャッターチャンスだけが写っていたのであろう。いや,確かにサイバラが感服するだけのことはある。
さて,そのサイバラの目にとまった「筑豊のこどもたち」が住んでいた極貧の炭鉱街ができあがった理由を,先のサイバラの発言に続いて対談相手の大月隆寛が次のように説明している(同,P.128~P.129)。
筑豊=ヤバいところ,ってのは最近また若い衆中心にいろいろ言われているようだけど,あれも実は戦後に増幅されたところあるんだけどな。明治になって炭鉱ができて流れ者の炭鉱夫が集まってきて,でも景気は良かったわけでさ。気質的には漁師と同じで「宵越しのゼニは持たん」だからバンバンカネ使うし。そんなのがわずか10年,20年で一気に廃れていったら,そりゃあ,まわりからは異様な眼で見られるよな。(中略)
業田義家の『自虐の詩』ってマンガがあるだろ。知る人ぞ知る名作。業田自身も九州の人間みたいだけど,あそこに出てくる「熊本さん」なんか,キャラとしてもディテールとしてもかなりヤバい。さっきから出てくる高知や筑豊や,なんでもいいんだけど,そういう西南日本の土地がらみ,風土がらみの「貧しさ」とそれにまつわる歴史が凝縮されてるようなところがあって,なんかもう切ないんだよね。でも,そういう「感じ」がいろいろ理屈つけなくても,ピン,とわかるのは,やっぱり西の人間なんだよなぁ。
人類全体として,20世紀に入ってからは,地域にばらつきはあるとは言え,飢餓の発生率は減っているようだし,全体として「豊か」になっていることは余り異論がなさそうだ。しかし,減ったのは絶対的貧困であって,相対的貧困はますます根を深く,全世界的に広まりつつある。
サイバラの最新絵本「きみのかみさま」は,全世界,特にアジア方面の自然風土をバックに,相対的貧困と区分されるであろう子供たちのモノローグで構成されている「絵本」である。この第3話は,フィリピンあたりの都市郊外にあるゴミの山で使えるものを探す少年が主人公だ。まさに,ボタ山を歩き回っていた筑豊の少年と同じシチュエーションである。
そう,このサイバラの最新絵本は,土門拳がかつて撮り歩いた戦後の「筑豊=ヤバいところ」と地続きの貧しさを主題とするものなのである。
前作の「いけちゃんとぼく」は正直余り感心しなかった。少女趣味がサイバラの根底にあることはいいとして,それが地に足のついていない,よくあるファンタジーに留まってしまっていると感じ,映画化したと聞いても見に行こうという気も起きなかったのである。
その反省なのかどうなのかは知らないが,本作は逆に,故・鴨志田譲と歩き回った世界各地の紛争地帯,東南アジアのディープな所に今も存在する「世界」を描いた。そこに根ざした風景に溶け込む子供たちのモノローグが,良い具合に現実とファンタジーの茫漠とした境界面を表現していて,面白く読むことが出来た。貧しい生活をしていても,現代日本で普通に豊かな生活をしていても,子供が成長する過程で必ず抱く哲学的疑問を「かみさま」に託して虚空に溶け込む様を,サイバラブルーを駆使して表現している本作は,たぶん,年寄りの方が読んでいてしっくり来るのではないだろうか。
次の日がくるように
人は生まれたり
死んだりする。
そうして
あの花のさく
向こうへ帰る。
第14話はこうして締めくくられる。
何度か倒れながらも精力的に作品を撮り続けた土門拳は,1979年に脳血栓で意識不明となり,二度と目を覚ますことなく,1989年に亡くなった。
「あの花のさく」「向こうへ帰」った土門は,サイバラにこの「きみのかみさま」を残して逝ったように,ワシには思える。この2冊を並べて紹介したのは,地続きの「世界」を表現していると,ワシは確信しているからである。
速水螺旋人「螺旋人リアリズム ポケット画集」イカロス出版
[ Amazon ] ISBN 978-4-86320-150-7, \2476
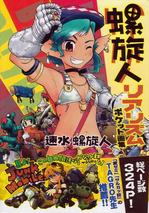
いやぁ~,恥ずかしいなぁ~↑・・・この表紙。今はやりの萌え絵から2~3世代は後退したような画風であるが,こう表紙にアーマービキニのファンタジー娘っ子を持ってこられては,なかなか本書の面白さ,速水螺旋人の真価を伝えられないのではないかと,躊躇してしまう。・・・いや,言い訳は良くありませんね,潔く言いましょう。元気な布地の少ない娘っ子の絵,ワシは好きですっ!
・・・ともかく! 本書はまず「ポケット画集」という言葉を裏切る分厚さ(324ページ!,これが入るポケットって!)と内容の「濃さ」において,2476円という,本文は完全モノクロ印刷にもかかわらずド高い定価を裏切らないものであることを,拙い文章で綴ってみたいとワシは思ったのである。
イカロス出版からは既に「螺旋人の馬車馬大作戦」が刊行されているが,これがまぁ,分厚い上に判型がデカい! しかも内容が本書の数倍詰まっているので,まぁ読みづらいったらありゃしない。いや,「読む」などという生やさしい行為を拒否しているとしか思えない作りで,さすがに螺旋人マニアの読者も,著者の同人誌以上にみっちり詰まったものは読みづらいと思ったのか,今回の「ポケット画集」はかなりすっきりした作りになっている。問題は価格で,前作が300ページもあってカラーページも含み,ポケット画集の2倍以上の判型なのに1429円,今回はカラーページなしで2476円・・・これは,プレミア価格設定なのかしらん?
価格はともかく,本書は戸田書店掛川西郷店の小さなタグにある通り,「イラスト集」と言える。TRPGのキャラクターに旧共産圏的メカデザインをまぶして中年SFファン崩れの油で揚げたようなイラストに,短いが著者の「うんちく」(偏っているけど)が入ったコメントが活字で添えられている。チマチマと手書きの小さい文字でみっちりおにゃのこの周囲に文章を書くのも良いが,近年著しく眼力が弱った中年としては,本書のように文章は立方体にゴチック体できちんと収まっている方が断然読みやすくて有り難い。本書が螺旋人を知るための教科書とすれば,前作は,更に螺旋人を探求したい人向けの資料集みたいな位置づけになろうか。
螺旋人の魅力は,宮崎駿にも共通するアナログくさい描線(とおにゃのこの可愛さ・元気さ)もさることながら,糸井重里言うところの「安売り王」であることにある。とにかくアイディアが豊富で,単に可愛いだけの萌え系イラストには15年以上前に食傷しているおっさんを魅了する,イラスト一枚に込められた「設定」の詰め込み度が尋常ではないのだ。鹿島茂のエッセイが,いちいち学術論文に展開できそうな「ひらめき」が込められていることと共通するアイディアのバーゲンセールっぷりが,この元気な娘っ子やオヤジども,軍人,丸っこくて油くさいアナログなメカから伝わってくるのである。そうでなければ単なる「イラスト集」に,しかも2476円も支払って買うわけがない。ひょっとしたら本書を刊行したことでイカロス出版が倒産するかもしれないが,そうなったらなったで,一つの物好きな出版社に自社を滅亡させるまでに惚れさせる魅力があったという証左である。ま,螺旋人の純マンガ集が出るまで潰れちゃ困るんですけどね,ワシとしては。
書き下ろしで3作,各8ページのマンガが納められている上に,螺旋人を形成した書物の紹介が巻末に入っているので,「こういうものを好む人物が日本のマンガ・アニメ文化に育てられるとこういうものを描くように成長するのだ」(そうか?)という偏見を助長するためにも,本書は日本人より諸外国で教科書として活用して欲しいものである。
山科けいすけ「サカモト」新潮文庫
[ Amazon ] ISBN 978-4-10-130391-8, \514
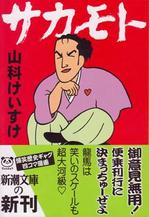
今年(2010年)のNHK大河ドラマが,福山雅治主演の坂本龍馬だというので,ドラマ開始前からドカドカ便乗本が出版された。柳の下に何万匹のドジョウがいるのか知らないが,一応,出す側も少しは頭を使っているようで,差異化を図るべく,個性を出そうとしている様子は見られて微笑ましい。個人的に気になったのは,「坂本龍馬ってホントはどうだったの? 何をした人なの?」という素朴な疑問に対して答えるもので,結局ワシは買わなかったのだが,TBSラジオ Digでは2010年5月7日放送分のPodcastで聞いた,加来耕三さんの言説が面白かった。これ聞いていると,ちゃんと弾道計算が出来た理系頭のやんちゃ者ってイメージが生まれてきて楽しくなる。司馬遼太郎の小説で過大評価され過ぎって指摘はその通りで,それはやっぱり「龍馬がゆく」が小説として出来が良かったせいなんだろうなぁ。
でまぁ,その数ある便乗本の中で,群を抜いて下らない(褒め言葉です)ものが新潮文庫から出たので,忘れないうちにご紹介しておく。それがこの「サカモト」だ。新潮社の意図として,本書を刊行すること自体がギャグになっていることは間違いない。ワシは書店でこれが並んでいるのを見て心中大笑いし喝采を新潮社に送り,さっさとレジに運んだのである。
もともと新潮社には山科けいすけをしっかり押さえている編集者がいるようで,小説新潮で連載を持たせ,恐らくは全く売れなかった(と思われる)短編集「タンタンペン」も刊行している。ワシはこの,かつての大人マンガのナンセンステイストを保持しつつ,いしいひさいち以来のキャラ者ギャグも取り入れたセンスが大好きで,見かける度に読んでいたのだが,まさかこの「サカモト」が新たに新潮文庫から,新潮装幀室のデザインセンスを疑わせるダサい表紙でまとめ直されるとは思いも寄らなかった。ここで謹んで,NHKと福山雅治に感謝しておきたい。
内容はというと,トンデモ学説に染まった勝海舟に師事したピストルマニア・坂本龍馬が,サツマイモと金玉の大きさにしか興味のない西郷隆盛や,コスプレのために潜入生活を送っているとしか思えないデカ頭の桂小五郎(木戸孝允),バイセクシャル・土方歳三に言い寄られるデブの沖田総司らと縦横無尽に交わって幕末を混乱に陥れるギャグ4コマ作品である。・・・いや,何が何やら分からない紹介文だが,分からないなら読んで下さい。ともかく下らないので,ワシは大好きである。
・・・などと言いつつ,ワシはどちらかというと,戦国時代の武将たちを弄んだ「SENGOKU」の方が,ナンセンス度合いが高くて好きだった。キャラクターの数もイマイチ「SENGOKU」に比べるとこの「サカモト」は少ない。時代が近いせいでちょっと遠慮した・・・とも思えないが,ちょっとテンションが下がったような気がして,ワシは本書の前に刊行された竹書房バージョンの単行本は買わなかった。
しかし,このたび読み直してみると,これはこれで少し「枯れた」感じがあって,山科けいすけを初めて読む読者には向いているかもしれない,と思い直した。久々に読んだこともあって,この手のギャグをびしっと決めつつ,絶対にシリアスに流れない潔さを持った4コママンガ家は少なくなったなぁと,別の感慨も沸いてきた。いしいひさいちが新時代を切り開き,業田良家がドラマを持ち込んだ4コママンガの本流とは別に,山科けいすけはマイペースに自分の世界をギャグだけでコツコツ作り上げてきたのだ。細く長く,映画化ともアニメ化とも縁なく,淡々とプロの仕事を積み上げてきた山科の大人としての態度にワシは敬意を表するべく,このぷちめれをアップしておく次第である。