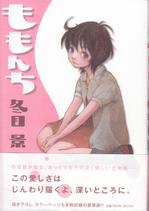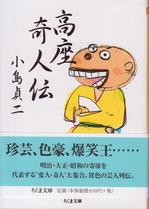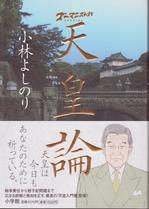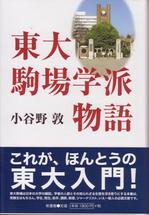[ Amazon ] ISBN 978-4-06-375722-4, \952
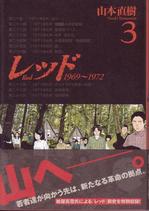
やぁあっと出ましたよ,「レッド」三巻目。で,一,二巻を読んで久しく待ちわびた所にこれ読んで・・・みんなどう思うんだろうな? ワシの感想は
「あさま山荘は遠そうだ」
というものである。何せ,本巻だけで1971年の5月~6月分にしかならないんだから。壮絶な「アレ」を期待していた向きには残念に思われるかも知れないが,ワシは逆にこの先の展開に期待を持ってしまった。単純に「じらす」というより,この後に来る,登場人物の頭にくっついている番号順に行われる筈の「事件」への伏線が張りまくられている,と感じたからである。実際にその伏線がどう今後のストーリーに反映されてくるのかは,多分,2010年に刊行されるであろう4巻を読まなければ何とも言えないが,ワシは期待しているのである。・・・ここまで引っ張っておいて,外したら怒るよ>山本直樹先生
さて,これからのお楽しみが増えただけの本巻の内容については,ネタばらしになることもない分,これ以上語ることもない。だもんで,普段はやらないんだけど,作品とは別に感心したものがあるので,それについての感想を述べることで本巻のぷちめれに代えることにしたい。
「レッド」は学生運動が盛り上がった1960年代~1970年代初頭の事件を題材にしているので,ワシらのように,それ以降に生まれた人間にとってはどーもその時代背景が分りづらい。本巻ではそれを補うために,ワシより更に二つも若い紙屋高雪が書いた解説「なぜ彼らは<革命>を信じられたのか?」が巻末に付いている。二巻では山本と押井守との対談が載っていたけど,「アレじゃこの登場人物達を押し立てていった時代の熱情が理解できん!」という読者の声でもあったのかなぁ? 少なくともワシはそこんとこを含めてこの事件をチャンと理解したくて,スタインホフの本とか若松孝二の映画とか見ることになったのだ。結果として,この事件そのものについてはよく分ったものの,時代背景を「どう理解できるか?」ということについては,以前に読んだ森毅の自伝的エッセイ「ボクの京大物語」の方が雰囲気はつかめたなぁ,というのが実情だ。
現代の左翼を自称する紙屋にしても事情は同じであるようで,14もの参考文献やドキュメンタリー映像を渉猟し,引用文を交えながら何とか彼らを持ち上げた時代を「解説」しようとしている。大体ワシの理解と一致しているし,ワシと同時代人が自分の言葉で語っているので,その内容はすんなりワシの頭に入ってくる。まずはこの名解説をまとめた労に対して敬意を表したい。
もう一つ,この解説に感心したのは,紙屋がきちんと自身が肯定する左翼思想と,「レッド」の登場人物達が行動の土台とした思想との共感ポイントを隠さずに吐露していることだ。紙屋は赤軍派と一緒にされてはたまらないと思いつつも
「しかし,それでも自分は最初の頃,そういうものに惹かれた。そうである以上,ぼく個人についていえば,まったく自分とは隔絶された無関係な存在として考えるのではなく,できるだけその論理や心情によりそいながら,そのうえで自分がどこで袂を分かったかを示したいと思った。」
と述べている。
ワシ個人の感想は,この「レッド」に描かれている事件,そしてこれから描かれるであろう悲惨な「同士討ち」が,彼らが左翼故に起こったものと理解するのは大間違いだ,というものである。ある種の強い思想を持って寄り集まった小さいグループが,抑圧的な状況下で集団生活を長期間過ごせば大なり小なり「同士討ち」が起こるものだ。1995年のオウム真理教事件をリアルタイムで知っている人間なら,アレが左翼思想とは全く関係なく起こったことを理解していよう。そして「レッド」の「状況」がアレとそっくりだった,ということも覚えているはずだ。右翼とか左翼とか宗教的とか,そんなことは事件の「様式」にしか関係しない。「同士討ち」に至る道は,あくまで思想とは関係のない「状況」に依存しているのである。真面目な人間ならば,いや,真面目であればあるほど,自縄自縛的に追い詰められたあげくにレゾンデートル維持のために,組織や思想という「名目」を盾にとって近しい人間を虐待しかねないのである。
紙屋がオウム事件を引き合いに出すことなく,ストレートに「レッド」の登場人物達の「論理や心情によりそいながら」時代解説を行ったのは潔いなぁと,ワシは感心しているのである。経済的には落ちていく現代日本の行く末を導く考え方は,右翼なワシとは相容れないところがあるが,逃げずに「レッド」と向き合っているところは,左翼も棄てたモンではない,と思わせてくれる。
・・・と,作品ではなくその解説をぷちめれしてみました。ま,たまには良いかっつーことで一つご勘弁を。