[ Amazon ] ISBN 978-4-344-98092-1, \840
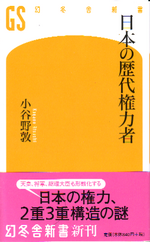
老境を迎えた学者が行う仕事はいろいろだが,学者生活の総決算を飾ろうという意図がある場合は
・自分の研究内容及びその周辺内容を含めた学問の歴史の記述
・長い研究生活を送るうちに蓄えた知識をまとめたデータベース的書物の執筆
つーのが普通のようである。「いやワシはまだ現役学者であるからして,コンテンポラリーな潮流を意識した研究に邁進するのだ!」というのもアリかと思うが,いくら何でも70歳を超えたら,少しは後進のために上記のような仕事をして欲しいよなぁと思う。ハッキリ言って老醜じゃねーか?と思える言動を取る老大家を見るに付け,ワシ自身は引退後に「学問の歴史」と「データベース」が執筆できるだけの知的蓄積を今からしておきたいなぁと思う。そうすりゃ,少しは人類の知的蓄積になにがしかの貢献ができるかもしれないし,多少の人格的障害があっても,世間のお目こぼしに預かれるだろうと期待しているのである。自分の年金支給額ばっかり気にしてヤイノヤイノ言う年寄りには正直,ウンザリさせられているのだ。
上記のうち,今のワシが読み物として好むのは「データベース」の方である。「学問の歴史」はワシが引退する20数年後までどんな変化をするのか予測不可能だから,現時点のそれを知っていてもあんまし実がないよーな気がするのだ。が,データベースなら,今のバカなワシが持っていない知識を仕入れることができそーだし,何より自分がそのうち書くかもしれないデータベースの一部に取り込むことができそーじゃないですか。何?それは剽窃であって,唐沢俊一みたいだってか? なーに,「嘘つき」よりも「ドロボー」と言われた方が,内容の信憑性にはお墨付きが付いたよーなもんなので,いいんです。大体引用元さえキッチリしていれば,自分の創作的寄与ゼロのデータベースであっても著作権がちゃーんと発生するのであるからして,立派な自分の仕事になるんであーる。・・・ま,そんな立派なものが引退後のヨボヨボジジイに完成できるかどーかは分かりませんが,ね。
で,最近だと「データベース」もコンパクトなものが好まれるのか,新書サイズのものが増えているようだ。例えば科学史家の小山慶太は「科学史年表」を中公新書で著しているし,ワシが複素関数論を習った井上正雄先生は「簡明 微分積分ハンドブック」(聖文社)を250ページ程度の新書版で出した。どっちも本来なら千ページを超える内容になりそうなものを,ペーパーバックサイズにまとめ,しかも読みやすさを求めてシンプルな文章と版組にしてある。「太い本を書きたい」というのは物書き共通の欲望だと中島らもは書いていたが,その欲望をあえて抑えているところがいいなぁ,とワシは思っているのである。
で,小谷野敦先生である。ワシより7つ上だから,まだ40代後半なんだよなぁ。それでいて今回「日本の歴代権力者」なるコンパクトなデータベースを著しちゃうというのはちと気が早いのではないか。いや,面白かったからいいんですけど,なーんか「人生のまとめ」に入っちゃったのかなぁという感じがして,愛読者としては少し寂しい・・・というのは考え過ぎか? 死なないで~,小谷野センセー(当分死にそうにないけど)。
小谷野先生は幻冬舎新書からは既に「日本の有名一族」を著しているけど,前にも書いた通り,著名人・政治家・学者の系図をまとめたものがWebページとして存在しているを知っていたので,ワシはあまり感心しなかった。ま,紙媒体で残っていた方が資料として便利なのでワシは買ったし一応読んだけど,うーん・・・下世話な本だというのが正直な感想であった。いや,品性が下世話なワシとか福満しげゆきのような人間にとっては「なーんだ,あいつもあいつもあいつもあいつも,ぜーんぶ係累がらみで出世したのか」という溜飲を下げる効能はあるので,その意味では読み物としては「あり」なのだが,一応,学者の看板を上げて商売をしている小谷野敦の著作としては「いいのか?」という気分がワシには残ったのである。
しかしこの「日本の歴代権力者」は,まともな学者の仕事の醍醐味を知らしめてくれる良書なのである。ワシが日本史の知識に疎いこともあって,それを補ってくれる記述が多い上に,大量の文献を渉猟した結果だろうが,「へ~,あの常識はまだ学問的に決着が付いてないものだったのか」という目から鱗の指摘が多く,二重に感心させられたのである。やっぱ東大出を標榜するならこんくらいの仕事はしてくれないと,ねぇ?
本書で言うところの「権力者」は,もちろん天皇ではない。本書の記述は蘇我氏から始まっていて,既に天皇は傀儡の扱いである。その後も,藤原氏による摂関政治,武家による鎌倉幕府と同様の扱いを受け続け,一時は後醍醐天皇が権力者として復活しようとするも挫折,以降も室町幕府,織豊時代を経て徳川幕府,明治維新,現在に至るまで,天皇は権力者に権威を付与するローマ法王的な役割(巻末に論考がある)を果たす存在になっていく。だから本書で言う「権力者」とは,その時代毎に,本当の権力を握っていた人物であり,それが判然としない時代には複数の人物が挙げられたりする。例えば,室町幕府創設時には足利尊氏・直義・高師直の三人が,戦前期には首相と共に内大臣・木戸孝一も挙げられている。この辺り,取り上げる人物は「恣意的のそしりを免れない」(P.4)と小谷野も認めている通りで,歴史にうるさいオヤジ連中の「あいつがいるのに何でコイツがいないのだ!」とゆー議論を巻き起こす可能性が高い。ま,それもまた本書の楽しみ方の一つである訳で,一人当たり1~3ページ程度とコンパクトにまとめられた記述には無駄がなく覚えやすいので,床屋談義のネタとしても有用である。
それにしても40台でこの著作かよ・・・と思ってしまう。いや,売れそうだから書いた,というのは本音としても,エライ手間と時間がかかっているんじゃないかと思うと,ホントに元が取れるんだろうか? 大体,こんなに知識を仕入れちゃったら,後は死ぬだけなんじゃないかと,愛読者としては心配になってしまう。老境に達する前に書いちゃったコンパクトなデータベース本を土台に,これから先の小谷野先生のお仕事がどのように飛躍するのか,はたまた・・・となってしまうのか,ちと心配な今日この頃であります。
雷門獅篭「雷とマンダラ」ぶんか社
[ Amazon ] ISBN 978-4-8211-8683-9, \838
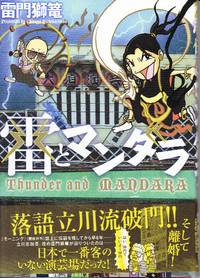
今の雷門獅篭(かみなりもんしかご)が,その昔,立川談志の前座・立川志加吾であったころ,一度だけその落語を聞いたことがある。浅草の雷5656会館の立川流一門会の,確か開口一番だったと思う。しかしその内容は皆目覚えていない。噺家らしからぬ長身のイケメンにーちゃんが出てきたなー,という印象を持った以外,その内容に感銘したとか大いに笑ったということは全くなかった。とどのつまり,まるっきり面白くなかったのだ。まあ前座の落語に面白いモノがあった試しがないのが普通なので当然と言えば当然だが,落語界の東大と呼ばれるぐらい,厳しい昇進のルールが定められた立川流の噺家ならば,前座でもそれなりに面白いかなーと期待していただけに,肩すかしを食ったというのが正直な感想であった。
故に,談志直系の前座を全員破門にしたという報道を聞いた時は,まあ当然だな,と思ったものだ。いくら昇進が厳しいとは言え,何年も二つ目になれないようなモノどもを,齢を重ねた談志が見切りを付けるのも無理はない。後に談志の高弟・談春の本を読んだら,全く同じ感想を語っていたから,世間の反応もそんなモンだったと思って頂いて間違いない。
ただ,獅篭が他のダメ前座どもと違っていたのは,四コマ漫画を講談社の青年漫画週刊誌・モーニングに連載していたこと,そして自分のWebページを持ち,ちまちまとメンテナンスを重ねていたことである。落語は面白くないが(シツコイ?),自分のパブリシティは怠りなかったのだ。それを継続せしめる「生きるエネルギー」だけは人よりぬきんでて燃えさかっており,エネルギーが余りすぎてオナホールを愛用しなければならない程なのである。
そのエネルギーを抱えた破門後のCHICAGOは,郷里・浜松からほど近い大都会・名古屋で噺家として生きていく決意をし,名古屋在住ただ一人のプロの噺家・雷門小福に入門を頼み込む。全くの偶然だが,東京で漫画もやっている噺家がいると聞くがそいつなら何とかなるかも,と小福が言ったこと(P.22)が決め手になり,その「漫画もやっている噺家」CHICAGOは新たに「雷門獅篭」として再生,潰れかけと言われて久しい大須演芸場を拠点に今日もしぶとく噺家として生きているのである。
モーニング連載時から今に至るまで,ハッキリ言って獅篭の漫画は絵が下手である。つーか,大してうまくなろうと思っていないことが見て取れる。「四コマはネタの切れ味とドライブ感が全て! 絵がうまくなっちゃったら元も子もない!」と割り切っているのかいないのか判然としないのだけれど,そう開き直っているとしか思えない進化のなさぶりなのである。しかしそれは絵についてのみ。獅篭の漫画には他の停滞した四コママンガ家にはない「魅力」があり,それは本書の前半の,特に絵が下手だった頃の作品に満ちているのだ。
実話をベースにたエッセイ漫画なので,ギャグはベタなモノが多いが,何と言えばいいのか・・・そう,ワシにとっては「共感できるもの」なのである。多分それはワシが普段から「生きるエネルギー」に渇望していて,それを発散している人物を好ましく感じるせいだろう。エリート街道まっしぐらの人生より,失敗だらけで七転八倒している様に感動するのがワシなのだ。故に,獅篭の漫画に対しては好悪の感想が相半ばするかもしれない。ぶんか社ということを差し引いても下世話なネタが多いから,上品な女性の方々にはお勧めしない方がよろしかろう。
ちょっと心配なのは,次第に獅篭の絵が整理されて見やすくなっているところ。特に最後のSCENE 17, 18辺りでは最初の頃の猥雑さがきれいに消えており,何としても笑って頂こうというサービスの度合いも低下しているように思えるところである。その分,本業の落語が面白くなっているといいのだが,ワシはまだ獅篭になってからの落語を聞いたことがないので何とも言えない。しかしblogを通じて知るところでは,結構あっちこっちの落語会に呼ばれたりしているようだから,それなりに腕は上がっていると信じたい。そのうち地元・浜松でもエンボスの社長のお眼鏡にかなって独演会が開催されるやもしれず,そうなれば本物になったと判断できるだろう。そこまで行けば,ワシとしては漫画がつまらなくなっても,十分に許すことができる。本書の印税がチェリーボムの支払いに回るだけでなく,多少なりとも芸の肥やしになることを念願してオナホールのゴムじゃなくこの記事を締めることにする。
[2009-09-28追記] 浜松にて獅篭の会が行われたので聞きに行った。なるほど,さすがしぶとく名古屋で噺家を精力的に続けているだけあって,段違いに腕を上げていた。ブレークするのも近い若手噺家期待の星であることを確信した。
カラスヤサトシ「おのぼり物語」竹書房
[ Amazon ] ISBN 978-4-8124-6873-9, \562
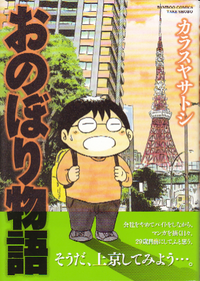
上京,という言葉を聞くと,条件反射的に胸の奥がちくりと痛む。
関東一円を「東京」と呼び慣わしてしまう程度に日本の首都から離れた地域に住む青二才が,「東京」に単身乗り込む理由は,就職だったり進学だったり,単なる親や故郷からの遁走だったりするが,さて,それから十数年経った後,「上京」という言葉に彼ら彼女らは一体何を感じるのだろうか?
サイバラの「上京ものがたり」,そしてカラスヤサトシの「おのぼり物語」は,多分,ちくりと痛むタイプの人間にしか描けないマンガだ。そして,整った絵を指向するマンガ家には描けない,自分の絵の下手さ加減を熟知し,結果として「やるせなさ」を抱えてしまっているマンガ家にしか描けないマンガなのだ。
カラスサトシを知ったのは月刊アフタヌーンの余白四コママンガである。そしてカラスヤがブレーク(という程ではないか?)するきっかけとなったのも,この余白マンガの持つ面白さであった。そこには「ダメダメな自分を笑って下さい」という,日本のエッセイマンガのステレオタイプを土台としつつも,自分独自の視点で些細なおかしみを提示するという,大受けはしないが時々気になるものが育っていったのである。その証拠に,カラスヤ以外にも多くの新人マンガ家が余白を埋めていたにも関わらず,次第にカラスヤの四コマが増殖していき,とうとう本誌本文の数ページを占拠するまでに成長(増長?),ついには単行本が出るに至ったのだ(2008年10月現在3巻も!)。それでいて絵の方は全然上達せず,カラスヤ独特の,へろへろな線で描かれた、愛想がこわばったような笑顔は本書においても変わっていない。しかしそれ故に,カラスヤのマンガからは遠藤淑子にも通じる叙情が醸し出されるようになっているのだ。
29歳,殆どフリーター状態のカラスヤが単身,大阪から東京へ乗り込んだのは,マンガ家になるためだった。その目的は,「カラスヤさんはこの先どんどん忙しくなりますよ」(P.132)という編集者の言葉で一応達成されたことが本書で示されている。それから殆ど間をおかず,生乾きのみっともなさを本人に執筆させ,一冊の単行本にまとめた竹書房の桐さんの慧眼はさすがである。恐らく,ワシのように「上京」→「チクリ」と来るタイプのオジサン・オバサン達に,本書は大いなる共感を持って迎えられるであろう。
サイバラの「上京ものがたり」は芸術的なまでに切なさを伴った一級品である。本書はもっとマイルドな二級品の切なさが詰まっているが故に,サイバラのものよりずっと広範囲に受け入れられる可能性を持っている・・・とワシは睨んでいるのだが,果たして竹書房は小学館以上の営業シフトを組んでいるのだろうか? 売れ行きが悪かったら,それはカラスヤのせいではない。あくまで営業努力の足りなさが原因と,ワシは断言しちゃうのである。
吾妻ひでお「うつうつひでお日記 その後」角川書店,DVD「らき☆すたOVA」角川書店
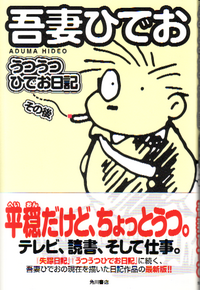
[ Amazon ] 「うつうつひでお日記 その後」ISBN 978-4-04-854246-3, \900

[ Amazon ] 「らき☆すたOVA」\5800
×月×日(△)
今年(2008年)に入って,少し鬱気味。最初はいつもの逃避行動かと思っていたのだが,本当にやる気が出ない。といって,危ない行動への衝動があるわけじゃなし,食欲が無いわけでもない(脂っこい物を食べなくなったぐらい)ので,「今年は鬱の年」と割り切って過ごすことにする。そーいや,吾妻ひでおも,アル中から立ち直ったと思ったら鬱になっちゃったんだよなぁ(「うつうつひでお日記」参照)。まあ,それまでの仕事量・稼ぎはダントツに先方が優れているので,比較しちゃ失礼な話ではある。
吾妻さん公式Webページの日記連載,毎月欠かさず読んでいるが,特に励まされるわけでもなし,といって絶望の淵に立たされることもなく,「ただ生きている」という日常が淡々とつづられている。鬱には励まし厳禁,とよく言われるが,具体的にどういう接し方をしたらいいのかは難題だった。そーか,こーゆー読み物を与えるのも手かな,と思った。少なくともワシにとっては薬とはいかないまでも,癒しにはなっている・・・かな?
□月○日(◎)
「らき☆すた」のOVAが9月に出るらしい。公式ホームページに告知が出ていた。かろうじて放送されていたラジオ番組も打ち切られたし,さすがに人気は落ちているだろうが,まだ元気な若者どもの固定客はある程度の量,存在していると見越しての発売か。興味が湧いたので,Amazonの予約ボタンをぽちっとなする。萌えアニメを買うのは,セラムン以来だなぁ~・・・って何年前だよ。
そーいや,「うつうつひでお日記」は,Comic新現実終了後,一時的にコンプティークに掲載されたことがあり,読者サービスも兼ねてか,コンプティーク連載陣の模写のカットが乗っていたりする。当然,らき☆すた原作者・美水かがみさんの模写もあって,茫洋としたみなみちゃんを選択していた。吾妻さんらしいな,と思った。
△月×日(□)
げげ,吾妻ひでおが倒れたか(P.40)。夜中にトイレに入ったら一瞬気絶して倒れたということらしい。幸い精密検査でも問題はなかったようだが,その後,吾妻ひでお死亡説が流れた(P.100)のも,これに尾ひれが付いて拡大されちゃったのかも。よくあるっちゃよくあることだが,「Comic リュウ」で毎回審査員しているんだし,ホントに死んだら大々的に告知されそうなもんである。
吾妻さんは元気です。ちょっとお痩せになったようだけど。
◇月●日(▽)
らき☆すた本編をYouTubeとニコニコ動画にてタダで見てしまった贖罪も兼ねて,角川グループホールディングス(GHD)の株を購入。買った後でアメリカの金融市場がおかしくなり,以来毎日,胃が痛い生活を送るハメになる。せめて配当と株主優待に期待して,自分を慰めるしかない。鬱なのに更に自分を追い込んで(しかも経済的に)どーするよ。
▲月◇日(×)
2社目の株主になる・・・バカだ,俺。ついでに言っておくと,今年中にもう2社の株主になる予定。バカの4乗ですね。いや,サイバラ先生のFX取引ほどではないけどさ。
Amazonから,クレジット情報が無効になっていると通知届く。放置しておくと発売日にらき☆すたOVAが届かなくなってしまう。大変だ!
引っ越した時のままにしていたのが原因だった。慌てて修正。あとは届くのを待つだけだ。
9月26日(金)
「らき☆すた OVA」届く。早速視聴。即感想。
1つ目・・・いつものらき☆すた。さすが原作者がシナリオを書いただけのことはある。
2つ目・・・オンラインゲーム用語,さっぱり理解できず。寄る年波を感じさせられる。
3つ目・・・みっくみっくにしてやんよ。かがみんに萌え~。
4つ目・・・ワシでも再放送しか見てないぞ,このアニメ。
5つ目・・・そうなんですか,そうなんです(年だから許されるよな,この程度は)
6つ目・・・いいのか角川,仮にも売れ筋の軍曹をこんな扱いして。視聴者としては面白いから許すけど,株主としては複雑だ。それにしても,みんな「ビューティフル・ドリーマー」好きだなぁ~。リアルタイムで映画館にて見た世代としては感慨に耽るのみ。
総論・・・次のOVAは・・・なさそな雰囲気。でもワシは出たら買います。あ,でも,株主優待でタダで貰えちゃったりして?
9月27日(土)
いきつけの本屋さんに「うつうつひでお日記 その後」が入ってますか~,と訊くべき所を「うつうつひでお日記DX」(文庫版)といいまつがってしまった。どっちにしろ,両方入荷してなかったからいいんだけどさ。
仕方がないので,ワシが唯一,掛川にてまともな大型書店と認定しているところへ4代目パルサーを駆って乗り付け,オレンジ色でない「うつうつひでお日記 その後」を入手できた。あ,やっぱWeb連載のまとめバージョンなのね。でもバックナンバーは消されちゃうし,資料としても貴重。書き足しもあるし。
改めてじっくり読んでみると,いしかわじゅん以上に辛辣な(=正直な)一言批評が多くて感心させられる。敵味方という区分を付けず,自分がどう思うかだけを綴るってのは,こーゆーことなんだな。故に,当たってると思うこと多し。
今の日本に漂う閉塞感が,吾妻ひでおの状態と重なることが多いってのは単なる偶然なんだろうか。もちろん,ワシの鬱状態は偶然以外の何者でもないのだけれど,この3者のシンクロ鬱状態,もうちっと面白がれないもんかなぁ。「楽しく過ごす鬱」・・・矛盾してますかね? 今の吾妻ひでおの状態はこれに近いモノが感じられるので,ワシも参考にして,日々鬱々と過ごすことにしようと思う。
9月28日(日)
らき☆すたOVAにくっついてきたBGM集(初回販売品限定)を聞きながら,さーて,いい年こいて萌えアニメを見ているというこっぱずかしい状況をどう誤魔化していこうかと思案。あっ,そうだ,萌えの元祖の日記とくっつけて書いちゃえばいいや,と閃く。まぜてしまえば分からない~・・・っと。で,吾妻ひでおを見習って,さらさらと架空日記も混ぜて書いてしまった。さーて,どんくらいフィクションが入っているのでしょうか? もう書いた人間も分からなくなっているのでありました。
中島らも「定本 啓蒙かまぼこ新聞」新潮文庫
[ Amazon ] ISBN 978-4-10-1166442-1, \438
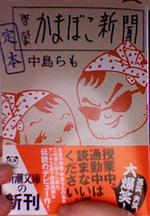
昔々,世間では泡(バブル)が大いに盛り上がっていた頃,首都圏の大学生どもは必ず小脇に「ぴあ」を抱えていたものである。その頃は「大学はレジャーランドである」という,日本の高度成長期に培われた良き常識が残っており,講義には出席していなくてもサークルの部室には必ず顔を出す,というのが普通の大学生のあり方であった。ワシもご多分に漏れずそのような大学生活を送っており,講義中こそ控えたものの,休み時間には必ず友人たちとカードゲームに勤しんでいたものである。教科書?予復習?なんだそれ?という感じであった。それが今ではグローバル化の大波に洗われて日本社会から余裕というものが失われ,「大学では勉強せよ」と世の親も教師も叫ぶようになってしまった。嘆かわしいことである。一体全体そーゆーことを言うお前らこそ,どんな大学生活を送っていたのかと小一時間問い詰めてやりたい。今の大学生諸君,反撃したいなら「バブルでGO!」は必見ですぜ。
さて,教科書よりも大事な「ぴあ」は,レジャーランドに通う若い頃のワシらにとって必須の情報ツールであった。世間で何が流行っているのか,どんなイベントがどこで行われているのか,それはすべて「ぴあ」に掲載されていた。いや,「ぴあ」に載っていないものは世の中には存在しないも同然だった,と言うべきなのかもしれない。今ではすっかり東京ウォーカーに部数で抜かれ,Webからキーワード一発でググるだけで済むようになってしまっているが,泡絶好調の時代はあの及川正通の精密な著名人の似顔絵を冠した紙の束が指し示す情報が,ワシらの大学生活の全てだったのだ。
そんな「ぴあ」だが,情報の狭間で密かに「サブカル」を育てていたのだ。「はみだしぴあ」という,記事ページの左右マージン部分に小さく縦長に印刷された小粋(死語)な文章。ワシはあれが大好きだった。そこでは常連も生まれ,号をまたいで密かなコミュニケーションも図られていたのだ。
そしてもう一つ,時期は判然としないのだが,大変に気になる,絵の下手なマンガがいつの間にやら掲載されるようになっていた。題して「微笑家族」。表情の全く変わらない,顔のコピーを貼り付けた,作画に関しては手抜きとしか言いようのない白黒1ページの地味なマンガで,その下には申し訳のように「カネテツデリカフーズ」の宣伝ページであることが分かる文章(といっても宣伝臭は皆無であったが)が付記されていた。
絵については褒めようのないマンガであったが,つい読まされてしまう不思議な磁力が働いていて,ワシはいつしか情報よりも「はみだしぴあ」とこのマンガを目当てにしてぴあを購入していたような気がする。例えて言うなら中崎タツヤやいましろたかしの描くダウナー系マンガの元祖のようなものであった。
それが「中島らも」との最初の出会いだった。たぶん,同じように中島らもとこの時期に出会った人は多いと思う。その証拠に,この啓蒙かまぼこ新聞は程なくして中島らもの著作としてまとめられ,今またこうして新潮文庫から編み直されて21世紀もしぶとく残っているのだから。ワシは広告の歴史にはトンと疎いのだが,中島らもは「自己表現としての広告」を開拓した先駆者に数えていいのではないかな。
その中島らもが52歳で,ほとんどアルコールに飲まれるようにしてこの世を去ったのはつい最近(2004年)のことだ。ニュースを聞いたワシは,驚くより「やっぱり」という感想を持った。それは周囲の人たちから断片的に伝わってくる情報や,らも自身が執筆したエッセイから知る普段の生活ぶりからして,遠からず破綻しそうな予感がしていたからである。ワシは中島らもの小説はほとんど読んでいないが,エッセイは「しりとりエッセイ」以来,特に1990年代に出版されたものはたいがい目を通している。そのエッセイの文体も,どんどん構成が「緩く」なっていき,晩年に近い時期のものは,正直言ってかなり密度が薄く感じられるようになっていた。これがアルコールの影響によるものか,意図的にやっていたものなのかは分からないが,少なくともワシが好きだった中島らもからはどんどん離れて行ってしまったのである。
本書を読んで,マンガの持つおもしろさは,馬鹿でバブリーな大学生だったワシが感じたものと変わらないことが分かった。純粋にダウナー的センスだけで勝負していたことで,20年以上も前の作品なのに全く古びていないのだ。しかしそこに添付された文章は,構成がかっちり決まった密度の濃い初期の中島らものエッセイそのもので,ワシは面白さよりノスタルジーを感じてしまい,少しほろりとしてしまったのである。
本書には,ワシの大好きだった中島らもが詰まっている。永久保存版として,大事にしていきたい。