どんよりどよどよな空。一時は雨も降ったらしいが,ワシは感知せず。よって本日は曇りの日とする。
日本の中部の亜熱帯,静岡県は今が温州ミカンの最盛期である。

我が家の冷蔵庫の野菜室は,名とは違ってミカンでいっぱいである。おかげで便通がいいのだが,ウンコが臭くなってしまうのが玉に瑕だ。ミカン果汁に含まれる何らかの成分が大量のアンモニアを生成する素になっているようなのだが,まあ全てにおいて良いことなぞないのが世の中だ。これから1月までは,タダでさえ黄色い肌が更に黄色くなった黄色中年が臭いウンコをムリムリとホキ出しつつ英気を養う季節なのである。
ぷちマネーの虎をやってみた。まーこーゆー投資には最悪の時期に,バカが一人ぐらいいてもよかろーて,っつーこってすな。但し,5年経って配当が出なかったら実名でボロクソ書く予定。投資っつっても無議決権株式な上に優先株でもないから,このぐらいのことはしても罰は当たるまい。そうならないよう,これから5年は気合いを入れて頑張って稼いでね>T君 あ,配当代わりの吉牛とラーメンはイヤだからね,最低でも銀座アスターのフルコースを奢んなさい。以上。
何やら仕事があれこれ入ってくる。12月の情報教育研究集会の原稿が受け付けられたと思ったら,次年度11月の研究発表が早くも決定。静岡に来てからはなるべく毎年1件は教育がらみの発表をするようにしていたが,次年度は2件になりそな気配。本来なら仕事の分野は絞るべきなのだろうが,体力があるうちは(40台前半ぐらい?)このまま鼻の穴尻の穴おっぴろげのまま突き進んでみたい。・・・朽ち果てたりして。
あとは今何とかなりそな反復改良法のネタがまとまるかどーかだな・・・今回のHOKKE2009はなんだか講演したけりゃメンドクサげな条件をクリアしないとダメらしいのだが,何とかなる・・・かな? ま,ダメもとで出してみよっと。
あ,査読依頼が来てたんだっけ・・・今回は(も?)来ないと思って安請け合いしたのがウンコのつき,もとい運のつきだったんだなぁ・・・ま,勉強しながら何とか次週中に読んでしまいましょう。勉強にもなるしね。
そろそろ地デジTVを我が家に導入したいなぁと思っているのだが,ついでに狭いディスプレイを交換したいので,三菱のこれとかIOデータのこれとかがいいかなぁ~と。まー先立つものがあるかどーかなんだが,ま,冬のコミケをパスすればなんとかなるっしょ。
つーことで,少し計算してから寝ます。ウンコはもう出しました。所詮,人間,糞袋ぉおおっとくりゃぁ。
10/22(水) 掛川->浜松->掛川・?
何か,10月も半ば過ぎだというのに日中はあっついなぁ。ホントに秋か? 今年の春,お掃除の神にムリヤリ買わされた羽毛布団をひっかぶって寝ようとすると,まだちっと暑くて,朝方の冷え込んだ頃にはすっかり蹴飛ばしてしまっていて,寝冷え状態で目が覚めてしまう。んっとに面倒な気温だこと。今年は台風も来ないようだし,その割には世界中で金融がダメになるし,せめて町山さんご推薦の「W」でも見て(日本公開はいつかな?),全ての元凶のお勉強でもして溜飲を下げるほか無いなぁ。
以前から,静岡大学での非常勤講義ってのはロクな目に遭わないのだが,今年はホントに酷い。今やっている講義は,ちょうど大規模改装工事中をやっている境目の教室,しかも滅茶苦茶狭い所を割り当てられて最悪である。今日なぞは,板書しているそのすぐ裏でバリバリでかい音立てられる始末。頭に来たので,工事現場のドアをけっ飛ばして「責任者出せぇ,おらぁ!」と文句を言ってやった・・・というのはちょっと誇張があるな。「マルサの女2」で,きたろう扮する地上げ屋のチンピラが,マンションの一般家庭のドアをドカドカぶん殴ってムリヤリ開けさせるやいなや,静かなドスのきいた声で「すいませんけど,お醤油貸してくれませんか?」と言う,あのシチュエーションを思い出して頂けるとピッタリである。で,人の良さそうな工事現場のアンちゃんにお願いして,少しはマシになった。
しかしまぁ,こういう教室を割り振られるってことはとっとと辞めてくれってことなんだよな。ワシはともかく,受講生にはいい迷惑だ。これでも必修科目だってぇから,国立大学が聞いて呆れる。何とかしてくれと事務局にねじ込んでも埒があかないし。
まあ次年度から当分は依頼もないだろうけど,暫くは駆け込みだろうがナンダロウが,絶対静大からの非常勤は引き受けないつもり。関係各位にはよろしくお願いしておく。
さて,風呂が沸いたのでゆっくり浸かって今日はもう寝ます。
「月刊Comicリュウ」2周年に寄せて
[ 公式サイト ]

2006年9月19日,徳間書店が青年漫画月刊誌「Comicリュウ」を創刊した。雑誌不況と言われるようになって久しい時代に,しかも月刊誌では採算が取れている雑誌の方が希有,という状況下でよくもまぁ出したモノだと感心させられた。
で,これ↓が創刊号の表紙である。
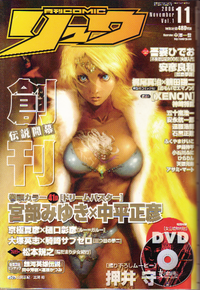
この時の主な執筆陣を挙げておく。(連)は連載,(シ)はシリーズ連載(不定期も含む),(読)は読み切りの意味。
(連)「ドリームバスター」宮部みゆき(原作),中平正彦(絵)
(連)「ルー=ガルー」京極夏彦(原作),樋口彰彦(絵)
(連)「ゆるユルにゃー!!」小石川ふに
(読)「HangII」遠藤浩輝
(読)「不条理日記2006」吾妻ひでお
(シ)「ちょいあ!」天蓬元帥
(連)「子はカスガイの甘納豆」伊藤伸平
(連)「おもいでエマノン」梶尾真治(原作),鶴田謙二(絵)
(シ)「麗島夢譚」安彦良和
(連)「MMリトルモーニング(後に「青空にとおく酒浸り」に改称)安永航一郎
(シ)「ネムルバカ」石黒正数
(連)「REVIVE!」五十嵐浩一
(シ)「木造迷宮」アサミ・マート
(連)「XENON」神崎将臣
このうち下線が付いているのは,2008年12月号においてもまだ連載が続いている作品である。創刊して後もまだ雑誌のカラーを決めかねている角川書店の「コミックチャージ」に比べると,創刊時における雑誌の性格付けが殆ど揺らいでいないことが分かる。創刊3号目において連載陣の一人・安永航一郎から「COMICリュウ,ついに3号ですね。いよいよ3号雑誌の本領発揮ですよ。」(最終ページ・著者コメント欄より)などと,激励なのか揶揄なのか判然としない文句を投げつけられたにもかかわらず,SFファンタジー色の強い,少年キャプテンとSFアドベンチャーの遺産を受け継いたこの雑誌は,どの程度の販売部数なのかは不明なれど,創刊一年目において中綴形式から平綴形式に移行し,ページ数も370ページから200ページも増加した。
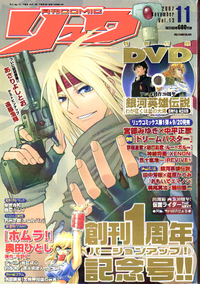
この時点で,いわゆる揶揄的な意味での「3号雑誌」は脱却したと見るべきだろう。雑誌単体で採算が取れているかどうかは疑問だが,連載作品のコミックス化が始まったのがこの時期からなので,ボチボチComicリュウ関係の売り上げから飯が食える程度にはなってきた,とワシは想像している。
連載陣のラインナップから想像するに,読者の主力は恐らく30~40台のオタク世代,もしくはオタク崩れのオヤジどもであろう。最新号にはちみもりおの短編集が付録として付いてきたが,収録された作品は,初出がないので断定は出来ないけれど,1980年代後半のロリコンブームの影響とおぼしき20年以上前のものばかりであった。ま,他にも付録として押井守の短編映画とか銀英伝とかが付いてくるぐらいだから,読者層については推して知るべしである。
そのようなオヤジ読者の経済力を背景にして勢いを得たのか,Comicリュウは旧キャプテン時代の作品をコミックスとして出版していくと同時に,新人発掘にも力を注ぐ。大野編集長はなるべく新人には執筆の場を与えるべきだという主義らしく,創作同人誌の古株・コミティアから即戦力として引っ張ってきた作家(アサミ・マート,坂木原レムなど)や,同誌が主催し,安彦良和・吾妻ひでおが審査員となっている龍神賞受賞者(いけ,大野ツトム,横尾公敏,平尾アウリ,山坂健)にもシリーズ連載や連載を持たせている。創刊2年目では更に100ページ以上もふくれているから,ちょうどその増加分を新人らで持たせているということになるようだ。

この調子ではまだまだComicリュウの快進撃は続きそうである。個人的には永遠の28歳・魔夜峰央のエッセイ漫画と,あさりよしとおの衣鉢(死んでないけど)を受け継いだかのような作風の大野ツトム「ネム×ダン」シリーズが好みなので,雑誌が潰れるまではお付き合いしたいと思っているのである。崩れ中年オタクどもの癒しとして,更に欲を言えば,次の世代のオタクどもを育成するためにも長く続いて欲しい雑誌,それがComicリュウなのである。
最後にComicリュウにまつわる謎とお願いを提示してこの記事を締めたい。
それは先にも名前を挙げた,安永航一郎の連載漫画「青空にとおく酒浸り」についてである。この作品,連載開始以来2年以上になろうというのに,そして一度たりとも連載が休みになったことがないというのに,未だコミックスが刊行されていないのである。人気がないとは思えない。ワシはいつもこの傍若無人な無軌道コメディを楽しみに読んでいるし,2008年10月号に掲載された「瀬戸内海の西の方のちょっと信じられないすごい話」という「フィクション」は,「フィクション」とはいえ身につまされながらも大いに笑ったマンガだった。「日本ふるさと沈没」において没にされたという幻の「竹島沈没マンガ」を彷彿とさせる程の大傑作だったのだ。
そのような傑作マンガなのに,何故この作品だけがコミックスになっていないのか?・・・ま,理由は100%作者にあるんでしょーけどね。同情しますよ,編集部には。
しかぁあし!,ワシとしては是非とも,Comicリュウ休刊までに安永先生のコミックスを出して頂きたいのだ。伏して編集部のご尽力と,瀬戸内海の西の方におわすマンガ家先生にお願い申し上げる次第である。
小谷野敦「日本の歴代権力者」幻冬舎新書
[ Amazon ] ISBN 978-4-344-98092-1, \840
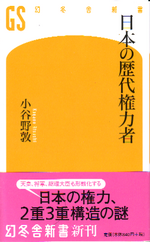
老境を迎えた学者が行う仕事はいろいろだが,学者生活の総決算を飾ろうという意図がある場合は
・自分の研究内容及びその周辺内容を含めた学問の歴史の記述
・長い研究生活を送るうちに蓄えた知識をまとめたデータベース的書物の執筆
つーのが普通のようである。「いやワシはまだ現役学者であるからして,コンテンポラリーな潮流を意識した研究に邁進するのだ!」というのもアリかと思うが,いくら何でも70歳を超えたら,少しは後進のために上記のような仕事をして欲しいよなぁと思う。ハッキリ言って老醜じゃねーか?と思える言動を取る老大家を見るに付け,ワシ自身は引退後に「学問の歴史」と「データベース」が執筆できるだけの知的蓄積を今からしておきたいなぁと思う。そうすりゃ,少しは人類の知的蓄積になにがしかの貢献ができるかもしれないし,多少の人格的障害があっても,世間のお目こぼしに預かれるだろうと期待しているのである。自分の年金支給額ばっかり気にしてヤイノヤイノ言う年寄りには正直,ウンザリさせられているのだ。
上記のうち,今のワシが読み物として好むのは「データベース」の方である。「学問の歴史」はワシが引退する20数年後までどんな変化をするのか予測不可能だから,現時点のそれを知っていてもあんまし実がないよーな気がするのだ。が,データベースなら,今のバカなワシが持っていない知識を仕入れることができそーだし,何より自分がそのうち書くかもしれないデータベースの一部に取り込むことができそーじゃないですか。何?それは剽窃であって,唐沢俊一みたいだってか? なーに,「嘘つき」よりも「ドロボー」と言われた方が,内容の信憑性にはお墨付きが付いたよーなもんなので,いいんです。大体引用元さえキッチリしていれば,自分の創作的寄与ゼロのデータベースであっても著作権がちゃーんと発生するのであるからして,立派な自分の仕事になるんであーる。・・・ま,そんな立派なものが引退後のヨボヨボジジイに完成できるかどーかは分かりませんが,ね。
で,最近だと「データベース」もコンパクトなものが好まれるのか,新書サイズのものが増えているようだ。例えば科学史家の小山慶太は「科学史年表」を中公新書で著しているし,ワシが複素関数論を習った井上正雄先生は「簡明 微分積分ハンドブック」(聖文社)を250ページ程度の新書版で出した。どっちも本来なら千ページを超える内容になりそうなものを,ペーパーバックサイズにまとめ,しかも読みやすさを求めてシンプルな文章と版組にしてある。「太い本を書きたい」というのは物書き共通の欲望だと中島らもは書いていたが,その欲望をあえて抑えているところがいいなぁ,とワシは思っているのである。
で,小谷野敦先生である。ワシより7つ上だから,まだ40代後半なんだよなぁ。それでいて今回「日本の歴代権力者」なるコンパクトなデータベースを著しちゃうというのはちと気が早いのではないか。いや,面白かったからいいんですけど,なーんか「人生のまとめ」に入っちゃったのかなぁという感じがして,愛読者としては少し寂しい・・・というのは考え過ぎか? 死なないで~,小谷野センセー(当分死にそうにないけど)。
小谷野先生は幻冬舎新書からは既に「日本の有名一族」を著しているけど,前にも書いた通り,著名人・政治家・学者の系図をまとめたものがWebページとして存在しているを知っていたので,ワシはあまり感心しなかった。ま,紙媒体で残っていた方が資料として便利なのでワシは買ったし一応読んだけど,うーん・・・下世話な本だというのが正直な感想であった。いや,品性が下世話なワシとか福満しげゆきのような人間にとっては「なーんだ,あいつもあいつもあいつもあいつも,ぜーんぶ係累がらみで出世したのか」という溜飲を下げる効能はあるので,その意味では読み物としては「あり」なのだが,一応,学者の看板を上げて商売をしている小谷野敦の著作としては「いいのか?」という気分がワシには残ったのである。
しかしこの「日本の歴代権力者」は,まともな学者の仕事の醍醐味を知らしめてくれる良書なのである。ワシが日本史の知識に疎いこともあって,それを補ってくれる記述が多い上に,大量の文献を渉猟した結果だろうが,「へ~,あの常識はまだ学問的に決着が付いてないものだったのか」という目から鱗の指摘が多く,二重に感心させられたのである。やっぱ東大出を標榜するならこんくらいの仕事はしてくれないと,ねぇ?
本書で言うところの「権力者」は,もちろん天皇ではない。本書の記述は蘇我氏から始まっていて,既に天皇は傀儡の扱いである。その後も,藤原氏による摂関政治,武家による鎌倉幕府と同様の扱いを受け続け,一時は後醍醐天皇が権力者として復活しようとするも挫折,以降も室町幕府,織豊時代を経て徳川幕府,明治維新,現在に至るまで,天皇は権力者に権威を付与するローマ法王的な役割(巻末に論考がある)を果たす存在になっていく。だから本書で言う「権力者」とは,その時代毎に,本当の権力を握っていた人物であり,それが判然としない時代には複数の人物が挙げられたりする。例えば,室町幕府創設時には足利尊氏・直義・高師直の三人が,戦前期には首相と共に内大臣・木戸孝一も挙げられている。この辺り,取り上げる人物は「恣意的のそしりを免れない」(P.4)と小谷野も認めている通りで,歴史にうるさいオヤジ連中の「あいつがいるのに何でコイツがいないのだ!」とゆー議論を巻き起こす可能性が高い。ま,それもまた本書の楽しみ方の一つである訳で,一人当たり1~3ページ程度とコンパクトにまとめられた記述には無駄がなく覚えやすいので,床屋談義のネタとしても有用である。
それにしても40台でこの著作かよ・・・と思ってしまう。いや,売れそうだから書いた,というのは本音としても,エライ手間と時間がかかっているんじゃないかと思うと,ホントに元が取れるんだろうか? 大体,こんなに知識を仕入れちゃったら,後は死ぬだけなんじゃないかと,愛読者としては心配になってしまう。老境に達する前に書いちゃったコンパクトなデータベース本を土台に,これから先の小谷野先生のお仕事がどのように飛躍するのか,はたまた・・・となってしまうのか,ちと心配な今日この頃であります。
10/17(金) 掛川・?
あー・・・しんどかった一週間も何とか終わった。本日先程よーやっと情報教育研究集会の講演予稿を仕上げて(でっち上げて?)送付。PDFファイルをWeb経由でうpするのだが,昨年度はやたらめったらフォント埋め込みチェックが厳しくて,dvipdfmxでダイレクトに作ったPDFファイルが散々蹴られて焦りまくったモンだが,今年はあっさりおっけ。大分システムが改善された模様。広大情報メディア教育研究センターの皆様方のご尽力のタマモノか。
それにしても,書き慣れない内容を締め切り日当日に書こうとするものではないな。次年度はもう少し余裕を持って書きたいモノである。
世界同時金融恐慌の事態は避けられたようだが,アイスランドはロシアに助けてコールを出すハメになっちゃったらしい。アイスランドの経済なんてどーなっていたのかさっぱりわからんかったからな。これで少しは理解が進んだ・・・かな?
反面,日本は既に金融危機を経験しているせいか,銀行の再編は進んでいたし,危ない商品に手を出すこともしていなかったので,比較的ノンビリしていたようだ。オマケにぶっつぶれたりつぶれかけのアメリカの金融関係会社を買い取っちゃったりして,漁夫の利をかっさらう側に立てた訳だが,浮かれるのはちと違うぞ,という記事があった。
日本の財政幹部はもっと率直にこう認めた。「賢明だったというよりは、運が良かったのだ」と。
まあそーゆーこっちゃね。でも運が悪いよりは良いに決まっているわけで。塞翁が馬,でしょうかね。
ちょろっと計算して寝ます。