2,3年生ガイダンス。良い天気なれど,気温少し低め。桜はかなり散ってしまった。
CG教材,順調に推移。後はどう組み合わせていくか,というところ。土日で何とかなるだろう。
某国際学会と,某シンポジウムのメールやり取りが頻繁。特に前者は何だか凄いことになっている。うーん,お世話役は大変である。
某査読,締め切りすぎて催促メールが届く。すいませーん,明日には何とか・・・。
うーん,本が溜まってしまった・・・。こりゃ,連休中にまとめて消化かな?
お,SmithField搭載初製品はDellから(PC Watch)。しかし,About $3Kか,高いなぁ。
出荷は数週間後,というから,今月末か来月初めにはCPU単体でも発売開始になるんだろうな。しかし,出始めは高そうだし,Chipsetのbugも心配だし,そろそろATXのケースを買うのも避けたいし,当分は様子を見た方がよさそうだな。講義終了まで時間も取れそうも無いし,人柱さんたちの報告を待つとしますか。
新学期開始までカウントダウン。英気を絶やさぬように,早めに寝ます。
4/9(土) 掛川->浜松->掛川・晴
CGに勤しむ予定が,やった仕事と言えば「今年はCGをやります」と休日出勤中のN先生にメールを送った程度。完全に休養日になってしまった。ま,いいや。
午前中は余った回数券を使うため浜松へ出向き,増えすぎたサーバに取り付けるためのHappy Hacking Keyboardを買うべくCompuMartへ。が,肝心の物は無く,程よいキータッチの省スペースタイプはUSBキーボードだけ。結局,自宅で使う光学式マウス用のパッドを買い,谷島屋で夢路行全集16~18を仕入れて昼飯を食って戻ってきた。
後は食料品の買い込みをして,惰眠を貪るのみ。あーいーな,こーゆー日も。その分,明日はてんてこ舞いだが。
寝ます。
4/8(金) 掛川・晴
良い天気。気温もかなり上昇し,数年ぶりに徒歩で出勤したら汗でぐしょぐしょ。桜もほぼ満開。講義が始まる次週には散り始めそうである。
誤って24000を自分で踏んでしまった。
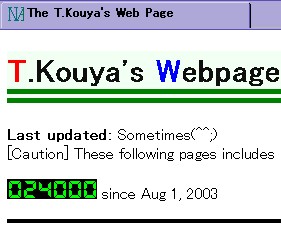
Webページ移動後2年でこの数字は,まあ多い方ではないな。ボチボチやっていきましょうぞ。
予定通り,数値計算のテキスト執筆。本日第3章完了。予定通り行けば,6月半ばには下書きを終えて,7月中には完成するものと思われる。・・・でも予定通り言ったためしがないからなぁ。どーなることやら。
cs-pccluster,cs-pccluster2共々,無事動いている模様。このまま7月まで過ぎてほしいなぁ。
明日はCG教材作りの予定。
寝ます。
4/7(木) 掛川・雨後曇
本格的に暖かくなってきた。おかげでcs-pccluster2ルームは早くも冷房モード。今年は昨年度のような酷暑にならなければ良いが。
職場に着いてから「今日は何をやるんだっけ?」と健忘症に罹患する。で,このblogを見て「ああそうだった」と納得する。うーん,Webってのは広大な私的メモの博覧会場(しかも検索機能つき)なんだな,と感じる。
Mesa3Dはapt-get install Mesa-devel; apt-get install glut-develであっさりインストール完了。3D CGも難なく動作する。さて,後は教材作り・・・と。元ネタ本は「OpenGLによる3次元CGプログラミング」(コロナ社)なんだが,ちーっとネタが地味である。といってこちとらCG初体験者なので,そうそうすっばらしいモンを作れるわけがない。まあ今年は慣らし運転がてら,ボチボチやる予定。
cs-pcclusterの方はすっきりケーブル配線をして,NIS, NFSの設定終了。MPICHの設定は時間が出来てからだな。Quotaの設定をやりかけたところで帰宅。まあまあ予定通り。
と,順調に通常業務をこなしつつあるのだが,名前だけ事務局員として連ねている国際研究会の方は何やら切羽詰っているらしい。とは言え,個人で何か出来るレベルの話ではないので,きちんと割増料金(割引の間違いに非ず)でRegistして,Projectorを貸し出す手続きを取るぐらいのことしか出来ない。大変なんだろうな~,と洞ヶ峠を決め込む春雨の日なのであった。まああと一月ちょっとの辛抱だし。
明日は数値計算テキスト執筆の後,会議に出席して帰宅予定。土日はCG三昧かなぁ。
寝ます。
4/6(水) 掛川・晴
入学式。前も後もずーっとcs-pccluster2の再構築。HDDの換装用安物Removable Caseの接触が悪いのと,余計なジャンパをHDDに付けていたのが重なって,サーバのセットアップを2回もやり直す羽目になった。これで動作が安定してくれれば,今年一年は何とかなるだろう。
結局,mpich-1.2.6をインストールして環境構築したところまでは出来た。これで今月後半は自分の研究が出来そうである。しかし,mpich2はmpdの起動がトラぶって動作できず。rsh経由で呼び出しているのが悪いのかなぁ。5台までは無事起動するんだが,それ以上になるとお釈迦になる。まあ,mpich2にしたところで劇的な速度改善があるわけでもないんだろうけど,ちょっと悔しいぞ。時間が出来たら再チャレンジしてみよう。
明日は学生実験の準備と,cs-pcclusterのセットアップ。土日で学生実験の資料作りを終わらせて,いよいよ新年度のお仕事が始まるのであった。
ふーん,SUSEは1.2万円か(PC Watch)。Vine 3.1で不満があるとすれば,日本語フォントの漢字だけなんだが,そのために万単位でお金を払うのもなぁ。それに一旦買ってしまうと,一年に一度の再インストールなんてもったいないこと出来ないもんなぁ。
Adobe Acrobat 7.0 Elementsは5千円台(PC Watch)。いきなりPDF対策なんだろうな。競争がないと消費者は搾取される一方。家で使う分にはこれで十分である。安くなるのはめでたい。
明日のために寝ます。