[ Amazon ] ISBN 978-4-09-185317-2, \800
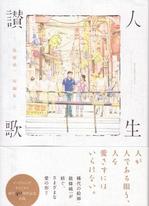
大御所過ぎて語るのもはばかれる雰囲気のある能條純一であるが,折角読みやすい短編集を出してくれたのだから,この機会に言いたいことは言っておくべきと考えて取り上げることにする。
小川隆章「アンモの地球生命誌」双葉社
[ Amazon ] ISBN 978-4-575-30548-7, \1000
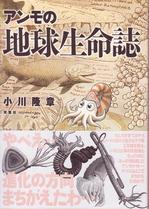
本書がどーいう文脈で双葉社から出版されたのか,ワシはさっぱり分からないのだが,夏休みの読書感想文のネタに困った時に役立ちそうなものとして本書を推薦したい,つまらん科学書より面白い漫画を読んだ方が何倍も勉強になる,ということはワシの40年以上に渡る読書遍歴によって証明(?)されている訳だが,本書に関しては,題材もさることながら,純粋に漫画として大変面白いのだ。躍動感のある古代生物描写は深海生物に胸ときめかせているガキどもにも面白がって貰えること間違いないのである。
久世番子「パレス・メイヂ 1巻」白泉社
[ Amazon ] ISBN 978-4-592-19404-0, \429
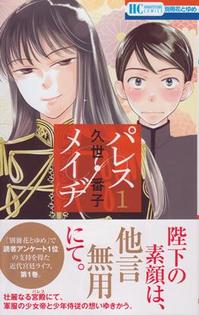
エッセイ漫画の名手,久世番子が少女漫画「コミックス」を出すとは,時代も変わったものである。別冊花とゆめで連載が始まったと知った時には意外だなぁと少し驚いたのだが,今回単行本として纏まったものを読むと,不思議なほど違和感がない。勿論,ワシがスレッカラシの中年漫画読みであることの影響も大きいのだろうが,本作は至極まっとうな「純粋少女漫画」であると感じたのである。それはいわゆる「王宮もの」(今ワシが勝手に作ったジャンルだ)に分類される「(初期の)パタリロ」や「大奥」が純然たる少女漫画であるのと同様,本作は間違いなく少女の夢・ファンタジーを描く作品となっているからである。
私屋カヲル「こどものじかん 13巻(最終巻)」「こどものじかん ほうかご」双葉社
「こどものじかん 13巻」[ Amazon ] ISBN 978-4-575-84246-3, \600
「こどものじかん ほうかご」[ Amazon ] ISBN 978-4-575-84247-0, \600
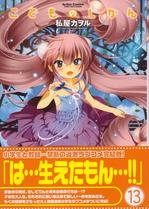
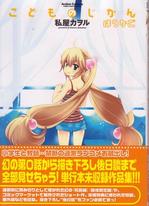
私屋カヲルについては一度は言及しておく必要があると思っていたのであるが,ついぞ述べる機会を逸していた。それは面白い近作を見逃し続けていた(あまり面白くない凡作は読んだ)という理由による。ここはやはりここ一番のヒット作である「こどものじかん」を読むしかないな,と思っていたところで最新刊・最終巻が発売されたので,一気に読んだのである。で・・・さすがだなぁ,と思うと同時に,これをやり玉に挙げて児童ポルノ法案に漫画・アニメ表現規制も盛り込もうという向きは少し考え直した方がいいのではないかと助言したくなったのである。
ということを書くと,お前は表現規制派なのかと言われそうだが,個人的には逆であるつもりだ。ただ両者の間のブリッジはもう少し広くして,規制したい方々の「嫌悪感」と,規制したことによる弊害,いやそれ以前に,規制することの「非合理性」についてガチで議論を深めてほしいと願っている。ま,ガチガチの規制派・規制反対派の方々にとってはどっちつかずのコウモリ野郎ということになるのだろうが,それはそれで正しい認識である。ワシはコティさんよろしく,世間の風向きというものにも一定の合理性は認める人間なので,どっちに転ぶのか,その原因たる社会的背景の方を注視していたいのである。
で,私屋カヲルである。デビュー時にはダッサイ絵だなぁと一顧だにしなかった漫画家が,気が付くと萌え萌えの画風となり,あれよあれよという間に「こどものじかん」で大ヒットを飛ばすまでに成長するなどとは露程も思わなかった。ワシは全く見る目のない一読者であるなぁと今大いに反省しているのである。
いつぞや,Twitter上では結城焔と私屋カヲルとのバトル(という程でもなかったが)が話題になった。第三者が読めば,私屋の本作が「あざといエロ釣り」であり,それ故に結城作品も載っている掲載雑誌が一般書店に流れづらく,結果として売れていない,という批判が発端となったバトルである。これをつらつら読むと,結城の最初の発言は相当言いがかりである。では振り返って私屋カヲルの本作が「あざといエロ釣り」ではないのかと言われれば,大方の人々は肯定せざるを得ないのではないかと思うのである。断言すると,ストーリーではなく絵面の表面だけ見れば,「あざといエロ釣り」という表現は当たっているのである。そしてここからが重要な論点になるのだが,では「あざといエロ釣り」というものが誰にでも描けるのか,そして大多数が認める「あざといエロ」というものに対して同じく大多数が納得する合理性を伴った規制というものが可能なのかどうか,折角本作という成人漫画規制の枠外の「具体例」があるのだから,大いに議論してほしいと思っているのである。そしてその議論の結果,ジャパンクールにおける「あざといエロ」の重要度が認識されるのではないかとワシは考えているのである。
本作の主人公・九重は,担任の教師・青木に恋する小6生だ。それだけならいいのだが,その好意の寄せ方は相当エロく,直接的なものである。この辺りが一部のお固い向きから憤激を買うんだろうが,そこを私屋は「都条例をクリア」する表現で,最大限の効果を得るべく描いているのである。この辺の見せるテクニックは非常に巧みで,萌えの極地のような絵柄と名人芸レベルに達した構成で読者を引きつける。「あざとい」と形容するのがピッタリだ。そしてこのあざとさが,都条例をクリアしているにも関わらず,憤激を買う原因になっている。これに規制の網をかぶせようとすると,もっとぼんやりとしたシチュエーションを規定せねばならず,現在問題なしと見られている他作品への影響が大きすぎるということになる。そこがまた規制派の方々のイライラを募らせている原因なのかなぁと想像するのである。
本作がエロいというのは正しいが,それがエロいのは基準をクリアした表現の巧みさに起因するものであって,私屋カヲルと同レベルの表現力がなければ成し得ない。それ故に本作を規制のターゲットとするのは問題が多すぎる,というのがワシの意見である。大体,ストーリー的には面白く真面目な性教育読本とも解釈できる内容になっているんだし。
・・・しかし規制派の意見にはあまり合理性がないとはいえ,政治的動向によっては「ぼんやりしたシチュエーション」での規制がかかり,最低でも現状以上に厳しいゾーニングを余儀なくされるかもしれない。そうなれば本作も同時発売された「こどものじかん ほうかご」も成人向け作品にカテゴライズされてしまう可能性がある。
だが,私屋カヲルの成り上がりっぷりを見る限り,どんな規制がかかろうと,そういうものはラクラクと踏み越えてしまうだろう。エロ抜きであっても面白いストーリー展開という武器を,私屋はすっかり自家薬籠中のものとしているのだ。規制を逆手に取った漫画作品を生み出して読者の支持を得ること間違いないのである。
森達也「死刑」角川文庫
[ Amazon ] ISBN 978-4-04-100881-2, ¥705
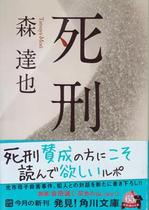
森達也の本を読むのは初めてである。聖人君子のようでもあり,人生に疲れたオッサンのようでもある風采の上がらないジャーナリスト(ドキュメンタリー監督と言うべきかな)は,メディアに現れた時には朴訥な口調で分かったような分からないような要領の得ない議論を口にする。しかしその内容に疑うところはあまりなく,むしろ,正論とされる多種多様な意見を誠実にまとめあげた結果,本人なりにはアウフヘーベンしたものがあの「要領の得ない議論的意見」なんだろうと推察する。
本書もそんな著者の誠実さが現れまくった一冊である。しかし,読み終えてからは,著者のやけにきっぱりとした態度表明とは別に,とてもメンドクサイものを読者であるワシに押し付けたのである。そういうものを嫌う向きにはお勧めしない一冊だ。
本書を端的に物語る著者の言葉を以下に紹介しておこう(P.249)。
死刑をめぐるロードムービー。まだ取材を始める前に鈴木久仁子(注・担当編集者)から本のイメージを訊ねられたとき,僕はそう答えたことがある。ならばあらゆる場所に行かねばならない。そこで僕は様々な人に出会い,様々な死刑を目撃する。
実際,本書では,死刑をテーマとした作品を描いた漫画家,死刑執行所を持つ拘置所の所長,死刑廃止を求める国会議員,かつて死刑囚だった人,死刑の場に立ち会った検事・教誨師・拘置所員,死刑判決を求めている被害者家族,死刑判決を求めない被害者家族,かつて死刑廃止を主張していたジャーナリスト,そして死刑判決を受けるかもしれない被告人を弁護する弁護士とコミュニケーションを重ねていく。重ねすぎて目眩がしてくるぐらいだ。そしてその濃密な情報交換の積み重ねを,ワシら読者は風采の上がらぬオッサンと共に追体験していくのである。テーマは一つ,「あなたは死刑存続(存置)を望みますか?」である。
よくある死刑存続の主張,死刑廃止の主張を押し付けるようなことを,森は絶対に行わない。あくまで態度は「あなたの意見はどうですか?」である。インタビューした相手に対しても,ワシら読者に対しても。それ故に,よくある自己主張の賛成を求めるだけの書物とは違うモノをワシらに突きつけ,メンドクサイものを残していくのだ。「あなたの意見はどうですか?」,と。
国際的な趨勢と,学術的な知見をふまえる限り,死刑存続派の理論的主張はほぼ成立しない。しかしそれでも本書に登場するかなり多くの,しかも実際に死刑に向き合わざるを得なかった死刑廃止派のジャーナリストや人権派弁護士ですら,死刑廃止を主張できなくなっているという現実を本書は突きつけている。「(死刑廃止の)理屈はその通り,だが・・・」と語尾が濁り,割り切れないものを抱えて葛藤している様は,本書を読み終えた,死刑存続を望む多数の読者にも同じことを要求してくるのである。
「死刑」という重苦しいテーマにも関わらず,森達也の筆は読者の視線を引きつけてやまない。それは淡々と事実を綴る誠実なドキュメンタリーを撮り続けてきた著者の誠実さと作家としての力量の所以であろう。死刑に賛成でも反対でも,真剣に議論したいのであれば,その議論の俯瞰図を知るべく,本書は最良の一冊となること間違いないのである。