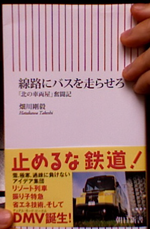台風が近づいているらしいが,まだ太平洋高気圧の勢力が強いので,小笠原辺りを迷走しているようである。それでも今週末には東海から関東に上陸しそう。え〜っ,日曜にはマンションの見学会があるってのに(やっと2階の床を作るらしい・・・(号泣)),無事見られるのかしらん?
GMP Version 4.2.2のRC3が出たので,UNIX Note PCでコンパイルテスト。おおっ,Core 2 Duo向けのアセンブラコードが出たか。でもコンパイルはコケてしまう。
$ make check
make check-recursive
Making check in tests
Making check in .
make libtests.la t-bswap t-constants t-count_zeros t-gmpmax t-hightomask t-modlinv t-popc t-parity t-sub
/bin/sh ../libtool –mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c -o memory.lo memory.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c memory.c -o memory.o
/bin/sh ../libtool –mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c -o misc.lo misc.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c misc.c -o misc.o
/bin/sh ../libtool –mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c -o refmpf.lo refmpf.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c refmpf.c -o refmpf.o
/bin/sh ../libtool –mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c -o refmpn.lo refmpn.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c refmpn.c -o refmpn.o
/bin/sh ../libtool –mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c -o refmpq.lo refmpq.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c refmpq.c -o refmpq.o
/bin/sh ../libtool –mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c -o refmpz.lo refmpz.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c refmpz.c -o refmpz.o
/bin/sh ../libtool –mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c -o spinner.lo spinner.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c spinner.c -o spinner.o
/bin/sh ../libtool –mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c -o trace.lo trace.c
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 -c trace.c -o trace.o
/bin/sh ../libtool –mode=compile –tag=CC ../mpn/m4-ccas –m4=”m4″ gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8test -f 'amd64call.asm' || echo './'amd64call.asm
../mpn/m4-ccas –m4=m4 gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 amd64call.asm -o amd64call.o
m4 -DHAVE_CONFIG_H amd64call.asm >tmp-amd64call.s
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I.. -O2 -m64 -mtune=k8 tmp-amd64call.s -o amd64call.o
tmp-amd64call.s:92:32-bit absolute addressing is not supported for x86-64
as: fatal error in /usr/libexec/gcc/darwin/x86_64/as
make[4]: *** [amd64call.lo] Error 1
make[3]: *** [check-am] Error 2
make[2]: *** [check-recursive] Error 1
make[1]: *** [check-recursive] Error 1
make: *** [check] Error 2
うーん残念無念。x86_64アセンブラ部分を弄くる力量はないので,もうちっと改善されることを望むしかないなぁ。Do you know who can modify to be able to compile new gmp in our Mac OS X with gcc ?
良い記事。教育の原点だね。中学校でこういう指導を受けることが出来,逃げ出さずに「勉強する態度」を身につけることができたこのA男君は幸運だね。知的に障害がない平均的なIQを持った若い人間なら,この態度を身につけていればそこそこ出来るようになるモンである。たいていの場合,「できない」のは能力の問題ではなく,態度の方にあるんだよなぁ。
ジャンジャンバリバリ,サーチエンジン本を書いている・・・つもりでございますが,書いても書いてもも終わりませぬ。つーか,書けば書く程,「あれが足りないこれも足りない」状態になって,分量が増える一方。どーすりゃいいんだ,全く。
書くだけ書いて寝ます。