[ BK1 | Amazon ] ISBN 4-86167-146-9, \857
アマゾンの書評を見る限り(2007年3月16日(金) 20:29時点),本書に対する評価はまっぷたつに分かれている。支持する向きは本書が「Google八分」なるものを公の場にさらしたことを評価し,そうでない向きは著者の一方的な感想を書き連ねただけの本だと批判する。
ワシの結論は,
ということに尽きる。本書を読むことなしに「Google八分問題」を語ることは,他に類書が少ない今の時点では片手落ちと言わざるを得ない。しかし,本書の言い分だけで「Google八分問題」を結論づけてしまうのもまた片手落ち,なのだ。
著者は,その筋では有名なサイトである「悪徳商法?マニアックス」を主催する管理人beyond氏である。サイトの文面や本書の記述を読む限り,飄々とした2ちゃんねるのひろゆき氏とは正反対の熱血漢とお見受けする。そして,詐欺的な商売をする輩を糾弾する姿勢,度重なる圧力や抗議にもめげず,サイトを維持し続けている姿勢は尊敬に値すると,これはイヤミでもなく褒め殺しでもなく,そう感じる。
そして,本書を書くきっかけとなったGoogle八分は,この著者のサイトの情報に関連して起こったものであった。実際,「悪徳商法?マニアックス」でGoogleると今でも(2006年3月16日(金)現在),削除された情報がある旨が検索結果の下に表示される。どうも,著者のサイトにある某詐欺的商法の情報に対して抗議を受けた事による「Google八分」であるらしい。
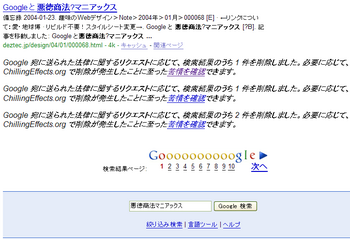
著者はGoogle日本法人への問い合わせを行い,名誉毀損の疑いありと判断されてしまったことを確認したが,どのように該当ページを修正すれば再掲載されるのかを問うてもはかばかしい返事は得られない。佐々木俊尚氏がこの件に関してGoogleにインタビューを行った結果,Googleとしても判断を迷った削除であることは判明したものの,上記のように,今現在もGoogle八分状態は変わっていないのである。
本書にはそれ以外のGoogle八分事件が紹介されているが,中国政府による検閲・朝日新聞による削除養成に関する報告を除けば,大部分のGoogle八分の事例は「悪徳商法?」に関連している事例である。それに気が付いたあたりから,ワシは「これは・・・自分の受けた被害を肯定する資料を積み重ねるだけの本か?」という疑念がついて回り,本書のタイトルから受けていた「Google八分問題を総合的視点から議論する書」というイメージがガラガラと崩れるのを感じたのである。
従って,
という印象を受けた読者が批判的な書評をするのは,至極自然な成り行きなのである。
第4章の「グーグル八分と表現の自由」では,弁護士と図書館協会の方にインタビューを行っているが,ここが本書で最も議論が開かれている部分である。ここがなければワシは本書を「Google八分が理解できる本」として紹介することはなかった。そして,このお二人の話を総合して
・Google八分の問題は,そもそもサーチエンジン市場におけるGoogleの占有率が高いことに起因している
・Googleは情報を削除する基準が曖昧であり,それ故に「表現の自由」を犯す危険が高い
・Google八分そのものが悪いというのではないが,可能な限り,情報は検索・閲覧できるようにしておくべきである
という,かなり多くの賛同を得られるであろう主張を取り出すことができるのである。逆に言えば,この辺を立脚点にして議論を進めていけば,Amazonの書評のように評価が分かれる本にはならなかったのではないか。更に逆に言えば,このような客観的な視点が少ないということが,本書の一番の特徴であり,好き嫌いの別れるところなのであろう。
個人的には,「そもそも何でGoogleだけが情報削除を叩かれるのか?」という疑問が拭えないのだ。それを言い始めると,Yahoo!のカテゴリに自分のサイトが登録されないなんてことは日常茶飯事なのに,何で問題にならないの?,という反論がされるに決まっている。実際,前述の最初の論点に挙げたように,確かにGoogleのシェアは高くなってはいるが,アメリカでも約47%,日本ではトップがYahoo! Japanの約62%で,Googleは本家とあわせても28%に過ぎないという調査結果がある。現状,日本では,ことさらGoogleの「八分」だけを問題視する客観的理由は薄弱なのである。中国の有力サーチエンジン「百度」が近々日本にも上陸するらしいから,今のうちに独占禁止法的な枠組みを議論しておく必要はあろうが,基本的には私企業に対して,商売を度外視して「表現の自由の番人たれ!」とせっつく主張がどこまで強制力を持っていいのか,ワシにはよく分からない。
してみれば,本書はやはり自分のサイトがGoogle八分されたことによる「私憤」をぶちまくための場なのであろう。しかし,全ての「公憤」は,「私憤」を種として発芽し,そこに第三者の共感を得て育っていくものである。本書は,かなりひん曲がっちゃってはいるものの,第4章の助力も得て,私憤が育った苗にはなり得ている。これがそのうち巨大な,それこそクローバルスタンダードとしての公憤の大木に育っていくのか,それとも著者個人とその周辺だけの私憤として収束していくのかは,ワシにはこれもよく分からない。
しかし,今のサーチエンジンの周辺事情に興味のある向きは,必ず読んで,手元に置いておく必要があるだろう。そして,年月が経過した後,再び本書を紐解いて,著者の主張がどのような結果に結実しているかを確認すべきである。世の中には時間でしか解決できない物事が山ほどあるが,たぶん,著者が投げかけたのも,その中の一つなのである。
