[ Amazon ] ISBN 978-4-87311-478-1, \1800
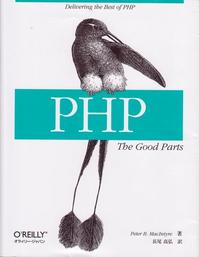
UNIXのテキストを書き直している。まだ作業途中ではあるが,まぁ型は決まってきたのでとりあえず公開してある。これから更に2章分追加して全体を整えて,最終締め切りが2週間後,2/18(金)なので,そこまでギリギリと作業を行うつもりである。
UNIXテキストとか言いながら,実質はC/PHPプログラミングのワークブックであって,演習のための最低限のCUI操作を教えたあとは,文法なんか後回し,とりあえずこう書けばこう動く!,分かったらちみっとカスタマイズしてこういう動作をするようにしてごらん,という調子で自学自習ができるようになっている。・・・というのが謳い文句だが,正直言ってこういう作りのワークブックを大学のテキストとして用意するってのはどーなんだと思わなくはない。
高校までの数学を単なる計算演習だと思い込んで疑わない層に,定理の証明を考えて次の定理を導く手がかりにし,理論体系の構築まで理解させる,とゆー本来の数学を教えることは至難の業である。プログラミングも同様で,文法を教えてサンプルプログラムを実行してその動作を理解し,言葉だけで書いてある演習問題を自力で解かせる,とゆーごく普通の「学習」が可能なのは結構まともなレベルなのである。試行錯誤を自分で行えない,つまり,躓いたら起き上がれない状態の子供に,「自分で立て!」とスパルタ教育をしたところで虐待,下手すりゃアカハラになる。「昔はこうやって鍛えられたもんだ」などという世迷言は通用しない。職のない優秀な若いDr.はゴマンといるんだから,昔を懐かしむだけの馬鹿ジジイはさっさと引退して席を作ってやれ。
今求められているのは,学生個々人のレベルに合わせた学習であって,逆に言えば,学習の「結果の平等」は二の次でいい,ということでもある。受講生の満足が第一なのだから,満足した結果が世間的にまるで通用しないレベルであってもそれは「自己責任」。ただし,世間並みの知識は与えましたよ,拾わなかった(or 拾えなかった)のはそちらの責任でしょ?,という説明責任を果たすぐらいのことは教師の最低限のモラルである。安くない学費を貰っているんだから,当然である。
だから,このスタイルのワークブックが,現時点でワシが考えるベストな形なのである。とりあえず書いてある通りに打ち込めばコマンドもプログラムもスクリプトも動く。でも,打ち込みながら「どういう原理なんだろう?」という「学習意識」が働かなければ,単なるキーパンチャーとして半期の講義を終えることになる。逆に,きちんと理屈の理解ができていれば,文法理解は荒っぽいけど,「こーゆーことができるんだ!」という,それなりに有用な経験として作用するはずである。この学習効果の差を,逐次レポートや提出課題を出させて確認し,成績を付ける。キーパンチャーでも真面目にやっていればC,そこそこ理解できていればB,完璧に理解して少し抽象度を上げた課題もこなせるようならA,という感じである。・・・ま,そーゆー講義ができているか,この評価基準がしっかり守られているかと言われれば,マダマダ,なのであるけれど,理想はそんな感じ。それを実現するためのテキストが自作のワークブックなのである。
しかしながら,本来のプログラミング教育ってこんな安易なモンじゃないだろう,という割り切れない気分はまだ残っている。本書は,O’Reillyのプログラミングテキストとしてはかなり薄手ながら,ワシが未だに未練を残している「本来のプログラミング教育」を実現したものとして,折に触れて読み返したい「スタイル」を持ったお手本なのである。
PHPのテキストと言えば,同じくO’Reillyから出ているPHP本が筆頭であろうが,これをテキストとして使うのは,少なくとも日本の2流以下大学では無理である。せいぜい参考書として紹介し,その中から適切な解説を抜粋して講義のネタに使うぐらいが関の山だ。O’Reillyに限らないが,邦書のPHP本でも講義テキストとして使える適度な厚みを持ったものは殆どない,とゆーのがワシの実感である。分厚すぎるのである。
その点,本書は理想的だ。本文は158ページしかないが,PHPの文法の解説からデータベースプログラミング,クラスの例示,JpGraphによるグラフ作成からPHP 5.3の新機能の解説まで,短いが要点を踏まえた文章で綴っている。欧米人の書いたものってホント分厚くて嫌になることが多いんだけど,これは真逆。まぁ,「言いたいことはコードに書いてあるから読み取って」とゆーことなんだろーな。具体的な例を次々に”Good Parts”として紹介していくのはコギミ良くて素敵だ。
何よりいいのは,ちゃんと解説文を読み解いて「機能」を頭の中で咀嚼して進んでいかないと,まるで学習ができない,という点である。打ち込めば動作するコードが書いてはあるのだが,文章による解説の補完という程度のものが多く,それらのコードの動作を理解するためにはそれ以前の記述をきちんと頭に入れておかないと理解不能という構造になっている。普通のプログラミングのテキストってこーだったよな,と思い起こさせてくれるスタイルの入門書なのだ。
PHPに限らないが,オープンソースな開発環境はリファレンスを必要なときにオンラインで参照するのが普通だ。検索するのは当たり前だし,PHPなら公式マニュアルを使わない開発者は皆無だろう。だから分厚い解説書はもはや不要・・・とは思わない。むしろ,きちんとした解説をしたいと思うのなら,ますます分厚いICT本にならざるを得ないのだ。
それは,断片的な知識を探すことが容易になった今だからこそ,それらを有機的につなげる糊としての解説がますます重要性を増しているからに他ならない。誰でも容易に入手して使えるパーツがゴマンとあるからこそ,それらの組み合わせの数は膨大なものになるのだ。どれをどう組み合わせてどういうことができるのか?・・・初心者であればあるほど,自身にあったレベルの入門書が,このインターネットに散らばる知識の集め方と使い方を例示してくれる最初の羅針盤として不可欠なのだ。羅針盤としての入門書としては,しかし,薄いに越したことはない。・・・このあたりのサジ加減が難しい。
ワシが書いているワークブックは最底辺層を掬い上げて,情報社会に飛び込むための助走をさせる程度を目指している。しかしそれでは「やりがい」を見出せない,学習の甲斐がない,というちょっと意欲のある向きが最初にPHPに取り組むための入門書として,良いパーツ(The Good Parts)を手際よく解説している本書はお勧めのものと言えるだろう。
2/3(木) 掛川・?
・・・初稿ゲラチェックの間,現実逃避のためのTweetしまくった結果,作業は進まず,結局そう不機嫌ギリギリまで追い込まれてしまった。それでもなんとかクリアして郵便局からゲラを発送したら急に眠気が襲ってきて早仕舞い(つーても午後6時過ぎだがな),家に帰ったらバタンキュー。3時間ほど寝てからメールチェックして二度寝。これが昨日の話。
で,本日よーやく本調子に戻った。遺憾イカン,こんなことでは如何,衣冠,偉観! とゆーことで,blog更新も再開するのである。ぷちめれも停滞しまくったがバンバン出していこう!・・・という決意は何回目なんだか。ま,ボチボチやるしかないのである。
で,UNIXテキスト,まだまだ手直しが必要だが,それでも何とか予定通りの教材は揃えることができた・・・となれば欲が出てくるもので,あと2章追加してやろう!とゆーことになった。どーせ講義ではそこまで出来ないし,ゼミ資料としては使えるか,というものなのだが,まぁさらっとでもPHPlot & Open Flash ChartやPthread, OpenMP,MPIについて触れてはおきたいのである。でないと,後々の講義や卒研に繋がっていかないからなぁ。VBでもMS Office VBAでもいいっちゃいいんだけど,そーゆーのってもう商売にならないご時勢。何せ,ICT業界上げてのCloud化まっしぐらシフト,アプリは全部Web常で動くようになるに決まっているのである。AndroidだってネイティブアプリですらJavaで作らなきゃいけないのであるから,Webの知識なしでプログラミングするなんて考えられないご時勢なのだ。
さて,明日は東京行き。吾妻ひでおマニアックスが始まるので見てこようかなぁ。初日だし,混んでたらさっさと帰ってこよう。
寝ます。
1/28(金) 掛川・晴
寒い日が続く・・・のだが,ボチボチスギ花粉が飛び始めるそうな。ワシはまだ花粉症デビューに至っていないのだが,今年は相当ひどいことになりそうだという予報が。該当者の方々はさぞかし戦々恐々としているのであろう。お大事にして頂きたいものである・・・ワシの敵を除く。
そーいや,梅の蕾も膨らんできた様子。桜よりも地味だが趣があるんだよな~。昨年はコミケスペシャル水戸のついでに偕楽園を散策してすっかり魅了されたのである。どっか見に行きたいもんだ。
うちの研究室,卒論・概要は一通り仕上がり,来週から発表練習フェーズに移行する。昨年は「ワシが」頑張ったが,今年は間違いなく「ワシも」頑張ったのである。この微妙なニュアンスの違いについては察して頂きたい。しかしまぁ,今年は3人だから楽であった。来年は8人・・・死ぬかも。
ここのサーバの移行を画策している。金がない,というのはいつものことだが,回線品質・サーバトラブルの少なさはいいとして,新しいバージョンのサービスが始まっても旧ユーザがほったらかしにされるWebArenaの姿勢に嫌気がさした,ということが一番の理由。
乗換先としては,T社長が脅威と言っていたDTIのServerman@VPS。IPv6が使えるのと,何より安くて安定してそう,というのが大きい。DTIは技術力では安心していいと思っているので,まずは2月からお試し運転してじっくり試してから3月初旬に移行するかどうかを決めよう。Blue Onyxってのも興味があるし。
ゲラチェックが進まない・・・。

明日頑張ろう・・・。これが終わらんとblogどころではない。Twitterは別物であるのでいいのである。
寝ます。
1/22(土) 掛川・晴
さむ~・・・って,寒い寒いって言ってばっかだが,ホントに寒いんだからしょうがない。特に下半身。下半身デブだから昔はそれほど感じなかったんだが,やっぱ内臓脂肪だけじゃなく,足の脂肪も落ちたのかなぁ。いいことなんだが,しかし寒いのはヤ。しかしデブに戻るのはもっとヤ。
Facebook,アカウントだけとってほったらかしてたのだが,どうやらTwitterとの連携ができるようなので,久々にアクセスしてProfileの手直しもついでにやってみた。

ビジネスマンじゃないし,学者は論文と業績だけのお付き合いをするのが普通なので,今んとここれ以上何か活用しようという予定はない。いい使い方があれば別だが・・・どーも馴染まんなぁ。有名人のメッセージを読みたいだけならTwitterで十分だし,日本社会に根付くのかしらん?
ぷちめれどころかここの更新も滞っているけど,一段落したとはいえまだまだ2月中旬の締め切りに向けて現在進行形のUNIX(+Webプログラミング)テキストや情報数学のゲラチェックなど,論文研究以外のお仕事が詰まっていて余裕なし。何とかせにゃぁ。以前なら逃避しながらいろいろ書けたもんだが,体力落ちたかなぁ。
さて,お掃除洗濯風呂掃除してスポーツクラブで汗流して寝ます。
1/12(水) 掛川・?
あ~,寒い寒い。全く,冷え込みがきついのと,昨年より格段に皮下脂肪が減少したことによる相乗効果で寒いったらありゃしない。ヒートテックを上下3枚買ったが,大活躍中である。講義とか試験監督とか,足元が寒い教室では必須のアイテム。かつて,ひざ掛けなんて惰弱な奴がするものさ~,などと嘯いていられたのはデブで馬鹿で若かったからだな。人生,中年になると反省することが増えますな。
プログラミングの教材をあれこれアップしているのだが,preタグでくくっただけではイマイチ見栄えが悪い。文法構造まで調べて色分けソースコードを表示しているサイトをちらほら見かける度に,どうやっているのか不思議だったが,どうやら手動でやっているところを除いて,SyntaxHighlighterをJavaScriptを使っているところが多いようだ。
つーことで,試しにGSLのサンプルコードをきれいに表示してみた。

ってのを

というようにカラフルにしたわけ。ついでにshBrushCpp.jsのキーワードにGSLのデータ型や関数名を追加してGSLの機能の強調表示に対応した。だいぶ見やすくなったワイ。
この調子でPHPのプログラミング教材を作っていけたらなぁ・・・と取らぬ狸の皮算用。それよかコードも文章もバリバリ書かねば。明日中に目処をつけてしまおう。
寝ます。