[ Amazon ] ISBN 4-480-08675-7, \1500

一体全体,何でこんな本がもてはやされるのかなぁ,というのが本書を一読しての第一印象であった。京大の数理工学専攻出の著者なら,結構なレベルの解析学や数値計算,応用事例を学部でも勉強させられるはずだから,そこで学んだ知識を総動員してぶち込んだらこの程度の本は書けて当然。しかも数値計算の話が多少入っているぐらいで,内容はかなりオーソドックスな初歩の解析学(微分積分)に,関数空間の初歩を混ぜ込んだ程度のもので,解説が計算例をまじえて丁寧なのは美点ではあるけれど,もっと新機軸を入れられなかったのかなぁ・・・と,思っていたのだ。
で,この度,複素解析の講義を持つことになり,あっちこっちの文献を調べまくった中で,本書も再読することになったのだが,その際やっともてはやされる理由が分かったのである。
そうか,新しい視点を導入しなかったのが美点なんだ,と。手垢にまみれたネタを,より丁寧に具体的な計算例を交えて解説することに徹した,それが支持される理由だったのだ,と合点がいったのである。
数学は難しい。論理的思考は確かに人間の一部ではあるが,全てではない。本能とか感情とか,人間を人間たらしめる要素があってこそ,まともな社会生活が送れるのだ。それを数学は全否定する。定義から外れた用語の使用を認めないし,全ての定理はコード化可能な論理展開に乗っ取った証明が必要とされ,直感的な説明を排除する。書店の数学書コーナーでは「直感的な数学」みたいな本が出ているが,あれは数学ではない。数学の「あらずじ」みたいなモンである。もちろん,ワシら教師が講義するのも「あらずじ」に過ぎず,本式にやろうとするなら,「定義→定義→定理→証明→定理→証明→定義・・・」という,知らない人にしてみれば無味乾燥な繰り返しにならざるを得ない。記述にアクセントを付けるために,比喩や演繹に基づく「説明」や「具体例」が入ることはあるが,それは本来不要なものである。発想の原点としては大いに役立つとしても,数学の骨組みとは無関係なものとして扱われるのが普通である。
つまり,数学は,人間の脳の活動の多くを「論理」に向かわせようとする,かなり不自然な頭の使い方を強要するものなのである。それを楽しみながら出来る人間もいるが,まあ少数派である。大多数にとっては大なり小なり強制されてようやく身に付くものであり,しかも情緒力なんてものと違って,能力の個人差が大きく開いてしまう。中学,高校と進むにつれて,「自分は数学に向いてないや」と諦めてしまう人が増えるのも当然のことなのである。大学の理工系に進んだところで,いきなり「本式の無味乾燥論理体系」にぶち当たって挫折しない人間もまた少ない。今では専門課程の方から圧力がかかるため,「本式」で講義を行う数学教師は殆ど絶滅したと思われるが,個人的には「無味乾燥論理体系」の「無味乾燥」にもそれなりに存在意義があるので,少しは粉振りかけてもいいからきちんと教えて欲しいものだと思う。が,次々と受講生が減っていく事実を前にしてそれを貫き通すのはナカナカ困難である。
それでも何故か「計算」という部分に関しては,未だ世間の支持が高い。これだって「無味乾燥論理体系」の一部ではあるんだけれど,
○予備知識があまり必要ない
○計算に使われる論理体系はストレートなものが殆どなので,覚えるのが楽
○計算を進めることで,自力で解けた,という感動を味わえる率が高い
というあたりが数学における「計算」が広く支持される理由だとワシは思っている。この辺をうまく商売に結びつけたのが公文式で,ドリル方式の自学自習が可能だったのも,殆どの学習内容を「計算」練習に絞ったからである。
しかし,これを逆に考えると,世の中に必要とされる数学は「計算」しかない,ということになってしまう。これだけコンピュータがカジュアルにとけ込んだ現状を考えると,計算を人間が行う必要は殆どなく,もっとドラスティックな思考,近似的な概算とか,大規模な計算処理の効率的なやり方などを人間は担当すべきで,任天堂DSでチマチマ計算ドリルを解くのが数学教育の結果だとすれば,この先の日本の科学技術は非常に危ういと言わざるを得ない。
吉田のこの本は,大学理工系の線型代数・微分積分を本式に習った人間ならば,一度は聞いたことがあるテーマばかり扱っている。でも扱い方は非常に丁寧で具体的だ。「計算」の範囲で可能な説明を具体例を交えて行っているので,もしこれでその節の解説が分からないようなら,大学の基礎数学を学ぶための基礎教養に欠けていると言わざるを得ない。もう一度,高校までの教科書をひっくり返して勉強し直すように。
逆に言えば,本書の解説は「計算」が及ぶ範囲の「数学」,いや基礎解析学に留まってしまっているのである。「え,こんなに分厚い(文庫本500ページ超)のに?」と訝しげに思われる方もおられようが,そうなのである。線型代数+微分積分学+(初歩の)複素解析,これに数値解析のフレーバーを効かせたのが本書の内容の全てなのだ。それが悪いというのではない。いや,それこそが本書を数学書としては異例の売れ行き(って具体的な発行部数はシランけど)に繋がった理由なのである。計算が届く範囲の内容と解説に徹底して絞った自学自習書という狙いを持ったからこそ世間のレベルと要求にジャストフィットし,見事なマーケティング的成功を収めたのである。
だが・・・ワシはやっぱり言いたくなる。「これじゃ,『現代の』数学に繋がりませんよ」と。何故なら,今の数学は様々な「視点移動」によって組み立てられた論理体系なのであり,古典的な計算の単純な延長上には作られていないのだ。むしろ,そこからいかに浮遊するか,もう一つ別の位相を加えるかということに腐心してきた結果が今日の数学なのである。今更言っても詮無いことだけど,吉田には是非とも「本書の解説の限界」を示して欲しかったのだ。チルンハウス変換の先にも5次以上の代数方程式の代数的解法が存在しないことを解説して欲しかったのである。
無い物ねだり? いや,まさしくそうだ。世間の支持を得た書物に対してグダグダ文句を言うのは単なる嫉妬と片づけられてしまうだろう。だからこそ,ワシは唾棄されるだけのこのblogのエントリに,こう書き付けて置かなければならない。
是非とも,同じちくま学芸文庫から出ている「角の三等分」も読んでみて下さい。吉田の書には書いていない,視点の移動が主要テーマとなっているから,と。
半藤一利「決定版 日本のいちばん長い日」文春文庫,同「それからの海舟」ちくま文庫
[ Amazon ] ISBN 4-16-748315-7, \590「決定版 日本のいちばん長い日」
[ Amazon ] ISBN 978-4-480-42443-3, \780
[ Amazon ] DVD 岡本喜八監督作品「日本のいちばん長い日」(1967年)


敗戦記念日につき,敗戦処理をトピックとして取り上げることにしたい。
・・・と方針は決まったが,さていざ取り上げるとなると,結構難しい。今更,ウヨクやサヨクの意見開陳本を取り上げるのは退屈だし(ワシはどちらにもすっかり飽きてしまった),かといって,まじめくさった評論・学術書を読むのは,加藤典洋の「敗戦後論」を挫折して以来,なるべく忌避するようにしている。さりとて,右だの左だののプロパガンダっぽいものに引っかかるのはイヤだなぁ・・・と言う時に重宝するのが信用できるジャーナリストによるドキュメンタリーである。ワシのようなめんどくさがりの読者の代わりに綿密な資料の解析と取材を敢行し,事実をキッチリ押さえ,その上でエンターテインメント的なストーリーテリングを行ってくれる,そーゆー人の書いたものなら万人にお勧めできるというモノである。
とゆーことで,それが出来る数少ないジャーナリスト,半藤一利の著作をもって,日本の反省の夏の一日を振り返ってみたい。
最初の出会いは昨年日記にも書いた通り,半藤の本を原作とした映画だったのである。NHK BSの敗戦記念日特集の一環として,この日本映画の大作「日本のいちばん長い日」が放映されたのを見て大興奮したのであった。
何が興奮したかって,まず出演俳優陣の豪華さだ。制作が1967年というから,40年以上前のものだが,制作の2年後に生まれたワシですら名前がスラスラと出てくる俳優ばかり登場する。鈴木貫太郎役・笠智衆や,阿南惟幾役・三船敏郎はいうに及ばず,ナレーターの仲代達矢,佐々木大尉役・天本英世,以下役名は略すが,加東大介,加山雄三,黒沢年男,志村喬,小林圭樹,加藤武,北村和夫・・・,いやー,凄いですね。しかも今と違って,アイドル的な客引きメンバーは加山を除いてゼロ,演技力で圧しまくる実力派ばかりである。つまり,芝居については文句なしの出来にならないほうがおかしい。実際,この中で鬼気迫る演技を見せる黒沢年男と天本英世,対照的に飄々として敗戦処理を決断し実行する笠智衆が一番見応えがある。その辺は実際に映画を見て堪能して頂きたい。ワシは既に5回以上は眺めてしまっている。難点は台詞がある女優が一人しかいないという所か。暑苦しく色気のない映画としてもNo.1であろう。
しかし何と言っても,一番スリリングなのはストーリーだ。しかもこれは実際に,1945年(昭和20年)8月14日正午から翌15日正午まで,つまり,ポツダム宣言受諾を国民に知らせる玉音放送までの24時間を描いた史実に基づく物語だ,というから二重に面白い。いや,面白いと言っては不謹慎かもしれない。しかし,戦後60年以上経過した今のワシらから見れば,殆どスラップスティックかという程,お粗末な小型の二二六事件を描写しているのであるから,呆れると共に,やっぱり無責任に面白いと思ってしまうのである。
第二次世界大戦の枢軸国側において,戦争責任(ここでは「敗戦の」責任者という意味で用いる)を追求するのが一番ヤヤコシイのは日本である。ドイツやイタリアのように独裁権力を持ったヒトラーやムッソリーニという「個人」が不在だったからである。強いて言えば,二二六,五一五事件を引き起こし,中国東北部から権益を拡大しようとした日本陸軍の将校クラスにその責任を帰す,というのが今の日本における一般的な認識と言うことになる。更にそこから個人としての責任者を持ち出そうとすると・・・ま,東京裁判で処刑されたあの方々,ということになるのだろうが,石原莞爾はどうなんだ,いや,もっと上に統帥権を持った天皇という存在があっただろう・・・という議論は未だ絶えることはないけれど,こういうゴタゴタが未だ収束しないと言うことは,やっぱり陸軍というコアグループが日本の世論と政治を引っ張って戦争に突入していった,という他ないってことなんだろう。そしてそれを証明する事実は山ほど上がっている。その事実の一つが,「日本のいちばん長い日」,つまり八一五宮城事件なのである。
事件を一言で言うと,ポツダム宣言受諾に反対する日本陸軍の若い将校達が近衛師団長を殺害し,玉音放送を阻止するため皇居やNHKを一時的に占領,しかし関東を統括していた東部軍首脳にあっさりと事件は鎮圧されてしまうというものである。14日深夜から15日午前中に起こったことなので,とても短い出来事であるが,二二六や五一五事件とは異なり,皇居及び天皇の居住地(御文庫)まで取り囲んでしまったのだから,これが長引いていれば原爆の数個は追加投下されていた可能性もある,歴史的にもないがしろに出来ない事件である。
しかし,それが鎮圧された後で振り返ってみると,この事件,かなりクーデターとしては出来が悪い。陸軍全体が「承詔必勤(意訳:天皇がポツダム宣言受諾を決断したのだから,黙ってそれに従え)」でまとまっていたにも関わらず,その雰囲気を理解せずに一部の青年将校が激高して暴れた,という感が拭えない。しかしそれを実行してしまう「雰囲気」が,日本陸軍内部では充満していたということは確かだろう。そしてその雰囲気熟成が昭和に入ってからなされており,その最後の小爆発がこの宮城事件である,と解釈できる。そう考えると,やっぱり「戦争責任」を個人単位で考えるのは相当難しいんじゃないかなぁ,となってしまうのである。
映画の原作となった半藤の「決定版」は,映画では演出の都合上端折られていた事実も含めて綿密に事件の推移が描かれており,イケイケドンドン日本男子が死滅するまで(「二〇〇〇万(人)の特攻(隊)を出せ」だもんなぁ),という雰囲気の日本陸軍を押さえ込むのがどれほど大変だったことか,イヤと言うほど知らしめてくれる。映画の方も,事実を曲げず,象徴的な「絵」,例えば畑中少佐の狂気じみた情熱,計画が失敗した時の椎崎中佐の激高ぶりなどをうまくストーリーに組み込んでいるので,映画だけを見て宮城事件を勉強した気分になっても,何ら問題ない。どちらもノンフィクションとして,映画として優れた作品になっているのである。
さて,敗戦処理,ということでは,日本では幕末期に幕府側の実質的な責任者として活躍した勝海舟という人物を忘れることは出来ない。半藤が1965年にまとめあげた本書は最初,営業上の理由もあって大宅壮一の名前で出版されたが,そこで大宅はこんな序文(P.3 – 5)を寄せている。
今日の日本および日本人にとって,いちばん大切なものは”平衡感覚”によって復元力を身につけることではないかと思う。内外情勢の変化によって,右に左に,大きくゆれるということは,やむをえない。ただ,適当な時期に平衡を取り戻すことができるか,できないかによって,民族の,あるいは個人の運命がきまるのではあるまいか。
そしてこの宮城事件が「平衡感覚」を試される時期の一つであったとし,本書の意義をこう述べている。
敗戦という形で,建国以来初めてといっていい大きな変化に直面したとき,全日本がいかに大きくゆれたかを,当時日本の中枢にあった人々の動きを中心に調べたら,幕末期のそれと比較して面白い結果が出るのではないか。
結果として逆転しちゃっているけど,半藤は宮城事件と比較対照となる「幕末期のそれ」を2003年に上梓し,2008年に文庫化した。それが「それからの海舟」である。
西郷隆盛率いる官軍に対し,幕府側の責任者として江戸城引き渡し(1868年3月14日)を決断して実行した勝海舟の存在を知らない日本人がいたら,それこそ非国民のそしりを免れ得ない。しかし,それ以降の「敗戦処理」に勤しむ海舟を面白く描いた読み物はかなり少ない。司馬遼太郎に至っては,明治期の海舟は大言壮語や韜晦が酷く信用ならない,と一言の元で切り捨てているぐらいである。古くは福沢諭吉が政府高官になっていた海舟を「痩我慢の説」で非難しているところから発するようで,半藤はこの福沢の批判をかなり詳細に取り上げ,分析している(第11章)。全編これ「海っつぁんびいき」の威勢の良い半藤の啖呵で満ちている本書であるが,歴史的事実と,海舟非難論を書いた福沢の個人的,社会的問題意識も併せて論じているから,単なる卑俗な海舟擁護論になっていないところが半藤の,ジャーナリストとしての「平衡感覚」なのであろう。
そんな訳で,維新後の海舟の評判はおおよそよろしくないのだが,戦後になると,その大言壮語の中にきらりと光るモノを見いだして再評価する動きも出てくる。例えば古山寛・谷口ジロー「柳生秘帖 風の抄」は,海舟の談話における一言がヒントになってシナリオの骨格が出来上がったものである。
それ以上に,思想的な影響を受けていると思われる作品が,安彦良和「王道の狗」である。Comic新現実Vol.1でこの第37話が抜粋されているが,そこでは晩年の海舟が,同じ島国のイギリスが帝国主義に走っている現状をふまえた上で,日本はそれを真似するのではいかん,と釘を刺し,こんなことを言う。
「アジアの海は下町の横町だよ!」
「支那も朝鮮も古い御近所だ」
「つき合いってもんがあるだろ」
「これからは今まで以上にそれを大切にしなくちゃいけねえ!」
出典は多分「氷川清話」あたりかと思うが,あいにく手元にそれがないので(職場に死蔵されているはず),半藤の書から孫引きさせてもらおう。
「日清戦争はおれは大反対だったよ。なぜかって,兄弟喧嘩だもの犬も食わないじゃないか。(中略)
おれなどは維新前から日清韓三国合従の策を主唱して,支那朝鮮の海軍は日本で引受くる事を計画したものサ。」(P.276)
漫画の台詞と,この主張を両方読んで,ああなるほど,サヨクというか平和主義者を代弁して,安彦良和は勝海舟の口を借りているのだな,と会得したモノである。半藤の著作はこの戦後の風潮とは無関係に著されたものであるけれど,太平洋戦争を主導した「雰囲気」への嫌悪感を持っているという点は間違いなく共通している。
1945年8月15日と1868年3月14日を繋ぐ,半藤の大仕事は世紀をまたいでここに一応の完結を見た。鈴木貫太郎と勝海舟,共に敗戦処理を主導した人物とそれを取り巻く環境,そしてそれに対する論評をマゼコゼにして優れた読み物にした労作は,日本の戦後の民主主義がきちんと機能してきた証として誇っていいものだと思う。こういう言い方はある種の人々の憤激を誘うかもしれないけど,ワシ個人は「負けて良かったのだな」と思うのである。そして,「良かったな」と後世のワシらに思わせるだけの仕事を成し遂げた両人に対して,加えてこの両人を取り上げてくれた半藤にも,心からの謝意を表したいと思うのである。
ゆうきまさみ「ゆうきまさみのもっとはてしない物語」角川書店
[ Amazon ] ISBN 978-4-04-854206-7, \1500

いやぁ,お互い年は取りたくないものですなぁ,ゆうき先生。前作(上記写真の左)が出た時は1997年,ワシがまだ能登半島でくすぶっていた時代ですよ。「いんたーねっと」とやらがボチボチブームになり出した頃。懐かしいですなぁ。これは後ほど2003年に角川スニーカー文庫本2冊(天の巻,地の巻)にまとめ直されましたが,そろそろ視力に衰えが見えてきた三十路後半の身には,ちと読むのが辛かった覚えがあります。だもんで,いまでもこの日に焼けちゃった単行本が手放せないのですよ。
その単行本が刊行されてから既に11年経ちました。角川書店は角川グループホールディングスを構成する一出版社となり,その社長はあーた,NewTypeの編集長だった井上伸一郎さんですよ。ワシは角川GHDの株主になっちゃうし,全く光陰矢の如し。でもゆうき先生のこのコラムが連載開始以来23年,50才を越えられても未だに続いているのですから,ワシもまだまだ,あと十年は頑張らねば,と,ふんどしを締め直さねばなりません。良き先達は全くありがたいものです。・・・年寄り臭い言い回しに終始しましたが,年のせいと思って聞き流して下さいませ。
特にアニメオタクではないワシなので,コラムだけは欠かさず立ち読み(買えよ)していたNewTypeともいつしか縁遠くなってしまいました。なので,突っ込みキャラが登場(P.62)していたことも知らず,表紙の女の子を見て,「ああ,ゆうき先生もとうとうご結婚されたのか,羨ましいなぁ」と麗しい誤解をしてしまいました。大変失礼致しました。しかしこのツッコちゃん,可愛いですね。可愛いと言っても既にワシにとっては友人知人のお嬢さん,としか思えなくなっているのが非常に悲しいのですが。
オールカラーになっても,内容が時事問題から身辺雑記まで節操なく盛り込まれているのは全く変わらず,オールドファンとしては嬉しい限りです。晩年の手塚治虫は丸っこい線を描くと線がふるえてしまうと嘆いていましたが,ゆうき先生はせいぜい目が悪くなった程度(P.98)で,シャープな描線はCGになっても健在ですね。ご健筆,頼もしき限りです。保守復権の先導役・小林よしりんもまだまだやる気のようですから,ゆうき先生には是非とも戦後良識派としての立場を遵守され,ますます議論を深めて頂きたいと願って止みません。
この調子だと,次の「もっともっとはてしない物語」が出版されるのは10年後ですね。その時,私は50代,ゆうき先生は還暦を迎えるわけで,戦後初の「おたく老人世代」の先鞭役となられるはず。後輩のワシとしては,おたくの老後をどのように描かれるのか,今から大いに楽しみなのです。TVアニメ化が始まったばかりの鉄腕バーディー,掲載誌のヤングサンデーが休刊になってしまって今後の行く末が心配ではありますが,もし連載が中断でもされるのなら,バーディーの次に「ヤマトタケルの冒険」路線が復活するのではないかと,ワシはよからぬ期待を持ってしまっておりますので,それはそれで楽しみです。無粋な輩でどうもすいません。実は初期作品集(1,2)が編み直されると知って以来,アニパロコミックス等でゆうき先生の作品を読んでいた時代を思い出してしまっておるのですよ。・・・やっぱし,年ですかねぇ。
では,これからのゆうき先生のご活躍を祈念して,筆(キーボードですが)を置かせて頂きます。
長谷川武光・吉田俊之・細田陽介「工学のための数値計算」数理工学社
[ Amazon, 出版社のWebページ ] ISBN 978-4-901683-58-6, \2500
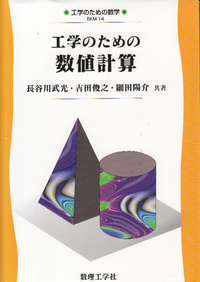
うはー,やりづれー。というのも本書は献本なのである。つーても献本してもらった癖にイヤミっぽいことを書いたという前例が既にあるので,貰いモンだから筆先が鈍るなんてことはあり得ないことは証明済みである。我ながらなんて「いい性格」なんでしょうねぇ。
やりづらい理由はもう一つあって,よく知っている内容の,しかも初学者向け(かどうか?)のものであるから,ワシと著者らとの主観の相違が際立ってしまう,ということが挙げられる。つまりは学問論争に繋がってしまうので,本格的に論じ始めたら果てしなく続いてしまいキリがない。これについては著者(ら?)とダイレクトにやりたいと考えているので,ここでは割愛する(でもちょっと混じってしまったか?)。
なので,ここではワシが個人的に数学を主専攻としない大学学部生向け教科書に必要不可欠と考えている以下の点についてのみ,考えていくことにしたい。
1) 現代的な内容になっているか?
2) 抽象的な議論に終始することなく,具体的事例を盛り込んでいるか?
3) 学習して欲しい基本的内容・記法は本書内の記述で自己完結しているか?
4) より深い知識を知るための参考文献は明示してあるか?
5) アフターサービス用のWebページが用意してあるか?
まず1)について。本書については掛け値なしに合格である。感心したのは
第2章のIEEE754浮動小数点数の解説(丸めモードの解説も欲しかったけど)
第3章のLU分解の解説(初学者向けの分かりやすいモノかどうかはともかく)
第8章のClenshow-Curtis公式の解説(翻訳でない邦書初?)
第10章の偏微分方程式の解説(詰め込みすぎのきらいもあるけど)
など。特に2章は現代の線型計算が,主として計算性能を上げるためにblock単位で行われていることを意識して記述してあるので,邦書としてはかなり「異色」,でも「現代的」であることは間違いない。LU分解の分かりやすい証明(P.34~36)はワシも使わせ頂くつもりである。
2)については文句なしに合格。ただ,地方国立大学工学部で教えたワシの経験ではちと高度すぎる事例が多いかなぁと感じた。特に第10章については,これだけで半期を費やすぐらいの時間を掛けないと身に付かないのではないか。本書を使った講義がどのぐらいの時間でどのように行われているのか,興味深い。
3)について。及第点ではあるが,3人の共著ということもあって,記法に不統一なところが散見されたのは残念。まあでも講義でフォローできる程度だから,大した問題ではない。
4)はまあ妥当・・・ではあるけれど,古くて絶版になったもの(特に邦文書)が多いのは初学者向けとしてはどんなものだろう。[2], [a]は新版が出ているので,そっちを勧めた方がいい。文献の並び順がどうなっているかも不明なので(「数値計算のつぼ」「同わざ」が離れているのは何でだろう?),も少し気遣いが欲しかったところ。
5)については,演習問題の解答もある親切なものができつつあるようなので合格。販売時には完成・・・しますよね?
つーことで,全体としてはちょっと高度な数値計算入門書として,理系のまともな大学生にはお勧めできる内容と言える。これを使って学習した学生さんの中から優秀な研究者が輩出されれば,更に本書の価値が上がろうというモノである。今後大いに期待したい・・・と,著者らにプレッシャーをかけて,やりづらいぷちめれを締めることにする。
色摩力夫「フランコ スペイン現代史の迷路」中公叢書
[ Amazon ] ISBN 4-12-003013-X, \2000

そーいや,スペインにフランコという独裁者がいたな,と気が付いたのは,昨年(2007年)のいつだったのか。八重洲ブックセンターでウロウロしている時にはたとひらめき,「フランコ,フランコの評伝はないか」と店内のデータベースを漁ってみたら,ヒットしたのがこの一冊。もはや在庫処分待ちという古ぼけた本の谷間にこれが残っていたのを見つけ,早速購入した。が,その後しばらくをパラパラとはめくるものの読了には至らず,ネチネチとベッドサイドの机に置きっぱなしになっていたのだが,今年(2008年)に入って軽度の鬱状態になり,逃避行動を取る中で本書にチャレンジ,時系列でフランコの事績を描き出した重厚かつ簡潔な記述に引き込まれ,一気果敢に読了してしまったのであった・・・が,ワシのは悩みは深くなるばかりで,ますますフランコという人物が分からなくなってしまったのである。
↑を読んでもワシ以外の人間には何が何だかさっぱり経緯がワカランだろうから,以下ではも少しかみ砕いて説明することにする。
高校で世界史を取ると,今はどうだか知らんが,ワシが高校生の時は第二次大戦終了直後で授業は打ち切りとなっていたものである。従って,授業の終盤で習う第二次世界大戦における枢軸国(ドイツ・イタリア・日本など)と連合国(イギリス・アメリカ・ソ連・中国など)の勢力図は大概頭に残っている。その勢力図には,ユーラシア大陸の西のはじっこ,イベリア半島に,塗り分けされていない空白地帯があった。これがフランコが独裁者として君臨していたスペインである。そしてフランコと言えば,ヨーロッパファシズムの一角を担っていた極悪人ということになっている。・・・ん? ファシストの独裁者の癖に,世界大戦中はドイツ・イタリアに与せず,中立国? どーゆーことなんだろう?
・・・というのが,「フランコという独裁者がいたな」と気が付くまでの経緯である。
しかしこのフランコという人物,どうにも分かりづらいのである。例えば,水木しげる「劇画ヒットラー」(ちくま文庫)には1940年にフランス・スペイン国境近くのエンダヤ(水木著ではアンダイエ(仏語読みかな?))で行われたヒットラーとの会談が描かれている(P.215)。ここでフランコは,(スペイン内線による疲弊のため)スペインは他国と戦争が出来る状態ではないことを述べ,ノラクラとヒットラーからの参戦要求をかわしている。
が,本書によればこれは事実ではなく,会談後に外相間で取り交わされた議定書は,むしろドイツ・イタリアとの枢軸同盟への参加の意思表示に近いものだったという。また,フランコもこの会談の時期までは,破竹の勢いでフランスを屈服させたドイツに傾いていたようだ。しかし,この会談後にフランコの政治的参謀となったカレロ・ブランコの超合理的な「政策メモ」(この後も度々フランコの政治的指針となる)の指摘により,フランコは枢軸同盟への参加を徹底して引き延ばすようになり,結果として中立国としての立場を維持することに成功した。うーん,独裁者にしては日和見的な態度である。
日和見といえば,独裁者に駆け上る契機となったスペイン内戦(1936年~39年)への関わりも,本書によればフランコの自発的なものではなかったようである。植民地モロッコで軍事的才能を発揮していた彼を,人民政府に対抗するクーデター首謀者側が引っ張り出した,というのが真相らしい。結果,内線の中で権限を一手に握ったフランコは独裁者としての地位を獲得し,内戦にも勝利してスペイン全土を掌握するに至るのである。うーん,ナポレオンがフランス革命のドサクサで担がれて皇帝になっていく過程とよく似ているよな。結局,乱世の中では洋の東西を問わず,秀でた軍事能力を持つ者に権力が集まっていくものなのであろう。
フランコの日和見的態度は,大戦後のスペインの地位を高めるのにも大いに役立っている。腹心カレロ・ブランコは大戦後の世界秩序が米ソ冷戦という構造になっていくことを冷徹に見抜き,フランコに提出した政策メモで,亡命した人民政府側の勢力を弾圧したところで,共産主義の招来を恐れる西側各国はスペインを非難こそすれ,実効的な圧力をかけてくることはないから気にするな,と助言する。外交官である著者も「シニカルな文書と見えるが,その洞察力は認めざるを得ない」(P.242)と舌を巻いている。こうしてフランコは独裁的政治を維持しながらも,政権内部では権力闘争のバランスの上に立つ「調停者」としてふるまいながら,スペインに高度成長をもたらすのである(1960年代)。正確に言えば,経済政策に全く疎いフランコが,カレロ・ブランコ率いるテクノクラートの政策を丸飲みしたことによるものらしいが,それを許容する独裁者ってのも度量が広いというのか,単なるボンクラなのか・・・。
こうして全く楽しくなさそな独裁的権力を維持しながらも,フランコは自分の後釜となる政体を,スペイン内戦前の「王国」に戻すよう計画していたというから,ますますこちらは混乱させられる。千年帝国を夢見たヒトラーとは正反対の現実主義者であったフランコは,カレロ・ブランコの案に従い,徐々にファン・カルロス一世を次期国家元首とすべく体制を整えていくのである。結果,フランコが危篤になるや権力が国王に委譲され,スペイン「王国」が復活したのである。その後は議院内閣制の立憲君主国家へ移行,スペイン内戦時からは想像も出来ない程のスムーズさで独裁国家から脱却したのだから,何というか,見事としか言いようがない。
こうなると,フランコを単なるファシスト独裁者呼ばわりするのは「何か違う」感じがする。透徹した合理性を愛したという以外,首尾一貫したイデオロギーはなさそうだし,あからさまな抵抗勢力は弾圧しながらも,部分的に選挙を行うなどして民意を確認しながら各勢力間のバランスをとり続け,次の世代へのバトンタッチをスムーズに行うための体制作りに勤しんだのだ。・・・一体全体,何が面白くて独裁者になっていたんだろうと首を傾げてしまう。ホントーに独裁を楽しんだんですか,フランコさん?
本書の副題は「スペイン現代史の迷路」となっている。これは,フランコの歴史的歩みを学問的にカッチリ押さえて重厚な記述を行った著者をして,フランコ時代をどのように捕らえていいものやら判断が定まらなかったという意味が込められている。いや確かに,独裁的権力を維持しながら合理性を追求するという訳の分からなさは迷路なんてモンじゃない,「迷宮」と言いたくなるほどである。しかし,参謀役カレロ・ブランコと,彼を重用したフランシスコ・フランコのコンビが愛したこの「訳の分からなさ」が,政権を長期に渡って維持する原動力となったことは本書によって明らかになったのである。しかしそれでもなお,フランコという人物がもたらした筈の,この長期独裁政権の根本的原因がどこにあるのかは今持って不明であり,それ故にフランコ時代の位置づけも宙ぶらりんになっているのだ。
本書は優れた学術書であることは疑いない。にも関わらず,対象が「フランコ」であるが故に,事実関係以外のものが見えてこない。これは一種の「芸術」である。
そう,本書はフランコ独裁そのものが芸術的な「訳の分からなさ」に彩られたものであることを明確にしたという意味で,貴重な一冊となっているのである。