[ BK1 | Amazon ] ISBN 4-592-13298-X, \571
最近,注目している書評コラムがある。Asahi.comで毎週金曜日に更新されるコラム,「松尾慈子の漫画偏愛主義」だ。性別は異なるが,世代が近いせいか,取り上げる作品がみょーにワシの好みと一致する。文章もテンパっていて面白いし,何より余計な知識や引用なしの潔い「私はこれが好きなのよ」パワーが全開しているところが良い。あんまし反響がなさそうなのが気の毒なのだが,もっと話題になって良いコラムだろう。がんばれ負け犬(ォイ)。
そこでちょろっと名前が登場する漫画家,遠藤淑子の作品を取り上げることにする。出版されたのが今年の初頭だから,まだ店頭では入手可能である。しかし,松尾さんがおっしゃっているように,単行本が出たのが数年ぶりという寡作ぶりで,本書も1997年から2001年までの作品群をまとめたものである。うーん,何があったのだろう・・・。ま,ともかく本は出たので,あまり詮索しないことにする。
遠藤はデビューからこの方ずーっとコメディを書き続けてきた作家である。今でも基本的にその路線は変わっていないのだが,次第に「ヒューマン」という形容詞が冠せられる作品が多くなっていった。個人的にはちょっとありきたりすぎるかな・・・と思うことが多く,取り立てて好きな作家ではなかったのである。大体,ヒューマニズムでまとめられる作品の多くは,大衆から嫌われることを恐れて逃げているように感じられるのだ。普段,あれこれと世間の制約から枠をハメられて思うように動けないもどかしさを感じている一般人の一人としては,せめてエンターテインメントぐらいは,少なくとも表面的には制約から逃れてスカーっとさせてくれるものを楽しみたいのである。これで少しは絵柄が派手であればまた別の楽しみ方が出来るのであるが,遠藤の絵は,申し訳ないがデビュー以来,殆ど変化がない(ように見える),地味なもので,ストーリーまで手堅くまとめられてしまっては・・・うーん・・・なのである。
しかし,人にはどうしても動かせないもの,変えられないものがあって,他人からどうこう言われても,どうしようもない性質というものがある。無理に変えようとすれば,体や精神に変調を来して寝込んでしまうことだってある。遠藤の軌跡を振り返ってみると,ちょっとゆるめのコメディ路線,しかも最後はヒューマン風味,という作風は,どうにも変えようのない代物だったのであろう。そのままずーっと描き続け,近年はボチボチやってます・・・という状況になったのもむべなるかな,という気がする。
それ故に,段々とヒューマン路線が深化していった面がある。本書の表題作である「空のむこう」と「スノウ」は,最初雑誌で読んだ時にはそれ程でもなかったのに,今このトシになって読み返すと,随分と「泣ける」話になっていることに改めて気が付かされた。何故か?
この2話は,西洋風ファンタジーと時代劇という異なる背景の作品であるが,主人公の境遇がよく似ているのである。「空のむこう」では原因・治療法とも不明の病が間欠的に流行する国の若い王,「スノウ」では二つの強国に挟まれた弱小国の若い領主である。前者は古い慣習に従って幼なじみの恋人を「生ける人柱」にしてしまい,後者では,好きになった雪女(?)と駆け落ちすることもできず,時の勢いを得た一方の強国から滅ぼされてしまう。・・・と,ストーリーを書いてしまうと何らカタルシスの得られない,淡々としたマンガのように感じられるだろうが,そのような状況に至る理由をきちんと面白く語ってくれているのである。詳細は本書を読んで確認してもらうとして,最終的に納得したのは,この二話の主人公の,状況に対して全く何の解決策も持てない無力さ,なのである。これが世間に対して無知な頃には分からなかったんだよなあ。今なら,「あーもー全くうざってぇ」とは内心思いながらも,限られた資源と状況を考えて,出来ること出来ないことを冷静に判断できる。そーゆーお年頃になって,初めて感動できるタイプの作品なのである。それが,最後に遠藤お得意のヒューマンでまとめられてしまっては,もう,こりゃオジサンもオバサンも涙腺がつい緩んでしまうのは仕方のないことでしょう。あーあ。
ということで,人生そろそろアキラメ感が漂う今日この頃の方には,ちょっと身につまされて,最後にほろっと来る作品もよいではないかな,と思う,オジサンお勧めのマンガなのであります。松尾オバサンともども推薦しておきませう。
小林信彦「出会いがしらのハッピー・デイズ」文春文庫
[ Amazon | BK1 ] ISBN 4-16-725614-2, \524
現在も週刊文春にて連載が続行中のコラム「人生は五十一から」の第三弾,2000年分をまとめて文庫化したものである。
相変わらず,偏屈江戸っ子下町っ子ジジイぶりが絶好調で,ファンとしては大変嬉しい。特に近年の政治については居ても立ってもいられないらしく,激しく罵倒しまくっている。とはいえ,そこはやっぱり著者の人柄が出てしまうらしく,あえて全てを物語らず,舌足らずにぷつんと打ち切ってしまう。こちらはもう慣れたモンだから,別段どうとも思わないが,所見の読者は「あれあれ?」と戸惑うのではないかな。
著者から見れば若いワシは,今の小泉政権については基本的に支持しており,昔の首相よりは大分マシという印象を持っている。従って,著者の意見には首をかしげるところが多いのだが,「そういう人もいるのだな」ぐらいにしか感じないのは,口汚く罵れない上品さ故なんだろう。
エンターテイメントの目配りの良さについては,ちょっと衰えたところもみられないではないが,基本的には変わらない。伊東四朗・Clint Eastwood・USAのEntertainment贔屓はそのままである。昔話が多くなってきたのは,自分が語っておかなければならないという使命感が強くなってきたせいだろうか。個人的はそちらの方が為になるし,面白いのでありがたいのだが。
久々の一気読み。こういう「含み」の多い文章は,通り一遍のわかりやすさを求める現在の風潮には反しているが,それだけに貴重である。まだまだ頑張って,更なる愚痴が出ることを期待して止まない。
Pet Shop Boys, “Pop Art” [Import]
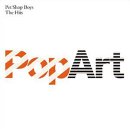
[ Amazon ]
CCCDにばっかり係煩っても仕方がない。少しはCDの内容に触れないといけませんな。
これは1985年の”West and Girls”から,2003年の”Miracles”と”Flamboyant”までのPSBヒット曲を集めた,所謂ベスト版である。曲リストは上記Amazonへのリンクを辿って頂くと見ることができる。もちろん公式サイトでも確認できる。
某浜松のCDショップにて「まだやっていた」というPopが張り出されているぐらいだから,もう20周年になるのかな。いやぁ,長い長い。しかもれっきとしたチャカポコテクノで,今も活動中ってのが凄い。この息の長さは,コアなファン層が老化しつつも確実に存在し,コンスタントにセールスを維持していることの証でもある。もちろん,ワシも老化しつつある極東在住ファンの一人である。
で,全35曲,通して聞いてみて,改めて思ったのは,PSBの全てはちょっともの悲しいテクノ音とNeilのオタッキーなVocalにあるんだってこと。アレンジにかなりの幅があっても,この二つが混入していることでPSBというハンコを付いていることになり,まごうことなきPSBの曲になってしまっているのである。・・・これを書きつつ,ちょうど流れてきたのが近作の”I Get Along”である。テクノ色の薄い,心地よいエレキが全体を覆うこの曲でも,NeilのVocalがほのかなテクノ色を感じさせてくれるのである。
個人的には,最新作の”Flamboyant”がいい。老成でもないマンネリでもない,でも挑戦しすぎて枠を外れていない活動ぶりが知れ,曲調も相まってほっとする一曲である。・・・とか言っているうちに”Rent”だぁ~。体が自然に揺れる~のでこの辺で失礼します。
筒井光春「うつと自殺」集英社新書
[ BK1 | Amazon ] ISBN 4-08-720239-9, \660
中高年の自殺が減る気配を見せない。ようやっと景気が一息つこうという時勢になってきたが,じゃあこれからは減るのか?となるとかなり疑問だ。あまりに不況期間が長かったため,各個人の仕事能力をシビアに見極める風潮が定着してしまった。何らかの理由で,「出来ない奴」という烙印を押されてしまえば最後,新卒者なら就職は難しくなり,既に社員となっているベテランでも,あの手この手で退職に追い込まれる。こうなってしまうと,ある程度は「出来る奴」と思われている人々も恐れおののき,我先にと能力合戦に突入していくことになる。しかも,定年まで続くロングスパンの競争である。この競争に勝つ・・・には至らないまでも,脱落することなく戦線内に踏みとどまるためには,自己管理能力が不可欠である。勉学に励むとかスポーツクラブに通い詰めるとか,そーゆー現時点の能力を高めることよりも,いかにこのストレスフルな社会で精神の安定を保つことができるか,ということが何より大切である。どーも,抜きん出た勝者って人達と見ていると,勉強が抜群に出来たとかスポーツ万能であったとかという以前に,精神的なタフさを生まれつき保持していたか,あるいは人生のどこかで獲得したか,どちらかではないかと思えるのだ。もちろん,単なる憎まれっ子ではダメで,プラスαの能力があってこその「勝ち」ではあるんだけど,それがない「憎まれっ子」であっても,長生きだけはするんじゃないかと思える。
ちょうどとあるワシと同年配の若手作家が自殺したという報道があって,そんなことをつらつらと考えていたところで本書が首尾良く出版され,こうしてワシの手に収まっているのである。
著者は「心療内科」の専門家(権威かどうかは知らない)であって,既に何冊か著作もあるようだ。そのせいか,なだいなだ並に読みやすい文章であり,寝床でうつらうつらしながら読んでいたら数日で読破できてしまった。内容を一言で言うと,中高年以上の自殺の原因には,かなりの割合で「うつ病」,あるいはそれが疑われるケースが存在するので,「うつ病」とはなにか,どのような症状なのか,どのように治療するのか,どんな場合にうつ病になるのか,といったことを世間に知ってもらい,適切な予防と治療を行ってもらおうというものである(長いぞ)。ふーん,うつ病って薬で治るんだ,ってのが一番感心したところ。すぐに回復するという訳ではなさそうだが,適切な治療を受ければ回復するってことを知っただけでも660円の価値はあったな。
不満が残るとすれば,まあこれは厚みに制限のある新書に望むのは酷かも知れないが,もちっと社会的な考察が欲しかったかな,という点であろうか。本書P.23に自殺者の年代別(1960年と2000年)比較のグラフというのがあって,このデータを見ると,1960年には自殺者の男女比率が57%(男) : 43%(女)なのに対し,2000年には71% : 28%となっている。どーも,この不況のプレッシャーは男に偏っているようだ。この辺の解説が欲しかったかなー,というのは無い物ねだりというものかしらん?
専門家が書いただけあって,うつ病は特殊は病気ではなく,誰にでも,特にマジメ人間に起こりやすい疾患であること,その病気のメカニズムと治療法については「なーるほど」と納得できる記述がなされている。ワシのようなズボラ人間には無縁かも知れないが,周囲でもうつ病になってしまった知人をちらほら見かける昨今,この病気に対する耐性を付けておくためにも一読をお勧めする。
酒井順子「負け犬の遠吠え」講談社
[ BK1 | Amazon ] ISBN 4-06-212118-2, \1400
この日記でも既に言及しているし,目下ベストセラー路線まっしぐらの本を今更紹介してもねぇ・・・と躊躇していたら,「東京人」5月号にて鹿島茂が,短いページ数ながら本書を「今更ながら」「面白かったので」紹介していた。別段それが悔しいとかいうのではなく,殆ど本書のあらすじ紹介みたいなその書評を読み,「オスの負け犬」である不肖・この私めは,負け犬としての義憤に駆られたのである。所詮,鹿島先生はオスの勝ち犬であるから,勝ち犬には描き得なかったであろう本書の価値をもっと賞賛しておく必要がある,と判断したのである。
そもそも,オスの負け犬本と呼ぶべきものは昔から存在した。ワシはぼちぼち負け犬として一生を送る可能性が高まってきた三十路前半から,この手の負け犬本をボチボチ漁ってきたし,手本とすべき先輩の負け犬を見つけては生きる糧としてきたのである。ここでは先輩の「オスの」負け犬についての言及はせず,オスの負け犬本だけを紹介しておこう。
負け犬の先駆者と言えば,海老原武「新・シングルライフ」である。これより以前に元祖「シングルライフ」という本を上梓しているらしいが,あいにく未見である。本書は「歩く裏切り者」津野海太郎曰く,「戦うひとり者」というぐらい,先鋭的な負け犬の主張を込めた思想書(おおげさ?)である。独身者であるが故の,世間からの攻撃・圧力・同情に対して果敢に反論を試みている。そして,世間になるべくご迷惑をおかけしない独身者としての生き方を提示して,本書を締めくくっている。負け犬たるワシをして,勇気づけられることの多い本なのだが,その海老原をして「自分は状況シングルからそのまま今日まで来てしまった」と告白している。つまり,独身者たる身分は自ら力強く選択したのではなく,なし崩し的に今日まで来てしまった,というのである。これは「結婚できるならした方がよい」という世間一般の常識を肯定しているのであって,自らの生き方をよしとはしていないのである。つまり,「自分はオスの負け犬である」ことをちゃんと認めているのである。酒井の前に,先駆的な本書があったことはもっと広く知られてよいように思う。
勿論,海老原の本は「オスの負け犬本」(しかも大分年上)であるから,メスの負け犬にとっては物足りない面もあったろう。しかし,メスの負け犬は酒井も含めた「女性作家」を探せば,いやぁ,もぉ,酒井が指摘するようにマスコミ業界同様,負け犬だらけであって,ちょっと挙げただけでも大先輩には森茉莉(バツイチだけど)を筆頭に,群ようこ,中野翠,岸本葉子・・・と評論家を名乗る人を含めれば枚挙に暇がない。しかし,彼女らにはあまり「負け」という意識がないようで,本書のように「世間的には負け負け負け・・・」と切々(飄々?)と敗北ぶりや愚痴を述べまとめたものは殆ど存在しなかったのではなかろうか?少子化に歯止めがかからず,いよいよ移民政策まで叫ばれるようになった昨今,お国に協力する気持ちはなきにしもあらずなのに,世の中,オタ夫やダメ夫やブス夫やダレ夫ばっかり氾濫して私らのような負け犬には飛びついてくれない・・・という女性陣から観た真実を述べた本書は,満を持して登場したと言ってよい。何たって,帯の文句が「嫁がず/産まず,/この齢に。」である。「ああっ,この本は私のことを書いているっ」とギクリとした方は相当数,いるのではないか?
単純に考えてみれば,人間は雄と雌が存在して,それは生殖のためにあるのだから,雄と雌はくっついているのが自然な姿なのである。そして,自然界の生存競争は自らのDNAを残すことが出来るか否かで勝ち負けが決定するのである。であるならば,くっついていない雄も雌も,生存競争から脱落した「負け犬」に他ならない。自ら「負け」を選択したかどうかは,本人のプライドに関係するだけであって,自然界から見れば負けは負け。さっさとその事実を認識し,遅まきながら「勝ち」を目指すか,「負け」を認めて子ども以外の価値を創造すべく,仕事に邁進するか,どちらかを選択しなければならないのである。このような酒井の主張は極めて明快だ。本書が,メスだけでなく,オスにも,そして勝ち犬にも読者を広げていったのは,このような単純かつ合理的な主張が,酒井の円熟した筆力によってユーモアにまで昇華している為であろう。もう,負け犬連中は涙を流しながら「こっ,これって私(俺)だよ~」と叫び,勝ち犬連中は「負け犬ってそうなんだよな~」と勝者の余裕を持って本書を楽しむことが出来る。ワシが義憤を駆られたのは,鹿島先生の書評にこの「勝者の余裕」を感じたからに他ならないのである。ぐぞぅ~。
と言う訳で,本書に触発されたオスの負け犬どもは,さっさと海老原先生の「新・シングルライフ」も読むように。酒井ばっかりよい目にあってはイケナイ。よいな。