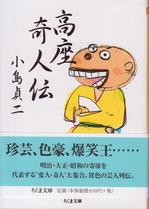[ Amazon ] ISBN 978-4-480-42615-4, \950
古谷三敏「寄席芸人伝」を読んで以来,芸人のエピソード集で面白そうなものがあれば読むようにしている。芸人・学者・教師には奇人変人が多いと言われているが,実際その通りで,ことに現代のようにモラルのない人間があっという間に排除されるようになる前は,よくもまぁこんな生活ぶりができたモンだと呆れかえる事例が結構ある。実際,これが身近な知人とか肉親に居たならたまらないだろうが,火の粉の降りかからない距離から遠目で見ている限りは,「ああまたやってるよ」と気楽な見せ物のように楽しめる。もちろん,「楽しめる」なんてものではないレベルまで逝っちゃっうこともあって,本書で言うなら「気○い馬楽」の生活ぶりがそれにあたる。そんなトンでもない噺家でも,死んだ後で二十日祭が開かれたり,故人を偲ぶ地蔵まで造られるんだから,人の評価ってのはスッキリといかないもんだなぁとシミジミ思う。
本書は1979年に出版されたものを文庫化したものである。時期的に見て,多分,寄席芸人伝のネタもとの一つじゃないかなあと想像する。実際,「気○い馬楽」も含めて,「あ,これはあの話に出てきたエピソードだ」と気がついたものが結構ある。さすがウンチクマンガを標榜するだけあって,古谷先生,勉強していたんだなぁと感心する。もちろん,エピソードがそのままストーリーになっているわけではなく,きっかけとして使っているものばかりである。
本書は,初代三遊亭円遊,三代目蝶花楼馬楽と同時代の柳家小せん(「め○らの小せん」),柳家三亀松,二代目三遊亭歌笑の評伝を中心に,小さな噺家・芸人のエピソード集を挟んで編まれている。単純に面白い小説としてではなく,噺家がその時代にどんな芸を見せ,それが現代にどのように繋がっているかも記してある点,歴史読み物としても役に立つようになっている。が,中心はやっぱり噺家の生き様と死に様だ。その中でも,やはり馬楽のそれは図抜けている。
芸人として優れていたことは本書の中核であるこの五人に共通している。しかし,女性からはもてなかった円遊は円満な夫婦生活を送り,道楽が過ぎて三十路になった途端に失明した小せんも夫人に助けられて有料落語指南所を営み,三亀松は遊びに狂っても最後は夫人に看取られて死に,歌笑は夫人にぞっこんだったことを考えると,この四人は常識人と言えるが,馬楽の晩年は完全に破綻している。最初の師匠をしくじって破門になるわ,博打中に警察に捕まって監獄にぶち込まれるわ,生き別れになった妹を取り戻した途端に売り飛ばすわ,あげくに頻繁な吉原通いが祟って明治末に発狂する。何度か発作を起こして入退院を繰り返した後,肉親にも見放され,最後の頼みの吉原(最後の頼みがこれかよ)も炎上し,失意と孤独のうちに五十一歳で死ぬ。まぁ,今なら妹を売り飛ばした時点で犯罪人だ。それも東北の貧しい農家がやむを得ず,というのとは正反対で,単純に遊び金欲しさというんだから,非道というほかない。
それでも死後に故人を偲ぶ集まりがあったり,馬楽地蔵ができたりするのは何故なのか? 芸人として優れていたことは確かだが,愛される要素があったからとしか言いようがない。そしてその要素は,この破綻した生活ぶりにあるのだ。
馬楽にはもう一つ,インテリという側面もあった。仲間から蚊帳を買うために集めた金を「三国志」の本を買うために使ってしまう。そして狂ってからも漢詩を書いちゃったりするのだ。こういうメンを勘案すると,総じて「その知己やよし」と,芸人仲間からは愛されていたとしか言いようがない。
おもしろうてやがて悲しき・・・というのは,破滅型芸人の人生を描写したような文句である。本書の表紙は南伸坊の,一見ユーモラスな噺家の絵だが,本書を一読した後に見ると,ピントの定まっていない描線と出っ歯が目立つ大口が何やら不気味な印象を与えている・・・ように見えてしまう。本書で小島が語った芸人,特に馬楽は,非道な馬鹿,と一言では片付けられない人間に潜む魑魅魍魎を体現しているように思えてならない。